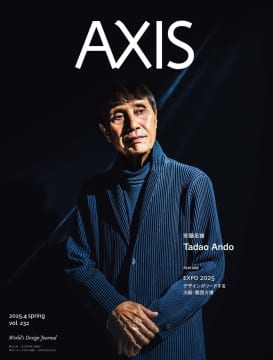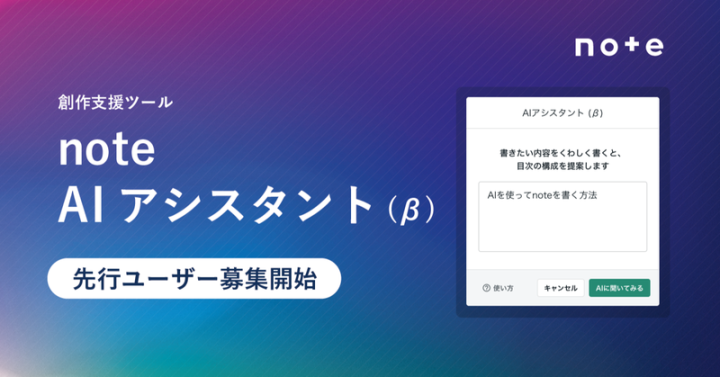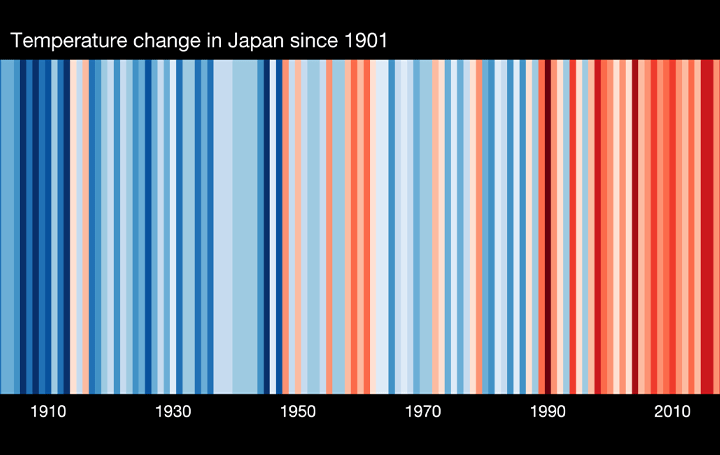REPORT | アート / カルチャー / テクノロジー
16時間前

当日上映された高倉一紀氏の作品「Deep Dream」より。
2025年3月27日夜、東京・渋谷の映画館「シネクイント」で、OpenAIによる動画生成AIモデル「Sora(ソラ)」を活用した短編映像の上映イベント「Sora Selects: Tokyo」が開催された。このイベントでは、世界各国のクリエイターがSoraで制作した多彩なショートフィルム作品が披露され、最新AI技術による映像表現の可能性が観客に向けて紹介された。

イベントには、OpenAIからプロダクト&エンジニアリング責任者のローハン・サハイ氏と、アーティストプログラム責任者のスーキ・マンスール氏が来日し登壇した 。また日本人クリエイターでは、高倉一紀氏やKaku Drop(カク・ドロップ)といった、Soraのクリエイタープログラムに参加したアーティストがステージで作品制作の経緯を紹介した 。実は今回の「Sora Selects」はニューヨーク、ロサンゼルスに続く世界3都市目の開催となり 、この夜は日本を含む世界各地から選ばれた約10本の短編映像作品が上映された 。東京での開催はSoraの大きなユーザーコミュニティが存在する日本への強い期待もうかがわせた 。

プロダクト&エンジニアリング責任者のローハン・サハイ氏。

アーティストプログラム責任者のスーキ・マンスール氏。
SoraはOpenAIが2024年12月に一般提供を開始した最新の生成AIサービスで、テキストによるプロンプトや画像・映像入力から、新たな映像を自動生成できるものだ 。最大約20秒程度の短い動画クリップを生成でき、まるで「文章で書いたシナリオを映像化する」ような感覚で作品制作が行える。その特徴を活かし、アイデア出しやブレインストーミングの段階で活用するクリエイターも多い。サハイ氏によれば、現在Soraは完成度の高い映像を一発で思い通りに出力できる段階には至っていないものの、逆に予想外の生成結果が発想転換を促すケースにつながっているという 。実際、広告制作の現場でもSoraは導入が始まっており、背景や部分修正、XR技術との組み合わせなどに加え、コンテ映像を用いた企画提案やクライアントとの合意形成の場面で活用され始めている。
一方、マンスール氏によると、アーティストプログラムでは、正式にローンチする前の約1年間、世界45以上の国と地域から集まった450名超のクリエイターと共にSoraのテスト利用と作品制作を行い、合計300万ドル規模の制作支援金を提供してきたという 。そうして生み出された数多くの映像作品の成果発表の場として企画されたのが「Sora Selects」であり、東京のイベントもその一環だ。「Soraならではの映像体験を届けたいし、AIだからこそ生まれる予想外のクリエイティビティに注目してほしい」と彼女は語った。
また上映された作品は、フォトリアルな実写風映像からゲーム風のピクセルアート調アニメーションまで、非常に多彩なジャンルに及んだ。いくつか作品を見てみよう。
高倉一紀が制作した「Deep Dream」は、1カットあたり約20回もの試行を重ね、偶然生成された映像効果を積極的に活かした実験的な映像作品だという。
カナダ・トロントの映像制作チーム、shy kidsによる「My Love」は、2匹の猿のラブストーリーを描いたユニークな短編で、テキストや画像、既存動画を組み合わせて何百回もの生成を繰り返し完成させた力作だ。
ロンドンと上海を拠点に活動する映像作家Junie Lauの「LOVE FROM VOID」。時空を超え、対話を求める仮想の恋人たちを描いた作品。
シンガポール出身のアーティストNiceauntiesによる短編作品。魚市場で休みなく働いていた祖母の姿をモデルに、写真も映像も残っていない記憶を頼りにSoraで映像を生成した家族の記憶の物語。
〜 Echoes of Grace 〜
ご覧あれ 🔈🔈🔈
Powered by #Sora
@OpenAI #genai #動画生成ai pic.twitter.com/uOLuwfloGA
— Kaku Drop 架空飴 (@KakuDrop) November 21, 2024
日本人クリエイターKaku DropによるAI映像作品。「日本」「女性」「ダイナミズム」をテーマに独特の美学で想像と現実の境界を融合させた映像表現が特徴。
OpenAIの意図は明快だ。生成AIを通じて、映像制作の可能性を拡張し、これまで限られた環境下でしか表現できなかった創造の機会を、より多様な人々へと開放しようとしている。その方針は、マンスール氏の「これまで困難だった映像表現を可能にする作品を届けたい」という発言にも端的に示されている。Soraは単なるツールではなく、個人の想像を可視化し、映像制作における新たな可能性を切り拓く存在として提示された。
注目すべきは、生成AIが生み出す民主化の力だ。これまで資金、技術、環境といった障壁により、映像制作に携わることが難しかった層にも、新たな表現の扉が開かれつつある。特に、伝統的な映画業界やクリエイティブ領域では声を上げにくかった多様な表現者たちにとって、AIによる映像生成は独自の視点を世界へ届けるための現実的な手段になり始めている。
生成AIが映像表現に与える影響は、まだ始まりに過ぎない。今回の東京でのイベントは、誰もが物語を紡ぎ、独自のビジュアル言語を探求できる未来への静かな出発点となった。披露された作品群と、観客の強い関心は、この新たな表現領域が確かに開かれつつあることを感じさせた。![]()