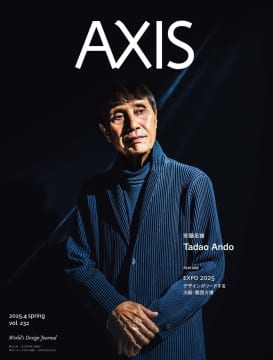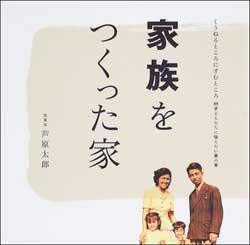東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。
グラフィックデザイナー 辻尾一平さん
「おもしろい」を追いかける
サイン計画や商品企画、ロゴデザイン、エディトリアルデザインなど、グラフィックデザインを軸とした幅広い分野で活躍している辻尾一平さん。自主制作も積極的に行い、ユニークな発想から生まれた作品をウェブサイトやSNSで発表し、注目を集めている。その発想の源はどこにあるのか。辻尾さんのオフィスを訪ねた。
グラフィックとプロダクトの中間にあるものつくりたい
――辻尾さんが手がけられた「アロマトグラフィー」は、パッケージの見た目の変化が楽しめるアロマという発想がとてもユニークで面白いと思いました。制作にあたって何が最も大変だったのでしょうか?
水だときれいに吸い上がってインクがにじむのですが、香りをつけるための液剤を混ぜると綺麗ににじまなかったんです。だから、液剤の配合から考える必要がありました。吸い上がるだけでなくて、どのような配合であれば、インクが綺麗ににじむのか、本当に手探りで試していきました。新しいことをやろうとすると何かしら意外な落とし穴が出てきて、それを解決するために苦労することはよくあります。案出しの段階では、「削るアロマ」というのも考えました。普通に置いて香るだけではなくて、寝る前などにガリガリと削ると強く香るというものです。でも、プロダクトに寄りすぎている気がしてやめました。グラフィックとプロダクトの中間にあるものつくりたいという想いがあったので、最終的にパッケージがさまざまな機能を果たす方向に持っていきました。


「アロマトグラフィー」。水を加えたボトルをひっくり返してパッケージに差し込むと、パッケージに香りのある液剤が染み込み、ディフューザーとして機能。 パッケージに特殊なインクでプリントしているため、徐々にプリントがグラデーションに変化し、美しい色の移ろいを楽しむことができる。
――多機能ペンのパッケージ「KURUPAKE(クルパケ)」も、プロトタイピングを繰り返してデザイン開発を進めたと伺いました。
これはパッケージで何ができるかというお題を振られて、回答する大喜利的な面がありました。私の今までの仕事をご覧になってからの依頼だったので、単純にパッケージの意匠をデザインすることではないだろうと。外側の層と内側の層の重なりによってアニメーションができあがるなど、さまざまなアイデアを練りました。最終的に、文字の一部をペンにして、それを回転させることによって、文字が3種類切り替わるという仕掛けにしました。最初はパッケージを回転させたときに並ぶ文字を真っ直ぐな配置にしていたのですが、文字が重なる部分に“無理やり感”が出てしまうので、あらかじめ上下にずらしてバラつきを持たせることで解決しました。

「JETからくりギフト KURUPAKE」(三菱鉛筆)。外側のパッケージをクルクルと回すと、内側の紙に印刷してあるデザインの重なりによって メッセージが変化する仕掛け。
――デザインにあたっては、ある程度ターゲットを想定しているのでしょうか?
全くしないですね。誰が見ても明らかで、人を選ばないデザインを目指しています。ペルソナ的な考え方は希望的観測のようであまり好きではなく、こういう人に刺さりそうより、自分がまず面白いと感じるかを大切にしています。
――大切にしているご自身の哲学や信念はありますか?
「おもしろい」と感じたことを常に大切にしています。日常からアイデアを拾い集めて、スマホにメモするようにしているんです。これは学生時代から続けていて、今はだいたい100スクロール分くらいのメモがたまっています。集めたアイデアはあえて整理せずに散らかしておきます。そうすると、意外な組み合わせが生まれるんです。
――普段はどのようにインプットされていますか。
直面している課題とか、出さなきゃいけないアイデアみたいなものを念頭に置いた状態で、改めてさまざまな情報に触れることが大事だと思っています。なんとなく普段見過ごしていたものでも、そういう脳みその状態で見てみると、新しい発見やヒントにつながるということが多いんです。インプットというよりもアイデアを出すための素材を集めている感じですね。
――どんなことをメモされるんですか。
日常生活で、「あれ?ヘンだな」と感じたことが多いですね。例えば、指の名前に一貫性が無いということ。人差し指と薬指は役割で命名されていて、中指は位置で、親指と子指はまた別の基準で、と名前の付け方に一貫性がないのではないかなど。世の中には整合性がないけども浸透しているものがかなり多いと思っています。冷静に考えたら切手も裏側を舐めるのはちょっと気持ち悪いじゃないですか。ほとんどの人はのりを使うかもしれませんが、それでも舐める貼り方を許容するプロダクトになっている。フラットな目線で見たらヘンだなと思うものが意外と多いと思っています。

過去からつながる、クリエイティブの原動力
――デザイナーを目指したきっかけはなんですか?
中学では勉強をガッツリやっていて、高校は進学校に通っていたのですが、急に勉強に対してやる気をなくしてしまったタイミングがありました。絵を描くことが好きだったのですが、絵で食っていく自信もなく、親が厳しかったこともあり、絵の道に進もうとはあまり思えなかった。そこで、デザインだったらもう少し社会との結びつきが強くて食いっぱぐれなさそうと考えたので、デザイナーという職業についていろいろ調べはじめたのがきっかけです。
――どんな学生だったのですか?
納得できないと人の言うことを聞かないひねくれた学生でした(笑)。学校にはふたつ門があって、最寄り駅からは正門ではないほうの門が近く、いつもそこを使っていました。入学当初、登校時はどちらの門を使っても良かったのですが、それがある日突然、正門だけになりました。つまり駅からすごく遠回りしないといけないようになったんです。今思えば何かしら別の理由があったのかもしれませんが、当時は門に立つ先生を減らすためだと思い、ひとりの人員削減のために、これだけ多くの人間を遠回りさせるのが本当に気に食わなかった記憶があります。なので、いつも近いほうの門を飛び越えていました。何度か見つかって反省文を書かされたので、今思えば逆に効率は悪かったですね(笑)。不条理なことや合理的ではないことを許容できなかったので、先生にしてみれば嫌なタイプだったかもしれませんね。でもどこかしらで今の制作スタイルにつながっている気がします。
――大学に入ってからのご自身の転換期のようなものはありましたか?
ひとつ目の転換期は卒業制作で、一年間朝から夜中まで考えてつくることをつづけたんですが、そういう習慣が身体に染み付いたと思います。そのときの体力で今も走っているところはあるかもしれないですね。もうひとつは「珈琲牛乳のグラス」を出したときです。これは多くの反響をいただき、その後の名刺代わりのような作品になりました。

「珈琲牛乳のグラス」。注いだ飲み物によって文字の表示が変わる。
――その頃と今の仕事の進め方や、デザインに対する考え方は変化しましたか?
考え方は変化していないです。やっていることもほぼ変わらない。ひょんなことから見つけたアイデアに夢中になって、それを「多くの人と共有したい」という想いがモチベーションです。
――いちばん大変だったことは何でしょうか。
独立したばかりのときにプロダクトをつくりたかったんですが、お金がなかった。クラウドファンディングでお金が集まったんですが、僕のミスでお金が振り込まれる前にプロダクトを発送しなければいけないスケジュールになっていたんです。それで仕方なく日払いの肉体労働をしました。身体中がバキバキになるまで働いたのに、たったの4000円しかもらえなかった。そのときに、本当にデザインだけでなく、その周辺のこともしっかりやらないといけないと感じました。
――AIの登場で、デザインも変革の時代を迎えていると思います。AIとどのように関わっていきたいとお考えですか。
よりコンセプトを練る力が重要になってくると思います。例えばamazonのロゴは、aからzに矢印が引かれることで、品揃えの豊富さを表していますが、このような捻りのあるコンセプトをAIで導き出すのは、現状難しいと思います。逆にモチーフが直接的なロゴだったり、短絡的な企画はAIでも発想することが可能な段階にきていると思います。AIの提案を上手く組み合わせて綺麗に着地させられる人が、これから活躍できるのではないでしょうか。
――最後に、デザインを学んでいる学生にアドバイスをいただけますか。
ありきたりな言い方ですが、自分がおもしろいと思うことをやってほしいです。人によって何を幸せに感じるかは違うので、それが良いか悪いかはその都度立ち止まって考えれば良いと思います。ひとまずやってみる。痛い思いをするのも財産になりますから(笑)。(取材・文・写真/東京都立大学 インダストリアルアート学域 上野美優、海野未洋、久保田恭平、佐々木陽香、嶋村有彩、杉谷望来、卓 暁桐、森澄優己、庾 佳希、柳原萌生)

辻尾一平/1992年大阪生まれ。2016年にグラフィックデザインコースを卒業後、トラフ建築設計事務所、TAKAIYAMA inc.を経て、2019年に独立。フリーランスのグラフィックデザイナーとして、サイン計画や商品企画立案、ロゴデザインを手がける一方、自主的な制作を続け、WebサイトやSNSでの発表を続ける。http://toal.co.jp