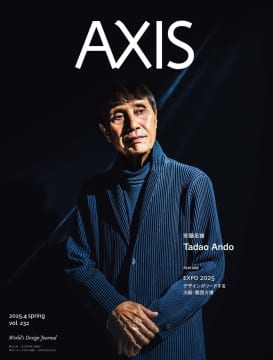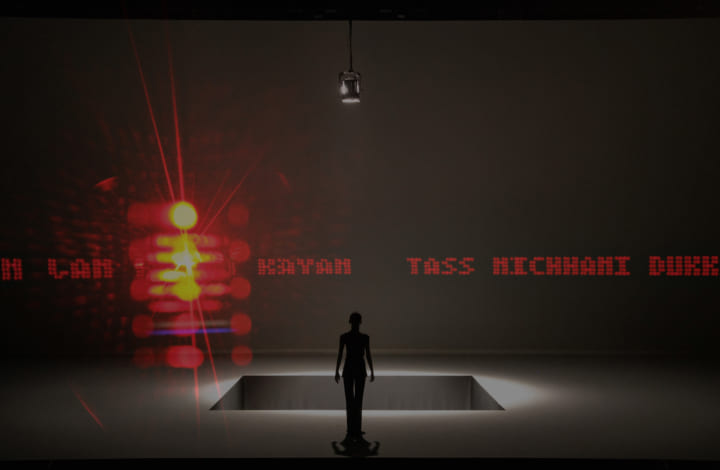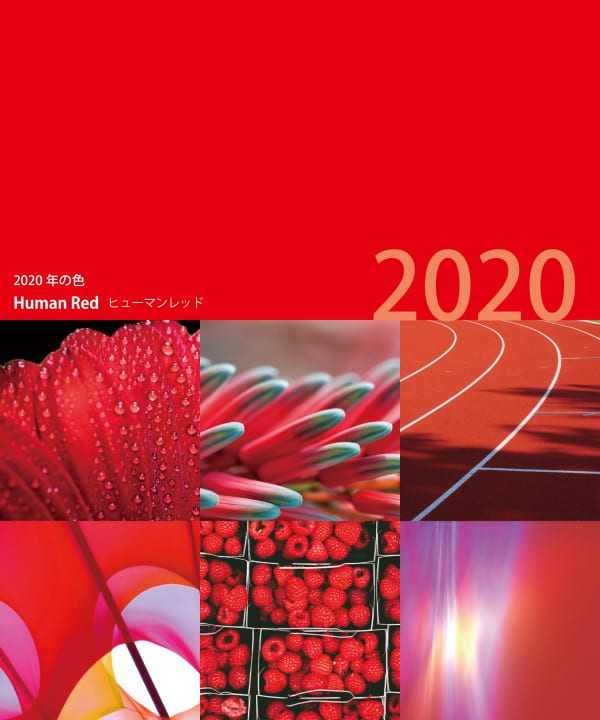MEMBERSHIP | ソーシャル
2025.02.20 16:08
水の恵みは山の恵みと不可分で、日本はその利に浴してきた。一方で、人間が都市生活を謳歌し自然を制御してきたツケは、災害の多発や環境の悪化などとして表面化している。デザイン視点でこれにいち早く切り込んだのが、井上岳一(日本総合研究所創発戦略センターチーフスペシャリスト)と藤崎圭一郎(東京藝術大学教授、GOOD DESIGN MARUNOUCHIディレクター)である。ユーチューブの「山水郷チャンネル」で2020年より、都市から離れて地域に入り、新しいナラティブ(物語)を求めて活動するデザイナー、クリエイターを紹介してきた。ふたりは今、どんな「水」の世界を捉えているのか語ってもらった。

水を巡る解像度が高まってきた
——井上さんは2019年に上梓した書籍『日本列島回復論:この国で生き続けるために』で「山水郷」というワードをあげ、山と水が変われば日本も変わる、島々が織りなす多様性がこの国のポテンシャルと説かれました。藤崎さんと山水郷のデザインとして地域で活動する人材を動画配信で紹介しています。「水」と聞いて、今、何を思い浮かべますか?
井上 造園家の高田宏臣さんが『土中環境』(建築資料研究社、2020年)で提示した世界観ですね。土の中には水と空気の道が毛細血管のように張り巡らされていて、そのミクロの水脈を通してあげると土が生き、山は引き締まる。しかし現代はコンクリートで土を固めているので、土は腐り、山も力を失っていると高田さんは指摘しています。土中の水の挙動をこういう解像度で捉えたものはかつてなく、山と土と水と海は全部つながっているんだと改めて教えられました。
藤崎 21年の「山水郷のデザイン展」で紹介した、岡山県西粟倉村の牧 大介さん(エーゼロ)も「百年の森林事業」として林業の活性化で森を元気にし、小水力発電や森林バイオマス資源の導入を進めながら、土中環境の重要性を語っていましたね。