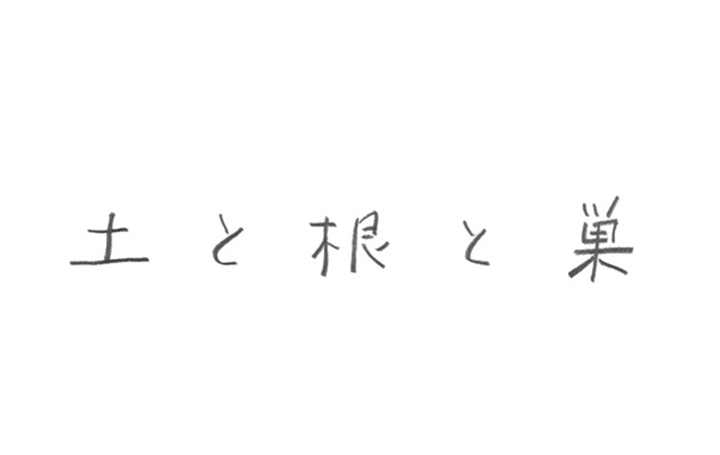REPORT | プロダクト
2024.11.07 12:47
まもなく100周年を迎える、1928年創業の広島の木工家具メーカー、マルニ木工。これまで100年先に残る家具づくりに取り組んできた同社が、この秋、伝統に回帰するように「Tradition」と題した家具シリーズを現代にあわせて再構築した。

「アントワーヌソファ」は、2015年以来コレクションから外されていたがリデザインして復刻。ファブリックをボタンで締める工程は同社でも限られた職人しかできないという。
足元を見直すことに取り組もう
Traditionは「マルニにしかできないものづくり」です。そう話すのはマルニ木工代表取締役社長・山中洋だ。
山中がファミリーカンパニーのマルニ木工に入社したのは1999年。営業担当だった当時、住宅メーカー主催の催事にブースを出しても、他の家具メーカーには引き合いがあるものの、マルニのブースは見向きもされないことに愕然としたという。その頃の製品は、創業時からの流れを組む西洋様式のクラシック家具。猫足や装飾的な彫刻が特徴の家具のみであり、「HIROSHIMA」を含むMARUNI COLLECTION(2008年発売)はまだ誕生していない。黒川雅之や妹島和世ほか社外デザイナーにデザインを依頼したnextmaruni(2005年発売)の誕生もまだ先のことだ。2000年代初頭、製品の企画やデザインはすべて自社で行っていた。
「自社で企画すると、どうしても受け継いできたクラシック家具の延長になってしまい、突破口が見えなかったんです。そんなとき、深澤直人さんたちと出会いました。会社の流れを変えるため、マルニ木工の新しい姿を追求することに注力し、2008年、HIROSHIMA Chairを含めたMARUNI COLLECTIONが誕生しました。今やMARUNI COLLECTIONが会社の売上の半分を占めるまでに成長しています。一方でそれまでのクラシカル家具の企画開発はなおざりになり、止まっている状況だったのです」。
政治や社会が不確かな2020年代は、次の潮流を読むことが難しい。「この先のマルニの姿を考えたとき、再び外部のデザイナーと新しいものづくりをするという選択より、足元を見直すことに取り組もうと思いました」。

maruni tokyoでの展示より。ずらりと並ぶ「エドワードチェア」は同社が1974年より製造するロングセラー商品。今回のリブランディングではリバティ社のテキスタイルを用いた。
家具生産の工業化を実現してきたからこそ
新作発表が中心のミラノデザインウィークでも、今年は新しいデザインより過去の名作を見直す動きが見られた。とりわけ目についたのはエルメスやグッチといったラグジュアリーファッションブランドの展示だった。エルメスは歴史的アーカイブに所蔵されているオブジェと近作を並列して展示することで自社のヘリテージが今のクリエイションに息づいていることを示した。グッチは自社で家具を製造しないものの、1960年代から80年代のイタリアンデザインの名品を展示することで自社のものづくりがクラシックに立ち返る姿勢を表現した。というのも、グッチを傘下に抱えるケリングのデピュティCEOであるフランチェスカ・ベレッティーニは業績の迷走するグッチについて、「足元の強化が大切」と語っていた。どちらにも言えることは、単に過去から学ぶというよりは、その時代の家具を通して、当時のデザイナーやつくり手の視座に立つことだ。
並べてみると膝を打つことになるが、60年近く前のマルニの家具づくりがあったことで、現在人気のHIROSHIMAやFuguといった三次元曲線が特徴の椅子づくりが可能となった。マルニは1965年にアメリカから木材を三次元に削り出すことのできるカービングマシンを導入し、本来、ひとつひとつ手で削り出す彫刻的なデザインの量産化に挑んだ。この機械をもとに翌年には自社オリジナルのカービングマシンを製造。クラシック家具が持つ脚や笠木などのパーツの工業化に成功した。現在は、クラシック家具と同じ生産ラインでHIROSHIMAをはじめとしたMARUNI COLLECTIONを製造していることからも、クラシックの延長に今のコレクションがあることがわかる。こうしたものづくりは、創業時から家具の工業化を目指してきた同社の特徴である。マルニしかできない商機をそこに見出した。

バレリーナの足先のような脚を持つ「ベルサイユスツール」(左)と、螺旋状にねじった脚が特徴の「エジンバラスツール」。どちらも過去にはなかったハイスツールに変え、貫にスチールを加えている。
「とは言っても、マルニのクラシック家具は、私たちからすると、先人が何十年もかけてつくり上げてきたすでに完結している家具なんです。社内の人間では完成しているものを触ることに抵抗があります。そこで、Traditionのブランドマネージメントを外部の相馬英俊さんにお願いすることにしました」。
相馬は三越伊勢丹でリビング部門のバイヤーを長年担ってきた。例えば、昔からある和食器の形を崩すことなく、今の暮らしに合うように企画したり、マルニとはフシのある木材をあえてHIROSHIMAの製品に取り入れたりした経緯がある。相馬はアーカイブにあるクラシック家具を見直した。具体的には既存のラインの彫刻的なシルエットはそのまま活かし、張り地のカラーや素材を現在の暮らしに馴染むように変更することで「Tradition」として再構築を図った。

アーカイブに残る図面や型紙などから忠実に復刻した「アルバートウィングチェア」。背もたれが高く翼のような耳のついた、ゆったりとしたひとり掛けのチェア。
端材を活用した新たな家具づくり
しかし、そもそもマルニが従来得意としてきたクラシック家具に、今、商機はあるのだろうか?
「ホテルやレストランといった法人向けに可能性を感じています。最近のマルニの売上の構成比は、個人向けが圧倒的に多く、85%ほどを占めます。対して法人向けの比率は15%。BtoB事業に注力していきたい」と山中社長は意気込みを語る。
それは日本のこれからの社会を読み解いたうえでの方針である。人口が減少し、世帯数が減れば個人向けの家具の需要は縮小する。一方で、外資系ハイエンドホテルの開業は続く。ラグジュアリーホテルの共用スペースやレストランには、クラシックなデザインの家具が今も採用されることが多い。ホテルは使用頻度が高いため、修理やメンテナンスの需要もある。旅行客数が右肩上がりならば、今後もホテルやレストラン向けのマーケットは明るそうだ。
これまでのクラシック家具コレクションを構成してきた18世紀の英国で一世を風靡したヘップルホワイト様式のダイニングチェアや、19世紀のナポレオン様式のソファベッドなどは家庭向けを想定していたため、デザインが小ぶりだった。再構築したTraditionコレクションではコントラクト向けにプロポーションを変え、海外の大柄な人でもゆったりと使えるデザインに仕上げている。印象を大きく左右する椅子の張り地については、クラシックでありながらも、毎年トレンドを取り入れた豊富なデザインを発表する英国のリバティ社のファブリックを採用し、クラシック家具でありながらもコンテンポラリーさを感じさせる。

さまざまな装飾に加え、継手の技法により端材を角材として活用する。
さらに、現代性の点では、端材の利用が挙げられる。既存の家具づくりの工程で出てしまう端材を組み合わせ、新たな角材をつくり、Tradition家具の木材としているのだ。木目や色の違いなど端材の組み合わせ方によって、より木の風合いを感じるかもしれない。コントラクトという大きなマーケットに端材を使った家具が収まれば、家具づくりのサイクルにも好循環をもたらすだろう。
なお、Tradition家具のリブランディングにともなう展示「Manufacture -Allure of Tradition-」は、11月25日(月)までmaruni tokyoで開催中だ。(写真すべて/市川昂佑)![]()

左は、マルニ木工Traditionプロジェクトディレクターの相馬英俊、右はマルニ木工代表取締役社長・山中洋。