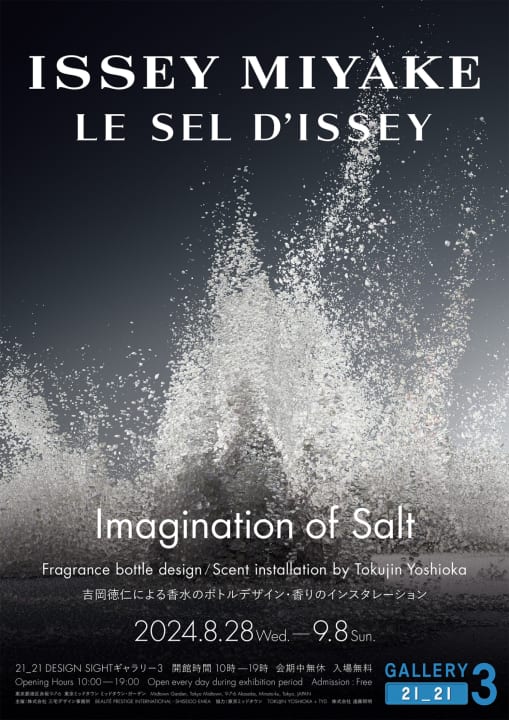PROMOTION | ファッション
2024.11.01 10:10

Photos by Masahiro Sambe
ISSEY MIYAKE(イッセイ ミヤケ) 2024/25 年秋冬コレクション「What Has Always Been」が展開中だ。同ブランドのデザイナー、近藤悟史の“今”に注目した前編に続き、後編ではコレクション制作に携わるデザインチームから3名のメンバーが加わり、「色」と「時」というキーワードから始まった、制作の具体的なプロセスについて紹介する。
日本の古典から言葉を集めた、夜明けから夕暮れへと移ろう色のパレット
2024年春、フランス・パリでISSEY MIYAKE 2024/25年秋冬コレクションのショーが披露された。会場は国立移民史博物館。フラスコ画に囲まれた吹き抜けのホールは、厳かな雰囲気に包まれていた。
ISSEY MIYAKE 2024/25年秋冬コレクション動画。
ショーの最後を飾るランウェイでは、モデルたちがまとった服が一列になって色のグラデーションを描く。その色の変化は一日の時間の流れを思わせ、まるで夜明けから夕暮れ、深夜へと移ろい、再び夜明けを迎えるようだった。
コレクション制作が本格的に始動したのは、ショーの半年ほど前。近藤は「まとう」という行為をとおして、色の根源的な美しさを表現したいと考えた。制作に向けて、デザインチームに「Clothed in Color, Clothed with Time(色をまとい、時をまとう)」という言葉を共有し、これを軸にデザインチームはあらゆるインスピレーションを求めて動き出した。
デザインチームのメンバーは「近藤によく言われることは、最初から服の形をつくろうとしないこと。テーマに対してリサーチを行い、フィールドワークに出かけ、柔軟な発想でアウトプットする。そうしてできあがった服ではない何かを、どうすれば服になるかをともに考えていくのが私たちのアプローチなんです」と話す。

近藤とともに、デザインチームはまず言葉のリサーチを始めた。「万葉集」をはじめ、「源氏物語」や「古今和歌集」のほか、文学や絵巻物など日本の歴史的な文献を調査。言葉を発掘してその情景について深掘りする考古学的プロセスには、新しいものづくりにつながる発見がいつもあるという。
「朝顔」や「松葉牡丹(マツバボタン)」、「三時草(サンジソウ)」など、特定の時間帯に咲く花々の名前。あるいは、秋に木々が黄色く染まる様子を表す「黄葉(こうよう)」や、葉が落ちる「落葉」といった季節感ある言葉。そして、夜の深まりを示す「深更(しんこう)」や夜明け前の「暁(あかつき)」など、空の変化を表す言葉が、本コレクションのために集められた。また、秋冬コレクションにふさわしく、「女郎花(オミナエシ)」や「藤袴(フジバカマ)」などの秋の七草を加えて、“言葉の色見本”ができ上がる。

チームメンバーが制作した色見本には、26の言葉と色が並び、真夜中から真夜中へと続く一日の時間の流れが表現されている。
これら26の言葉は、“時間の流れ”を表現するように並べられ、それぞれにふさわしい色が思案された。その色の並びは、ランウェイでモデルたちがまとった色のグラデーションそのものだった。
自然の美しさと向き合う、終着点を決めないフィールドワーク
「色からスタートしたコレクションだったので、比較的スムーズに進んだと思います」と近藤は言うが、それでも色決めの工程は毎回頭を悩ませる。ファッションの世界でよく使われる色見本帳を使わずに、デザインチームは自分たちで色をつくっており、今回は糸を染めたものを色見本として使った。
そうした色に対するこだわりには、三宅一生の強い想いが宿っている。
「例えば花ひとつでも、野に咲く花を三宅は大切にしていました。昔、私が花屋で買ってきた花で色見本をつくっていたところ、怒られたことを今でも覚えています。『野に咲く本物の美しさを見なさい』と言われました」と、近藤は懐かしそうに当時を振り返った。

デザインチームが拾ってきた落ち葉を使った柄のスタディ。
そんな近藤がISSEY MIYAKEというブランドを担当するようになった今、自然の力強さや機微と向き合う姿勢は変わらず続いている。フィールドワークはそのひとつだ。
デザインチームは、街を散策して道端に咲く名もない草花に目を向ける。海辺の植物や石を収集し、公園の落ち葉を拾う。そうした収集物や記録を共有して、「この葉っぱみたいな服ができたら面白いね」と語らい、思い思いの発想で手を動かしていく。

ISSEY MIYAKE 2024/25年秋冬コレクション「VIGOR(ヴィガー)」。
草花が持つ生命力を表現したロングコート「VIGOR(ヴィガー)」の柄は、そうした表現の模索から生まれたものだ。数十種類もの植物に直接絵具を塗って版画にしたり、その上からドローイングを重ねたりしたものがそのまま柄として採用されている。柄はプリントではなく、コットンとウールで編まれたもの。ウールに圧力をかけ、厚みを出す為に縮絨加工し、コットンとの素材の差を利用することによって、植物のディテールや生き生きとした刷毛目まで丁寧に表現した。

「VIGOR」の柄を描くまでにスタディした、直接植物が刷られた版画。
「フィールドワークから生まれるものは、このように直接デザインに反映されることもありますが、何にもならないこともよくあります」と、近藤は笑った。「それでも、自然との対話を楽しんで、いつもフィールドワークに出かけています」。
立体でも美しく、平面でも美しい 四角い布
「色」「時」「まとう」「自然」——。2024/25年秋冬コレクションを構成するたくさんの言葉たち。そこに連なるもうひとつのキーワードは「四角い布」だ。
服をつくる際は、身頃や袖、襟など、身体の曲線に合わせた複数のパーツを布から切り出すことがほとんど。デザインが複雑になるほどパーツの数も増えるが、布には繊維の向きがあるため、布地に対してパーツを取れる部分は限られてしまう。そのため、服づくりの際は布に無駄が発生してしまうのが常だ。

ISSEY MIYAKE 2024/25年秋冬コレクション 「ENCLOTHE(エンクローズ)」トップス。

「ENCLOTHE」トップスのパターン。正方形の型に襟と袖を通す穴を開け、襟に切り込みを入れたのみ。布と服の境目を探るように形がつくられた。
「最低限の要素で構成された服を目指したのが、この『ENCLOTHE(エンクローズ)』のトップスです。布の生地幅をフルに使い切っていますから、余計な部分はなく、捨てるところはありません」と、デザインチームは説明する。ヨコ糸に和紙、タテ糸にはナイロンとポリウレタンのストレッチ糸が使われた生地は、布の向きを変えるだけでシルエットが大きく変化してしまうため、トルソーに布をあてがいながら美しい陰影や布の表情を模索していった。

ISSEY MIYAKE 2024/25年秋冬コレクション 「ENCLOTHE WASHI AND WOOL(エンクローズ ワシ アンド ウール)」ワンピース。「ENCLOTHE」トップスの造形を発展させ、ワンピース型に落とし込んだ。
「ENCLOTHE PANTS(エンクローズ パンツ)」のこの型は、2カ所の縫製部分を解いてみると、ひらりと広がって一枚の四角い布に戻った。こちらは角のひとつが階段状に小さく切り落とされ、布面積の半分がわずかにカーブしている。
このようにデザインチームは「まとう」という原始的な体験を再現するため、衣服の原点であるただの一枚の布、それも生地幅そのまま、あるいは縦半分に裁断した四角い布を用いた。

ISSEY MIYAKE 2024/25年秋冬コレクション 「ENCLOTHE PANTS (エンクローズ パンツ)」。

「ENCLOTHE PANTS」のパターン。長方形の型がゆるやかにカーブしながらほんの少しだけ切り取られている。
布は一枚でつながっているため、例えば丈を長くすればほかのパーツに影響が出て全体のシルエットは大きく変化する。そうした布の動きを考慮しながら紙の上でデザインを検討することは不可能だ。デザインチームはひたすら納得する造形を探して手を動かす。パターンを調整し、それをまたトルソーに戻して形を整えるといった、試行錯誤を重ねる。

造形の検証で使用した、実物の1/2サイズのミニトルソー。
デザインチームの頭の中には、三宅のある言葉が響いていた。「立体でも美しく、平面でも美しいものをつくりなさい」。そうしてでき上がった服は、四角いパターンからは想像できないほど優雅で立体的で、身体にフィットするものになっていた。
ファッションの境界を超えた先にある、ISSEY MIYAKEらしさ
近藤はISSEY MIYAKEの制作について「私たちは常に新しい衣服をつくることを意識しています。今回は『色』と『時』をテーマにチームでリサーチをして、プリミティブで時間が経っても変わらない美しさを見出し、それを表現しました。ものづくりのヒントになるものは、どんな形であっても、どこでも見つけられる気がしています」と語る。
「チーム内におけるコミュニケーションのキャッチボールがうまくいったと思う」と今回のコレクションを振り返る。「テーマに対してメンバー全員が自然にキャッチボールできたとき、いい服ができることが多いです」。

ファッションブランドの組織は、デザインやパターン、縫製など専門分野ごとに分業制で運営されていることが多い。ISSEY MIYAKEのデザインチームはその境界が曖昧だ。
そうした才能を率いる近藤は、「デザイン画を起点に形にしていく方法が続くと、新しいものはなかなか生まれないと思っていて。直近の数シーズンでは、実際に布や紙を触り、手を動かしてスタディしていくなかで、チームと共につくりたいもののイメージをふくらませていくことが多いです」と話す。
常に次のコレクションに追われる日々のなかでも、少しずつ心に余裕を持てるようになってきたと話す近藤は、ファッションの垣根を超えることで、コレクション制作のあり方とは違う刺激を求めていた。
「ISSEY MIYAKEではコレクションを表現するショーやビジュアルにおいて、写真やアート、コンテンポラリーダンスなども取り入れています。また、衣服をつくることにおいても、ファッション以外の分野も視野に入れてリサーチし、その現場を体験するようにしています。それによって、ファッションにとらわれることなく、チームがどんどんやわらかくなっていけたらいいなと。それがISSEY MIYAKEらしさにつながっていくのではないかと考えています」。

デザインチームもまた、近藤の想いに賛同する。長年近藤と仕事してきたチームのひとりは、「物質的な豊かさというより、精神的な豊かさを求める人が多くなった現代において、日々の暮らしのなかの希望は、文化や芸術にこそあると思っています。それらは、季節を感じたり花を美しいと思ったりする人間の本質的な感情を育むからです。でも今、世界の激しい変化のなかで人間の営みは軽視され、文化や芸術の衰退が起きている。イッセイ ミヤケとして広い視野で活動を広げることは、新しく出会う人々の根源的な感情を呼び覚ます小さなきっかけになるかもしれない」と、その可能性を口にした。
「どんな時代にも、美しさや歓びは存在しつづける」と信じる近藤は、前を向いて言った。「ものづくりってすごく難しいんですが、それでいて、とても楽しいんです」(文/阿部愛美)。![]()