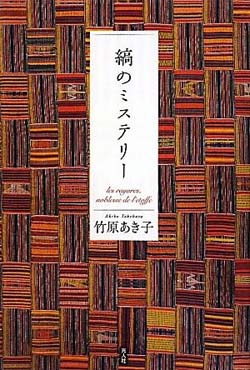REPORT | 建築
2024.06.24 15:07
アラブ首長国連邦(UAE)の首長国のひとつ、シャルジャで開催された、第2回シャルジャ建築トリエンナーレ(SAT)「無常の美:適応する建築」(2023年11月11日〜2024年3月10日)。キュレーターを務めたナイジェリア人建築家トシン・オシノウォは、グローバル・サウスの視点から気候変動に関する課題提起を行った。前編に引き続き、建築展のハイライトを紹介する。

エイドリアン・ぺぺによる、旧屠殺場を会場にした展示。
日常の都市空間を形づくるデザイン
SAPのメイン会場であるトロピカル・モダン建築の旧校舎アル・カシミヤ・スクールでは、19のプロジェクトが展開。そのひとつが、アンゴラ人クリエイターで、ロンドンとアンゴラの首都ルアンダを拠点に活動するサンドラ・ポールソンによる「偶然の贈り物としての砂塵」。ルアンダに常在する砂塵について考察し、廃棄された段ボールと澱粉を混ぜた単一素材を使って、ルアンダの人々にとっての生活必需品が並ぶマーケット空間を再現。

サンドラ・ポールソン「偶然の贈り物としての砂塵」。
インスタレーション空間には実際の砂埃は存在しないが、段ボールの混合物がそれに似た効果をつくり出し、視覚、嗅覚、触覚に訴えかける。砂塵は植民地時代の都市環境における階級分断を明示する存在である。セメントで舗装された場所はポルトガルの白人入植者によって支配され、アンゴラの原住民はほとんど砂埃で「舗装」されたインフォーマルな居住区に住んでいた。他方、砂塵は靴磨き、洗車といった経済活動をもたらす存在でもある。ポールソンは、偶発的な「贈り物」としての砂埃に興味を持ち、インスタレーションを通じて、一見不要に見えるものがどのように都市空間を形成するのかという問いを投げかける。

ニフェミ・マーカス=ベロ「アフリカ−デザイナーのユートピア:ラゴス編」。
ナイジェリア人デザイナー、ニフェミ・マーカス=ベロが手がけた展示は「アフリカ デザイナーのユートピア:ラゴス編」と題した調査プロジェクト。ラゴスの街角でよく見られる道具など、生活のなかでアレンジされて生まれた「匿名のデザイン」の記録である。例えば、再生木材と自転車のタイヤを再利用してつくられた水のコンテナを楽に運ぶためのメルワ・カート。モバイル販売什器のキワリは、渋滞にはまった人々にお菓子を売る人たちが使うもので、ガムやチョコレートなどがバンドで固定されて何層にも積み上げられている。アフリカの主要都市においては、「デザイン」と言わずとも多くのものがデザインされている。この調査には、日常的な問題の解決策、いわゆるインフラの代替としてデザインが機能していることを、正式に記録する目的がある。
生死を問うスピリチャルな建築と素材

ブブ・オギシ「óré ì sé agbòn(目に見える世界に広がった土地)」。
ナイジェリア人ファッションデザイナー、ブブ・オギシは、スピリチュアリティをテーマにした儀式的な作品”óré ì sé agbòn”(目に見える世界に広がった土地)を提示。明かりが最小限に抑えられた展示空間にはサイザルでできた妖怪のようなタペストリーやドームが設置された。床には廃棄プラスチックの破片が敷き詰められ、厳かな雰囲気の空間がつくられている。儀式のようなサウンドや、お香やシナモンの匂いは、鑑賞者に一層畏敬の念を抱かせる。この空間を歩くことによって、人間の身体も自然環境の一部だということを再確認させられる。気候変動に適応することは、アニミズム的な思想を取り入れる、あるいは取り戻すことなのかもしれない。オギシの世界観は日本の神道と通じる世界観であるとも言える。

ミリアム・ヒラウィ・アブラハムによる、ラリベラ教会の再現。
エチオピア出身のデザイナー、ミリアム・ヒラウィ・アブラハムは、ピンクのヒマラヤ塩のブロックを使って、エチオピア北部のラリベラ教会を再現した。岩を切り出して建てられ、絶え間ない腐敗と変化を続ける同教会を、シャルジャ地域で簡単に手に入る塩で再現することで、建造物の永続性と劣化の問題について問いかける。この展示においては塩の教会が劣化するまで存在することはないが、会期終了後は塩のブロックが解体され、小売店で販売される。建築展の有機的な展示のあり方を示した。

ユセフ・アグボ=オラ「生きた建築物」。
ロンドンとアマゾンの森林を拠点に活動する、ナイジェリア、アフリカン・アメリカン、チェロキーのバックグラウンドを持つアーティスト兼建築家のユセフ・アグボ=オラは、テキスタイルの社を制作した。ジュート、ヘンプ、コットンの糸を編んだ布で構成され、内部では香が焚かれている。気候変動が生物多様性に与える影響をテーマにした「生きた建築物」は、会期終了後にアマゾンに移され、そこで森と融合する。

エイドリアン・ぺぺによる、旧屠殺場を会場にした展示。
最近まで使われていて、まだ生々しく臭いが残る旧屠殺場の会場で展開されたのが、ホンジュラス出身でレバノン・ベイルートを拠点に活躍するファイバー・アーティストのエイドリアン・ぺぺによる、太い尻尾を持つアワシ羊の毛皮を使った大規模な展示。屠殺場内のレール状の設備に、縫い合わされた毛皮で覆われたチューブが張り巡らされている。来場者がチューブに触れると、まるで生きているような動物の温もりを感じることができるという仕掛け。かつては羊が屠殺されると、肉が食されるだけでなく毛皮や骨など全てのパーツが廃棄されることなく、日用品として活用されていた。しかし、昨今では産業化とグローバリゼーションの流れを受け、食用に屠殺された羊の毛皮は廃棄されているという。同会場では、ケニアの建築事務所ケーブ・ビュロー(Cave_bureau)が屠殺場ツアーをテーマにしたサウンドスケープとビジュアルコンテンツを展開した。来場者は屠殺される動物がかつて通った順路を進むという設計になっている。

エイドリアン・ぺぺによる、旧屠殺場を会場にした展示。
ケーブ・ビュローは展示のなかで、「無常の美」というSATのキーワードのひとつに触れ、「人生において確実なのは死だけであり、それ以外はすべて流動的である」と語っている。それは自然界ととともにわたしたちも変動し続けるべき、つまり気候変動に適応して歩んでいくべきだという警告であるとともに、それができるはずだという希望のメッセージのようにも思えた。![]()