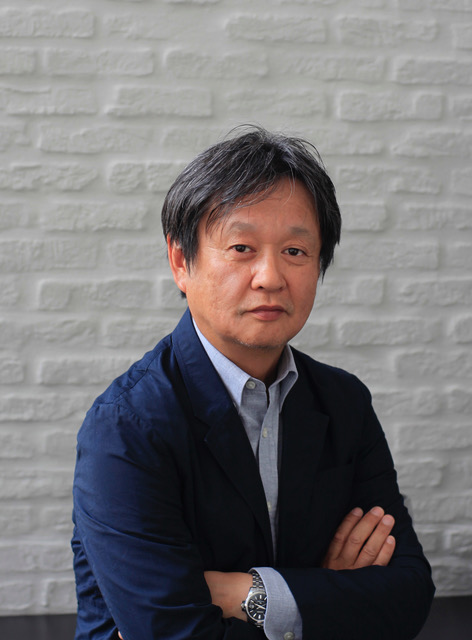東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。
コンテクストデザイナー 渡邉康太郎さん
「ともに編みあげる“ものがたり”」
コンテクストデザインとは、それに触れた一人ひとりからそれぞれの「ものがたり」が生まれるような「ものづくり」の取り組みや現象を指す。それはどのようなプロセスを経て成し遂げられるのか。コンテクストデザイナーの渡邉康太郎さんに聞いた。
対話で生まれる「点」の結び方
――コンテクストデザインはどのようなプロセスを経てつくりあげられるのでしょうか?
ケースによって変わります。最近では、110周年を迎えた学校法人北里研究所のリブランディングをTakramとしてお手伝いしましたが、このプロセスの一部にはコンテクストデザインの知見が活かされています。ロゴをつくり変えるとき、反映されるべきは、わたしたちのような外部のデザイナーの「こうしたい」という意志ではないと思っています。それよりも、実際に籍をおいている学生や教職員の方々が北里研究所にどのような思い入れがあるのかを聞いて活かしたい。多くのインタビューやアンケートを行いましたが、一人ひとりに北里との固有の物語があるんです。そして、そのなかから「全体を貫くひとつのストーリー」のようなものが浮かび上がってくる。それは彼らが直接言葉にしたものではないけれど、デザイナーが媒介的な役割を担い、ひとつのスローガンに纏め直します。つまり、つくり手が独自にインスピレーションを受けて着想するのではなく、対話の中から自ずと生まれてくるものを見出す。それがコンテクストデザインの根本にある考え方です。

「KITASATO BRANDING PROJECT」より
デザイナーとしては、ひとつの点と遠くにある別の点を自分の頭の中で結びつけていくという作業をします。何を結び付けて、どう物語にするかは、あらゆる人の話に耳を傾けるデザイナーの側が力を発揮できるところです。キーワードを与えられたとき、ただ単に目の前のことだけに着目するのではなく、それを相互に結びつける。また、デザイナー自身がこれまで体験したことや見聞きしたこと、つくってきたことなどを想起にしながら、それも結びつけられるかもしれない。このあたりにクリエイティブな着眼点が活かされます。相手の言ったことをそのまま取り入れる・取り入れないと判断するのではありません。複数の色をパレットで混ぜ合わせるように、新しい混ぜ合わせ方や視点を組み込む。そこにクリエイティビティの秘訣があると思っています。

「KITASATO BRANDING PROJECT」より
自分の考えがアップデートされるのを楽しむ
――コンテクストデザイン以外にも幅広くデザインを手掛けていらっしゃいますが、デザインを手がけるときに「変わらないこだわり」はありますか?
当初の個人の着想のまま形にするより、対話を通じてそれを複数人でつくり変えていきたい。「ともに編む」ことで形が変わるのを楽しみたいという想いがあります。コンテクストデザインを字義的に解釈すると「文脈を設計する」となりますが、僕がやろうとしているのはそうではない。例えば、クライアントの意向を「誤解がないよう正しく伝えていきましょう」と言うシーンがあるかもしれませんが、むしろ僕は誤解をしてほしい。そして、一人ひとりが異なる物語を紡いでいってほしい。つまり、人々が誤解し、思惑から外れることで形が変わっていく、「一緒に編み上げていく」ことを目指しているんです。
何かつくるときに、最初に思いついたものをそのままの形にすることを重んじるデザイナーもいるけれど、僕はむしろ変わっていくことを楽しみたい。人は一貫性を求めがちです。例えば、議論しているときに以前に言ったことと違うと、「矛盾しているじゃないか」と指摘する。でも、矛盾していいと思う。生きているうちに考えが変わるのは普通のことで、むしろ自分の考えがアップデートされ、物差しが変わっていくことを互いに楽しんだほうがいい。考えがアップデートされることで物事の解像度が高まったり、新たな視点を得たりできる。今まで見えなかった魅力が言語化できるようになります。
――大学時代に学んだことで、今にいちばん活きていることはなんでしょうか?
大学生のうちにできることの代表選手は語学だと思います。時間をたっぷり使って集中的に学習できるこの時期に、一度語学の下地をつくっておくといい。しばらく時間が空いて社会人になっても、自転車を漕ぐみたいに感覚を取り戻しやすいです。語学と異文化交流を通して、「無知の知」じゃないけれど、自分が知らないことを思い知る。他の人の感じ方を想像したり、追体験したりする。そして何よりも、今の自分の領域から出ることです。そうすることで、自分がどこにいたのか客観視できるから。ジル・ドゥルーズらの「脱領土化」のイメージです。
それに文化人類学や哲学など、デザインに直接の関係を見出しづらくても、すごく面白い分野がたくさんあります。大学時代は、そういうものに出会うことが本当に大事。大人になって多くの人が「学生のときにもっと真面目に勉強すればよかった」と言う。それは社会に出て「これが面白い」とか、自分の興味あることがわかってくるからです。いろんな見分に触れて、未来の自分のために、いつ芽を出すかわからない種を撒いておく。これは多分野の授業や、他者に触れやすい大学生のときにこそできることです。

楽しみながら新たなジャンルを切り拓く
――大学卒業後すぐに、Takramに参加されましたが、何がきっかけだったのでしょうか?
全くの偶然なんです。高校時代のバンド仲間が創業当初のTakramに参加していて、彼に誘ってもらいメンバーたちとランチをしたときに「一緒に働かない?」となったんです。創業数カ月だから、Takramのことはほとんど誰も知らなかった。
Takramはデザインとエンジニアリングを一緒にやりたいという人たちが始めた組織です。僕自身もその離れ離れのふたつの間を行ったり来たりしながら、両方の良いところを活かしていくという考え方に共感したんです。ぼくのバックグラウンドは必ずしも「デザインとエンジニアリング」ではないのですが、ふたつの異分野の間で振り子を振るという姿勢が素敵だな、と思いました。複数の価値観があって、そのなかで視点を固定させずに仕事をするのは面白いんだけど、緊張感もあります。Takramはそういう場だと感じています。
――コンテクストデザインのような新たなジャンルを自ら切り拓いていくことへの不安はありましたか?
感じているのは、不安ではないですね。どちらかというと「楽しいな」「これでないとできないな」というくらいの気持ちです。ただ、つくる対象がはっきりしているグラフィックデザイナーやプロダクトデザイナーのように自ら名乗れないので、「こういうデザインが得意です」という説明がしづらい。そこに対する不安はあります。日本の社会は職人性を重んじる傾向が強いので、「これが得意です」というものがあると、「プロジェクトを一緒にやらない?」と声がかかりやすい。けれど、抽象的なスキルや確立してないジャンルだと、他者に理解してもらうのが難しい。そういう難しさは常に感じています。でも、答えがない、新しいジャンルをつくることをしているので、未知との出会いを楽しみながらやってみるしかない。きっと共振してくれる人と出会えるはず。そう思っています。(取材・文・写真/東京都立大学 インダストリアルアート学域 大谷智史、加賀実奈、上林永宜、莫文萱、峰村明瑠、三田広樹)

渡邉康太郎/1985年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。コンテクストデザイナー、Takramディレクター。使い手が作り手に、消費者が表現者に変化することを促す「コンテクストデザイン」を掲げ活動。組織のミッション・ビジョン・パーパス策定からアートプロジェクトまで幅広いプロジェクトを牽引。関心事は人文学とビジネス、デザインの接続。主な仕事にISSEY MIYAKEの花と手紙のギフト「FLORIOGRAPHY」、一冊だけの本屋「森岡書店」、北里研究所や日本経済新聞社、J-WAVE のブランディングなど。J-WAVEのラジオ番組「TAKRAM RADIO」ナビゲーターも務める。著書『コンテクストデザイン』は青山ブックセンターにて総合売上1位を記録(2022年)。趣味は茶道、茶名は仙康宗達。大日本茶道学会正教授。Podcast「超相対性理論」パーソナリティ。国内外のデザイン賞の受賞多数。また独iF Design Award、日本空間デザイン賞などの審査員を歴任。慶應義塾大学SFC特別招聘教授。