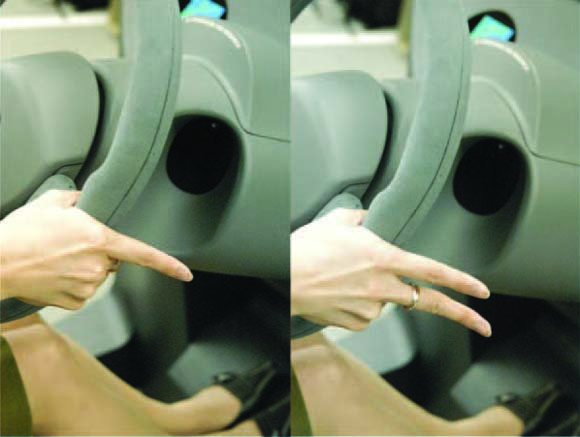東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。
ドミニク・チェンさんに聞く
「AI 技術との対話」
人間からテクノロジー、さらには糠床に住む微生物まで、多様な相手との“対話”をデザインしてきたドミニク・チェンさんに、昨今注目されているAI 技術と人との関わり方について聞いた。
AI 技術との新たな関わり方
――著書「未来をつくる言葉: わかりあえなさをつなぐために」のなかで、インターネットの普及によってクリエイティブ・コモンズが生まれたとおっしゃっています。AI 技術が進化することで新たなルールが生まれるのでしょうか?
みなさんはMidJourneyやStable Diffusion などのテキストからイメージを生成するAI を気にしていると思います。例えば、ある人がアニメーションスタジオに入社したとして、そのスタジオの画風でキャラクターを描けるようになるのに10年かかるとする。その10 年をAIがショートカットできることに対して、それまでやってきたスタジオの人たちがどう思うかという次元の話ですよね。「全然いいよ」って言う人もいるかもしれないけれど、自分の画風でなんでもつくられてしまうことで経済的なダメージを負っている人や名誉を傷つけられている人も現実にいます。知識や創造とはなにか、という問いが掘り返されていて、その意味では新しい可能性と問題に人類が直面していると思います。
今後、「この作品はAI に学習させてもいいですよ」という新たなライセンスが生まれるかもしれない。そのときにクリエイターひとりひとりがどう思うかは予測がつかないのですが、少なくともオリジナルをつくった人間に選択権が与えられるのはルールとして必要だろうと思います。

「Nukabot」
じんわりくるAI技術
――今後、AI技術と関わったら面白いと考えられる分野はどこでしょうか?
SNS 上でもフェイクニュースという問題があったりして、社会全体がダメージを被る危険性がある一方で、より良い世界をつくるために技術を使っていく可能性もある。今、僕はGPTを使って、雑談ができる糠床「Nukabot」というものをつくっているのですが、目的は糠床と一緒に暮らしている人が中の微生物たちの気配を日常的に感じられるようにすることです。発酵の分野に人格を留めておきながらも、意味がない雑談ができるロボットというものをつくりたい。ロボットに対する愛着も増すし、その中に住んでいる微生物たちにも意識が向くのではないかという仮説を立てているのです。そこで気をつけなければいけないのは、発酵はどうでもいいので喋る部分だけをつくってくださいと言われてしまうこと。それだと設計しなおさなくてはいけなくて、今までのデザインが失敗ということになる。それくらいAI というのは刺激が強いのです。
ファストフードって最初のひと口で旨みがガツンときますよね。それに対して、出汁の場合、その成分を自分で想像しますよね。「これ昆布かな、鰹かな」と自分の意識が能動的に動いて、ある意味食べ物とインタラクションしている。人間がクリエイティビティを発揮するのは後者だと思います。AI でつくられたコンテンツもフェイクニュースも地味なものはなくて、みんな派手でしょう? ファストフードと一緒で、考えなくても受け止められるようにつくられている。でも、一方的に押し付けるのではなくて、新しい使い方をしてもらったほうが、デザイナーや設計者にとっては学びになります。100パーセント思いどおりに機能することは実はあまり面白くない。年を重ねると見たことないものを見たい・人間の知らない可能性を知りたいという欲求が増えてきます。そういう地味でじんわりくるようなAI を今の技術でどうつくるか……。そういうことができたら、本当に面白いのではないでしょうか。

意味のないことをやるのが人間の特技
――学生時代に非営利組織・起業・研究と精力的に活動されてきましたが、学生の間にこそやっておいたほうが良いと思うことはありますか?
学生時代は「ちょっと気になったことをやってみる」ということに非常に向いている時期だと思います。年齢とともに「ちょっと気になったらやってみる」ためのコストが上がってくる。腰が重くなるという心理的な面や、物理的に体が動かなくなるという面においてね。だから、それほど強い興味が湧いていなくても「ちょっと何かありそうだな」と思ったら少しやってみる。そして、「やっぱりダメそうだな」と思ったらすぐにやめて次のことをやる。そんなことを100個くらいやる。そうすると、2つか3つくらいは芽が出てくるのではないかと思います。まあ、僕も100個はやっていなくて、実際は10個とか20個くらいかな。
研究室でのプロジェクトなど、実際に社会に出るものをつくる際は制約や制限がかかることもあるので、それとは別に学生でしかできないことを個人で自由にやることも非常に大事だと、 今、この話をしていて改めて思いました。社会に出るものをつくるときはどうしても意味や成果が求められてしまうので、社会と断絶したところで誰にも説明しなくていいこと、自分でも意味のわかっていないことをやる。そのようなものが自分の中で溜まっていき、それが全く関係のないプロジェクトにおいてアイデアへと繋がっていく。
逆に意味のないことをしていないと、みんなが同じ情報を見て、「今こういうものが流行っているからこうしよう」となってしまい、それでは人間が考えたりつくったりする意味がなくなってくる。AI は「意味のないこと」はできないので、無駄なことや意味不明なことをやるのが人間最大の特技だと思います。自分の中でどういうものが発酵しているのかをAI に教えてもらうという共生のあり方もあるのかもしれないですね。(取材・文・写真/東京都立大学 インダストリアルアート学域 王京京、黒木日南子、北野るな、Vitória Tomizawa、富田萌子、山下諸人)

ドミニク・チェン/1981 年生まれ。博士(学際情報学、東京大学)。
NTT InterCommunication Center [ICC] 研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)Design/MediaArts専攻を卒業後、NPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)を仲間と立ち上げ、自由なインターネット文化の醸成に努めてきた。近年では21_21 DESIGN SIGHT『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』(2020/2021)の展示ディレクター、グッドデザイン賞審査員(2016〜)を務めるほか、人と微生物が会話できる糠床発酵ロボット『Nukabot』(Ferment Media Research)の研究開発や、不特定多数の遺言の執筆プロセスを集めたインスタレーション『Last Words / TypeTrace』(遠藤拓己とのdividual inc. 名義)の制作など、国内外で展示を行いながら、テクノロジーと人間、そして自然存在の関係性を研究している。