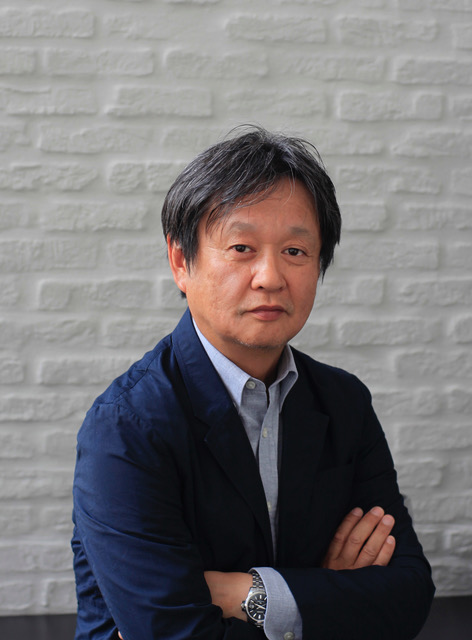東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。
柴田文江さんの“感覚”に触れる
日用雑貨や医療器具、ホテルのトータルディレクションなど、幅広いデザインを手がけてきたプロダクトデザイナーの柴田文江さん。日本の伝統文化とチェコの吹きガラスの技術を融合させたフロアライト「BONBORI」が、エル・デコインターナショナルデザインアワード2021の照明部門でグランプリを受賞など、その活躍の場はますます広がりつつある。柴田さんのデザインへの向き合い方などについて伺った。
感覚的に考えて論理的につくる
――BONBORIはどのような経緯でデザインしたのでしょうか?
生活用品をはじめ、さまざまなデザインをやってきましたが、あるときから世界を旅しながらものづくりを体験したいと思うようになったのがきっかけです。BONBORIにはチェコの伝統工芸のボヘミアガラスを使用しています。ボヘミアガラスを見たとき、とてもヨーロッパ的だと感じました。そこにアジア、あるいは日本という自分のルーツを掛け合わせて、もう少ししっとりした“うす味”を取り入れてみたら面白いんじゃないかと思ったんです。

▲BONBORI(BROKIS 2021)
――日本の民藝や伝統工芸とどのように向き合おうとしているのでしょうか?
以前、水晶の工房に行って感動したことを覚えています。表層的なデザインではない、本質的なものを感じました。伝統工芸はつくれる人でないとつくれなので羨ましい。ズカズカと踏み込んでいって、安易に手を出すわけにはいきません。敬意とデリカシーを持ちながら繊細に関わっていければと思います。
――デザインにおいて、対象をどのようにとらえて、造形表現に落とし込んでいくのでしょうか?
「感覚的に考えて論理的につくる」という言葉があります。美と実用性、論理と感覚など、私は相対するものごとを行ったり来たりするのがわりと自在にできるタイプです。例えば、カプセルホテルをデザインしたとき、湿度感をコントロールすることで快適さをつくろうと考えました。カプセルの中はしっとりさせたいけれど、自分と距離があるものはドライにすることでその場でのマナーを理解してもらうことを目指しました。形には湿度があると思っていて、それをコントロールすることでさまざまな表現が生まれます。

▲BONBORI(BROKIS 2021)
生きるように働く
――デザインとの出会いを教えてください。
実家が甲州織物をやっていて、子どもの頃からものをつくることが当たり前でした。工作が得意で、家の中でも学校でもものをつくる係みたいな感じでした。リカちゃん人形の服のようなおもちゃも自分でつくっていました。もちろん、そのころはデザインをしているつもりはなくて、手先が器用というくらいの感覚でしたけれど。
――企業に就職されましたが、なぜフリーランスという働き方を選んだのですか?
実家もフリーランスだったので、仕事は暮らしに密着している感じでした。もともと働きに出るというイメージも湧かなかった。でも、当時は女性のフリーランスが全然いませんでした。仕事もなく、どうなるか全然想像できなかった。最初は知り合いの手伝いや、朝顔の鉢のデザインのような小さな仕事をやっていましたが、それでは先がないと思って、まず自分のデザインを見てもらうためにコンペに応募しました。そこで賞を頂いたことで、地元の企業などから徐々に仕事の依頼がくるようになりました。
――普段の生活からどのようにしてアイデアは生まれていますか?
デザインは言葉よりも先にイメージが生まれて、後から言語化できるものだと思っています。だからBONBORIも最初から雪洞(ぼんぼり)というモチーフを思いついたわけではなくて、まず形のイメージがあって、最後に言葉で補うという流れで生まれました。私は、いろいろなことをやりたいという好奇心を大事にしていて、日々の暮らしから学んでていくことを意識しています。なので特別にあるデザインのためにだけインスピレーションをもらいに出かけるというわけではありません。
――では、仕事に対してどのように向き合っていますか?
生きるように働きたいと思っています。今は仕事が趣味のことのように感じています。30代の頃は忙しくて、生きるように働けてはいなかった。しかし、どこかで頑張る時期は必要だとも思っています。これからも長く自分の好きな仕事をしたいし、自己表現が仕事のような部分があるので、どこかのタイミングで自由に仕事ができたらなと考えていました。学生のときの自由は経済的に他者に依存して生きているので 本当の自由ではないと思っていて、本当の自由は、自分自身でなんでも自在にできることだと思います。

世の中にデザインという考え方を浸透させていく
――教員というデザインを伝える立場として、何を意識して教えていますか?
学生たちはデザインを学問だと思っているので、つい答えを欲しがってしまいますが、何かを教えるのではなく、何をしたらいいかを一緒に考えたい。学生が何かを探究している横で伴走していたい。サポートはするけれど、何が正解かを教えることが私の役目だとは考えていません。 プロダクトのデザインは自転車競技みたいなもので、そもそも自転車に乗る練習が必要です。そういった基礎を学んでようやくスタート地点に立てる。また、デザインをしたことがないノンデザイナーの方々に対しては、自分ごとのようにデザインを体験してもらえるような仕掛けが必要だと考えています。
――これからやってみたいことを教えてください。
やりたいことはいっぱいあります(笑)。旅は続けたいし、デザインミュージアムのようなデザイン普及のお手伝いや、さまざまなものづくりにも関わりたい。 街で変なものが目に付くことがあります。新しいものだけでなく、デザインと思ってやっているにもかかわらず変なものもあります。先日、マンションの自動ドアに「ドアに注意」という派手な色使いのシールが貼られていました。ガラスの自動ドアではなく木製の自動ドアなので、ドアに注意喚起をする理由がわかりません。自動ドアにはこのシールを貼ることがルールだからという説明でしたが、このようなおかしな事例に、何とかならないのかなぁと思いました(笑)。それに対して、私が直接何かをするわけではないのですが、デザインが浸透することで、間接的に世の中のデザインが良くなっていくのではないかと思っています。(取材・文・写真/東京都立大学 インダストリアルアート学域 歐陽、葉佳、越智勇斗、清田康貴、武政悠生、前川卓斗&電子情報システム工学域 不破万由香)

柴田文江/武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業後、大手家電メーカーを経てDesign Studio S設立。エレクトロニクス商品から日用雑貨、医療機器、ホテルのトータルディレクションなど、国内外のメーカーとのプロジェクトを進行中。iF金賞(ドイツ)、red dot design award、毎日デザイン賞、Gマーク金賞、アジアデザイン賞大賞・文化特別賞・金賞などの受賞歴がある。武蔵野美術大学教授、2018-2019年度グッドデザイン賞審査委員長を務める。著書『あるカタチの内側にある、もうひとつのカタチ』。http://www.design-ss.com