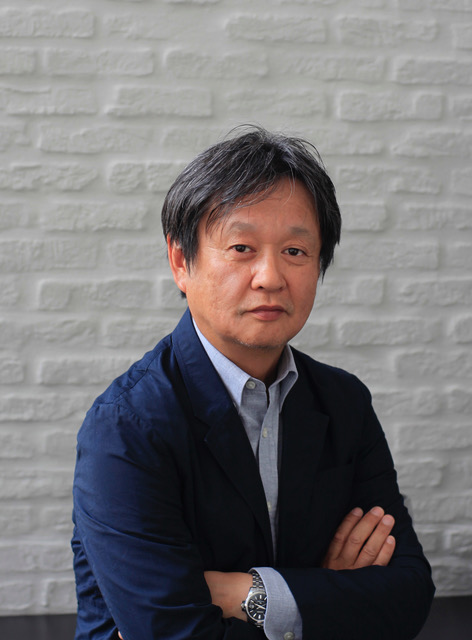東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。
デザイナー中村勇吾さん
「世の中にないものを、いい塩梅で出していく」
ウェブ・デザイナー、インターフェースデザイナー、映像ディレクター、そして大学教授、多岐にわたる活動を続ける中村勇吾さん。常に新しいアイデアを追求し、見る人を飽きさせないデザインで、注目を集めているデザイナーです。そんな中村さんのデザインに対する考え方や見方についてうかがいました。
他人の脳みそを使う
ーーデザインにおいて意識していることはありますか。
日常的な経験や視点を大切にするということもありますが、頭の中にはデザインの方法論の歴史があって、誰かが開拓した手法を基盤に、ボキャブラリーを足していこうという意識があります。その方法論のさまざまな表現の先端、誰もやっていないエッジをどう切り拓くかという意識で「こんなのあるんじゃない」と世界中のデザイナーとつくったものを見せ合っています。自分にはない表現ができる人は、一緒に仕事をしていて面白いですしね。
ーー意見や情報共有の場がインスピレーションの鍵になっているのでしょうか。
それはあります。どんな仕事でもなんとなく話しているうちに、言葉の端々から着想を得て「あ、これできるかも」と偶然出会うアイデアがある。ひとりで考えるより、打ち合わせの中で案がまとまることはあります。自分の脳みそだけでは限界があるので、他人の脳みそを使う。他人の脳みそを使ってものをつくることも、アイデアの出し方のひとつだと思います。
ーーマーケットに出す際のバランス感覚についてお聞きしてもいいですか。
僕としては、「7割わかる、3割わからない」くらいがちょうどいいと思っています。マーケットイン的な発想で10割わからせてしまうと面白くないんです。新しいもの・見たことないものに触れたいという気持ちが誰にでもあると僕は信じているので。すでにみんなに受け入れられているものだけで構成すると、つまらないじゃないですか。例えば、SNSの広告はマーケットに最適化されているけれど、全部文法が見えていてつまらなさを感じてしまいます。それよりは、自分たちだけは確実にわかっているけれど、世の中には共有されていないものをいい塩梅で出していく。その塩梅が難しいんですけどね。

▲NHK「デザインあ」より
ーーつくり手の「面白い」を起点にものをつくっていらっしゃる印象ですが、「デザインあ」についても同じ感覚なのでしょうか。
そうですね。「デザインあ」は子どもにデザインを教える番組なので、マーケットイン的な発想で言うと、子どもが好きな色や、子どもがわかる・興味を持ちそうな対象を出していこうとなるのですが、それはあえてやらない。こういうのはかっこいいだろ? こういうの面白いだろ?というものを見せる。もちろん子ども向けにわかりやすくしますが、最悪わからなくてもいい。
ーーこれからの時代のディスプレイの向こう側の世界の可能性について、感じていることを教えてください。
VRやARの世界のように視覚を全部乗っ取るような映像や、プロジェクションマッピングのように現実の中に介入するような感じで、映像のボーダーがなくなってきている。興味は尽きないですね。いろいろな領域に興味があるので、「可能性」といわれるとパッと答えるのは難しい。でも、さまざまなものの枠組みが広がってきていて、それは楽しいと思います。もっと爆発的に普及するものが出てくれないかなとも思っています。そうしたらやれることがいっぱい増えますから。
▲MOTION SIGNAGE FOR UNIQLO
経験がなくても、やってみる
ーー建築とウェブデザインの間に違いやつながりを感じる部分はありますか。
もともと土木構造物系の学科の出身で、そこにいながらも建築家になりたくて、建築の授業に潜り込んでいました。ウェブデザインについてもCPUでプログラムを持ち込んでブラウザ上で動くインタラクティブなものに興味を持っていました。その流れで普通のウェブサイトもつくっていた。建築はフィジカルなものであり、ウェブは仮想的なものという違いはありますが、どちらも構造やコードというルールが核になっていて、その現れとしてデザインが見える。ただ土木は50年、100年、もしかしたら永遠に残るけれど、ウェブは極端にいうと5分で消えたりする。時間軸が違うからこそ考えることも変わってきます。
ーー土木工学からウェブデザイン、広告、映像と仕事の幅が広がった理由を教えてください。
基本的には成り行きです(笑)。「できるんじゃないですか」と言っていたら、広がっていきました。例えばユニクロでウェブデザインをやっていたときに、映像をつくれないかと聞かれて、すぐに「できるんじゃないですか?」と答えた。実際はあまりできなかったのですが、「できないです」というより「できるんじゃないですか」と言うことで、仕事の幅が広がっていった。経験のない仕事でも初めてその文法を知って、取り組むときがいちばん新鮮なんです。経験上、そういうときこそいいものをつくれるイメージ。もちろん経験を活かすこともあるけれど、ゼロから考える機会も織り交ぜるのは大事だと思います。「経験ないけど、やる」みたいなね。
ーーさまざまな仕事をするなかで、異なる領域の仕事が互いに作用し合うことはあるのでしょうか。
それはあります。例えば、テレビCMをつくるにしても、映像ディレクターですごい人はいっぱいいる。そういった人たちがつくるCMとは違って、一種の違和感をつくらなければならないというときに、いわゆる「映像の文法」ではなくて、「ウェブの文法」をどう活用できるかを考えます。逆にウェブデザインやインタラクティブなことをするときに、「映像の文法」が活きることがある。領域をまたいで考えることで、新しいボキャブラリーが増えるんです。
▲METAFIVE – 環境と心理
まずは「つくる」ことが大事
ーー最後に、これからデザイナーを目指す総合大学出身の学生に何か一言あれば。
前提として、美大出身であろうが、総合大学出身であろうが、専門学校であろうが、中卒であろうが、学歴はあまり関係なくて、それぞれのパーソナリティが大きいと思います。仕事でも、この人がどこの大学の出身だなんて意識しない。あとでWikipediaで検索して「この人、ここの出身だったんだ」と知るくらい。専門性としてみたときに、デザイナーに期待されているのはいい設計をすることだと思います。だから具体的なアウトプットがいちばん大事。例えば、シェフに最も期待することは、新しい料理のビジョンを提案することではなくて、おいしい料理をつくることじゃないですか。まずは「つくる」ことがいちばん大事だと思います。(取材・文・写真/東京都立大学 インダストリアルアート学域 権藤直人、日向野由里、時田 葵、堀 真代、岡戸雄一郎、森 茉莉亜、伊藤勇輝)

中村勇吾/1970年奈良県生まれ。ウェブデザイナー、インターフェースデザイナー、映像ディレクター。東京大学大学院工学部卒業。多摩美術大学教授。1998年よりウェブデザイン、インターフェースデザインの分野に携わる。2004年にデザインスタジオ「tha ltd.」を設立。以後、数多くのウェブサイトや映像のアートディレクション、デザイン、プログラミングの分野で横断・縦断的に活動を続けている。
http://tha.jp