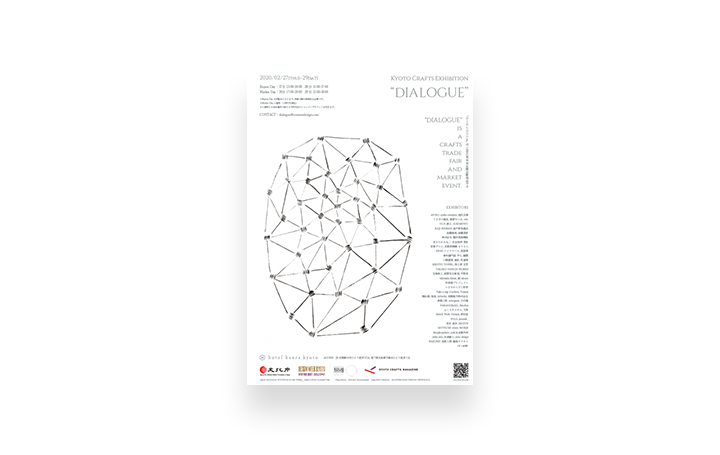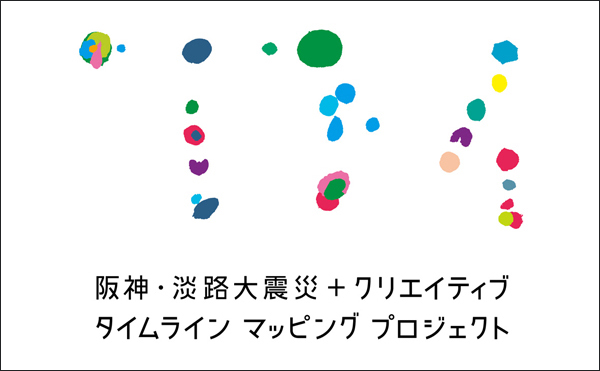REPORT | カルチャー / ソーシャル / 工芸
2021.03.26 16:29

▲岩手県洋野町で活動するfumotoのメンバー。左から、愛知から移住した後藤暢子さん、代表理事の大原圭太郎さん、東京都出身の原さゆりさん。現在ほかに5名の地域おこし協力隊員がいる。
青森県と接し、岩手県最北端に位置する洋野町(ひろのちょう)は、海山の風景が美しいのどかな町だ。太平洋側の種市町と山側の大野村が2006年に合併し、ひとつの自治体としてより多様性を持つようになった。
本州随一のウニの産地であり、アワビ、ホヤ、ワカメなどの海藻、サバ、サケ、タコなど海の幸も多彩。海岸に穏やかに打ち寄せる波は、所によってはサーフィンに適した力強い高波となり、東北有数のサーフポイントとしても知られている。
一方、山側の大野地区は高原に森林が続く、木工や炭焼きが盛んな土地で、木炭生産量は全国一。ほうれん草、しいたけ、山ぶどうといった農産物も豊富で、良質な乳製品や黒毛和牛の牛肉も生産されている。なにより大野では、工業デザイナー・秋岡芳夫氏(1920-1997)が提唱した「一人一芸の村」により始まった地元産の木材をロクロで削り出す“木の器”づくりが定着し、今も職人たちが手仕事で暮らしの器を日々製作している。
こんな海山の魅力にあふれた洋野町を、より広く、深く知ってもらうためのウェブサイト「ひろのの栞」が、この3月に公開された。
サイトを運営するのは、「fumoto」。地域おこし協力隊のメンバーを受け入れ、支援する組織として2019年に創立された一般社団法人だ。fumotoの使命は、洋野町役場とともに、この地の「関係人口」を増やしていくことでもある。関係人口とは、観光以上、定住未満というかたちで、その地域や人々と多様に関わる人々を指し、ここ数年地方創生において注目されている考え方である。

▲「本を読むように、洋野の暮らしと人をもっと知る」と題した、ひろのの栞。
地域おこし協力隊を支援する民間組織
fumoto代表理事の大原圭太郎さんは、地域おこし協力隊として2016年に洋野町に移住した。仙台出身で、東日本大震災後に仙台を盛り上げたいと洋服のブランドを立ち上げた経歴を持つ。首都圏でも活動したが、自分のやりたいことは地域から新しいものを生み出すことだと再認識し、奥さんの実家がある洋野の地域おこし協力隊に応募。3年間の任期中は観光をテーマに活動し、その後は、地域おこし協力隊の活動を民間で支援する組織としてfumotoを立ち上げた。
地域おこし協力隊とは、人口減少や少子高齢化が進む地域に移住し、地域ブランドの開発や、農林水産業などの地域協力活動を行い、定住・定着を図る取り組み。隊員の任期は1年から3年で、fumotoでは現在7名の隊員を、この4月からはさらに増えて計10名を受け入れる。民間組織で支援することのメリットを大原さんは、「それぞれの隊員がやりたいこと、テーマをもってこの地にやって来きます。市町村がほしい人材を求めるあり方とは隊員のモチベーションが違うと感じています」と説明する。それぞれの隊員は、サイクルツーリズム、木工、有休農地活用、空き家空き店舗活用、サーフツーリズム、海洋生物の研究、歴史民俗学研究などと、洋野町ならではのコンテンツをテーマにして活動する。

▲JR八戸線の線路の向こうは太平洋。洋野は東北有数のサーフポイントを擁している。

▲大野ではナラやアカマツの林をよく見かけた。ナラは日本一の生産量を誇る木炭の原材料に、アカマツは大野木工の主な素材となっている。
fumotoの活動をより充実させ発信力を強くしていくために、大原さんが頼りにしているのがmethod代表の山田遊さんだ。岩手県が開催し、山田さんが講師を務めた講座「北いわて産業デザインアカデミー」に大原さんも参加。「ひろのの栞」立ち上げにも協力を得た。
日本各地の地域プロジェクトに多数関わる山田さんは、「地域に新たな人を呼び込むには、やはり求心力のある人が重要です。大原くんみたいな“意志のあるよそ者”が、人と人とをつなげていくことが大切なんです」と大原さんへの期待を語る。
その大原さんの案内で、洋野の魅力を探るべく、この町ならではの土地、場所、人を訪ねた。

▲おおのキャンパスの天文台から牧場方面を望むと、目前に、地殻変動により大昔の海底が隆起してできたおよそ6段の海成段丘が広がる。

▲大野木工クラフトマン養成塾より。大野木工と聞いて、真っ先に思い浮かべるのがお椀。温かい汁物を入れても手で持つことができ、正しい姿勢で食事をとることができる。
秋岡芳夫氏の教えを今も体現する、木の器
最初に訪ねたのは、大野地区にある「おおのキャンパス」だ。緑豊かな高原には、秋岡芳夫氏が提言した「一人一芸の村」を実現した「大野木工」の工房をはじめ、陶芸や裂き織りの体験工房、それらを展示販売する大野産業デザインセンターが点在する。さらに、農産物直売所や温泉・宿泊施設、牧場や天文台などが緑に覆われた海成段丘に広がり、ジオパークとしても楽しめる複合施設となっている。
ここで話を聞いたのは、大野木工の草創期から秋岡芳夫氏に接してきた中家正一さんと中村隆さんだ。

▲大野産業デザインセンター所長も務めた中家正一さん。中家さんのインタビュー記事はこちらへ。
秋岡氏は、この地域の良質な木材に着目し、ロクロで削った木工食器の生産を提案し定着させた、“大野木工の恩人”的な存在。1970年代の大野村は、出稼ぎなしには生活が立ちゆかず、新たな産業を模索していたときだった。大野村役場に勤務し、後に大野産業デザインセンターの所長も務めた中家さんが当時を物語る。
「秋岡さんは、工芸という視点でものづくりをしながら生きていく、その方法をみんなで学びましょうと『工房生活のすすめ』という本を出されました。それを実践的に理解してもらおうと木工をはじめとした各分野の講師を連れて、1980年に4回にわたって、『大野村キャンパス80』と題した実習を開催したのです。大分からいらした時松辰夫先生のロクロの技術指導のもと、器づくりが始まりました」。
時松氏の指導を受けたのは、実演を見て自分もやってみたいと志願した大野村の7人。現在「工房 森の詩」を構える中村隆さんもそのうちのひとりだ。

▲中村隆さんは、秋岡氏とのいちばんの思い出を「NASAにも展示されている竹とんぼ」と語る。
木の器が1982年に大野村の中学校の学校給食の食器に採用されると、新聞やテレビなど数多くのメディアで取り上げられ、全国から注文が相次ぐようになった。その後、次世代の職人を養成し、職人がつくったものを1カ所で見られるようにと、1991年には「おおのキャンパス」に大野産業デザインセンターも設立された。
中村さんに秋岡氏の思い出を尋ねると、「秋岡先生の竹とんぼですね。ただの竹とんぼではありません。ご自身で竹を削り、形もバランスも飛距離も徹底的に追求された、並外れたものでした。その竹とんぼには、職人の基本である“ものづくりの精神”が集約されていると感じました」と言う。秋岡氏の「竹とんぼからの発想」は書籍にもなり、「手が考えるものづくり」として、今もデザイナーのバイブルのひとつになっている。

▲おおのキャンパスにて、中村さん(左)と中家さん。
中家さんや中村さんは、秋岡氏や時松氏から直接教えを受け、共に仕事をした、言わば「第一世代」。そのものづくりの精神は今どのように大野木工に継承されているのだろうか。「1998年に大野木工クラフトマン養成塾を開設し、技術的な継承は行ってきましたが、秋岡さん亡き後、そのものづくりの精神をどうやって継承していくかはこれからの課題です」と中家さんは語る。また、メソッドの山田さんは「今の時代にこそ、秋岡芳夫さんのコンセプトが社会に求められているのはないか」と期待を寄せる。
中家さんや中村さんらは、2010年から、大野木工の器を給食に用いている保育園に「出前講座」と題して出かけている。子どもたちにドングリの実を見せ、そのドングリが木に育ち、木から食器がつくられていることを知ってもらうという内容だ。実際にロクロで器を削り出すところを見せると、子どもたちは目を輝かせる。
「30年、40年かけて育った木でつくっているのだから大事に使ってねと説明すると、子どもたちも器を大切に思ってくれるようです。実際に使っている保育園の職員さんから、器の大きさや形などの要望を直接聞けることもありがたいことです」と中村さんは語る。
大野木工の木の器の材料は、すべて地元産の木材というのも素晴らしい。日本各地の伝統工芸や、その土地ならではの木工製品も、以前は地域の木を使っていたが今は外材や地元産ではない材料を使っていることが多い。ロクロで削られる木の香りは、この土地の自然に育まれてきたものなのだ。無垢の木を削ってつくった器の木目の美しさ、長い間使い続けた器の修理にも対応する工房の実直な姿勢にも感銘を受けた。


▲大野木工クラフトマン養成塾で製作に没頭していた佐賀工房の佐賀義之さん。丸いお皿は佐賀さんのオリジナル。研磨した後にプリポリマー樹脂を含浸して木目を生かしたり、漆塗装を施していく。
オリジナルの器も手がける職人たち
おおのキャンパス内の大野木工クラフトマン養成塾でロクロ作業に没頭していたのは、クラフトマン塾の第2期生だった佐賀義之さん。木工職人を目指すことを決意し、1999年に奥さんと生後6カ月の長女とともに埼玉県浦和市から移住。クラフト塾での3年間の研修を経て独立し、自らの「佐賀工房」を構えた。現在は後輩の研修生を指導する立場でもある。
「第二世代である私たちは、大野の産業の軸として木工の仕事に取り組んできました。今も40年前のデザインを継承していますが、ライフスタイルの変化に合わせた新しいものをもっと模索していいのかもしれません。一方で、大野木工の器は生活の道具なので、今後100年、200年と『民藝』のようなかたちで受け継がれていくようにも思います」と率直な思いを語った。
現在、佐賀さんが主に製作しているのは大野木工の給食用の器だが、浄法寺塗などの漆器の木地も製作し、その傍ら、自らがデザインした器づくりにも取り組んでいる。産業デザインセンターで展示販売されていた、佐賀さんオリジナルの器は、木目を活かしながら木地を薄手に仕上げた美しいもの。高度な技術が伺い知れ、大野の器の可能性を予感できるものだった。


▲木の器 サワクラフトの澤口真次さん。四角い皿やパスタ皿など、オリジナル商品の開発にも積極的だ。
おおのキャンパスから40分ほどクルマを走らせた種市で「木の器 サワクラフト」を営むのは、澤口真次さんだ。種市地区出身だが首都圏で就業し、6年前に帰郷して大野木工クラフトマン養成塾に入塾後、独立した。
「いずれは洋野町に戻って地元の産業に携わりたいと考えていました。37歳で帰郷した直後に、13年ぶりにクラフトマン養成塾の募集があり、もともと自然や木が好きだったこともあって、応募を決めました」と澤口さん。
現在は、毎日朝8時半から19時まで、工房で立って製作しているという。作業台の前には「無心」と書いた紙が貼ってある。大野木工からの仕事のほか、オリジナルの作品づくりにも取り組み、盛岡のデパートや都内のショップなどでも作品を販売。最近、予想以上に商品が売れて手応えを感じたと語る。
澤口さんのログハウスのような工房の窓からは、木々の緑が見え、薪ストーブのある空間はなんとも温もりのある印象だ。「大野産のアカマツやクルミ、サクラの木を使って、こんな場所で器をつくっているんですよというストーリー性も発信していきたい」。澤口さんの器には、まさに、その人柄とこの工房の雰囲気が反映されているようだ。
北三陸うみの学校を通じて、子どもたちに伝えたい
種市の中心部の海沿いに北三陸ファクトリーの本社と加工所はある。ウニ、アワビ、ワカメといった地域の食材を掘り起こし、魅力を伝える地域商社的な役割として2018年に創立された。その取締役を務めるのが地元出身の眞下(まっか)美紀子さんだ。
眞下さんは、高校卒業後、名古屋や東京などで学び、就職。飲食チェーンでの教育担当などの仕事を経験し、2016年に地元にUターン。飲食店向けの海産物卸業「ひろの屋」に入社し、2018年から100%出資子会社である北三陸ファクトリーに参画している。
「洋野町に戻って来て改めて感じたのは、地元産の食材のよさ、おいしさです。小さな北三陸の漁村から、国内を含む世界に発信していきたい。すでに台湾、アメリカ、香港、シンガポール、ベトナム、タイとは取り引きがありますし、ヨーロッパなどにも売り込んでいきたいですね」と、意欲満々だ。

▲北三陸ファクトリーの眞下美紀子さん。新たにオープンするショップ併設のファクトリーの前で。完成すると、町の人々とともに観光客が集う人気スポットになりそうだ。

▲北三陸ファクトリーの人気商品。「UNI&岩手産バターSPREAD」「UNI&北海道産帆立SPREAD」、奥の箱は「洋野うに牧場の四年うに/蒸し」の詰め合わせ。
北三陸ファクトリーでは、海産物の加工製造と販売、ウニ養殖、「北三陸うみの学校」という教育事業、これらを三本柱としている。なかでも眞下さんが力を入れているのが、北三陸うみの学校だ。
「商品をつくって売るだけでなく、その背景にあるストーリーを伝えることも重要です。そのために、地域の子どもたちや高校生に北三陸が魅力的な地域だということを知ってもらおうと始めた事業です。それが後継者の育成にもつながると思うんです」。
眞下さんはfumotoの理事も務めている。「16年に洋野町に戻って来た当時、町で活動している同世代はあまりいなかったのですが、ちょうどその頃に移住した大原さんと知り合い、お手伝いすることになりました」と言う。
今春には、商店街の活性化をテーマに、地元産のタラ、ジャガイモ、ほうれん草を使った「洋野コロッケ」を地域で活動する同世代のメンバーとつくり、fumotoの事務所前で販売する。若者たちが頑張っている姿を地元の人たちに見てもらいたいという。
「この土地にあるものを大事にしながら、人をつないで新しいことを生み出すのがfumotoの役割だと思っています。北三陸うみの学校からも洋野の魅力発信が始まっていくはずですが、それとfumotoの目的は同じだと思っています」。眞下さんの熱意と地元愛は、多くの人を巻き込み、着実に大きな波になっていきそうだ。


▲洋野町役場の長根洋一さん。長根さんの目線の先に広がるのは、洋野の海とバスケットコート。町役場から見える豊かな日常の景色だ。
ウェブサイトでさまざまな人とつながっていく
洋野町のさまざまな魅力、それを育んできた人、広くアピールする人などをfumoto代表の大原さんに案内してもらいながら巡ってきたが、これらの情報は、この3月に立ち上がったウェブサイト「ひろのの栞」に盛り込まれ、これからその内容はどんどんと厚くなっていく。
大原さんとともにこのウェブサイト開設を進めてきた洋野町役場企画政策係主任の長根洋一さんに「ひろのの栞」の役割について聞いた。
「毎年100人から200人が進学や就職で洋野町から転出します。そういった人たちとどう継続してつながっていくかが町の課題。また、仕事や観光などでこの地に関心を持ってくれた人にも、『ひろのの栞』に登録してもらえば、祭りやイベント案内を発信できますし、移住やUターンを考えている人には、仕事や住まいの情報などを伝えることもできます」と、期待を膨らませる。

▲fumotoの大原圭太郎さん。オフィスは現在自分たちの手で改装中。「自分が町に対して、こうなってほしいと言うのはおこがましい。自然と人が集まって変わっていったらいい」と語る。
大原さんは、「『ひろのの栞』のデザインをしているのはfumotoメンバーの原さゆりさん。取材・執筆も地元で行っていて、この取材を通じて自分たちも学んでいる最中です」と発信以上の収穫があるようだ。
町役場の長根さんも、「地域おこし協力隊の若い人たちが10人も町にやってくるというのは、かなりのインパクトがあります。町役場に勤める人はほぼ地元出身なので、fumotoは役場にはない民間の感覚で新たな気づきを与えてくれる存在として頼りにしています」と期待を寄せる。
「行政がすべてを背負うのではなく、民間の力でつながっていくことが大事。地域のプレイヤーが育てば、町も自ずと伸びていく」というのはメソッドの山田さんの言葉だ。
観光以上移住未満という人々との関係で、今後数年間、洋野がどう変わっていくのか。遠い都会から注目しつつ、時々この地を訪ねてみたいと思う。(文/鈴木伸子 写真/五十嵐絢哉)![]()

▲夕暮れの洋野。東京からのアクセスは、新幹線で八戸まで約3時間、八戸から種市までJR八戸線で約1時間。空路は、JAL三沢空港からクルマで約1時間10分。