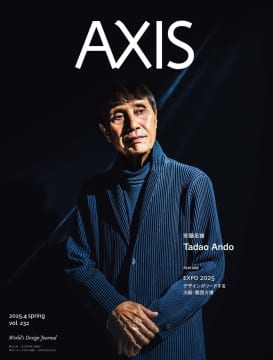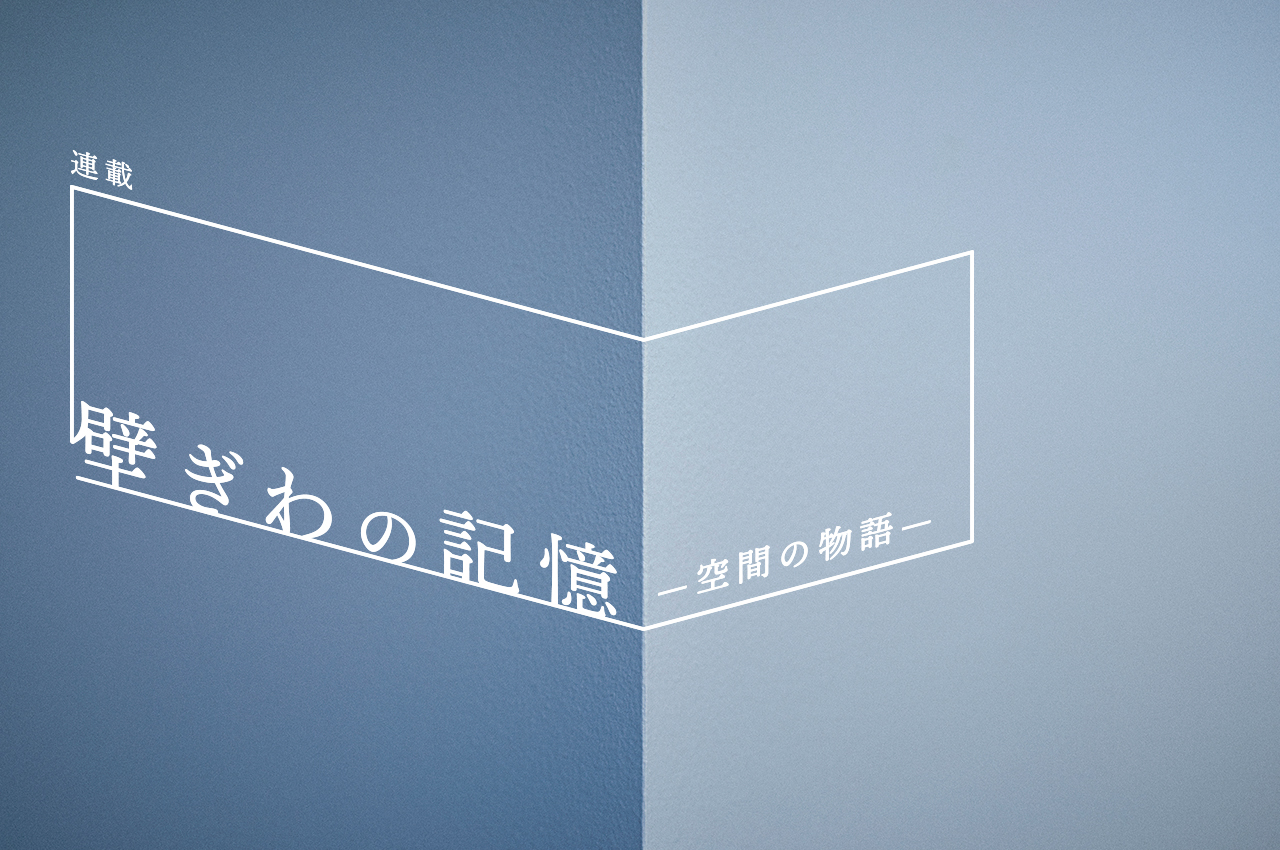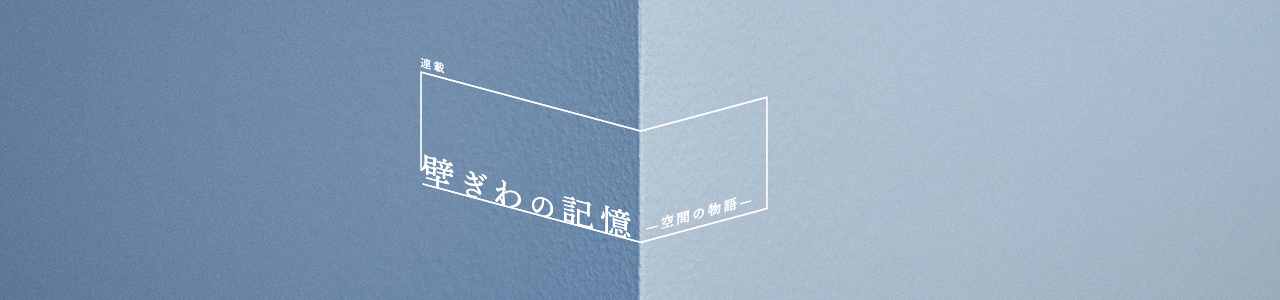詩人・大崎清夏が建築家の手がけた空間をその案内で訪ね、建築家との対話を通して空間に込められた想いを聞き取り、一篇の詩とエッセイを紡ぐシリーズ。
第10回は葛島隆之さんとともに住宅「A house」(三重)を訪ねます。大崎さんの心に浮かぶ、この空間に投影された記憶とは?
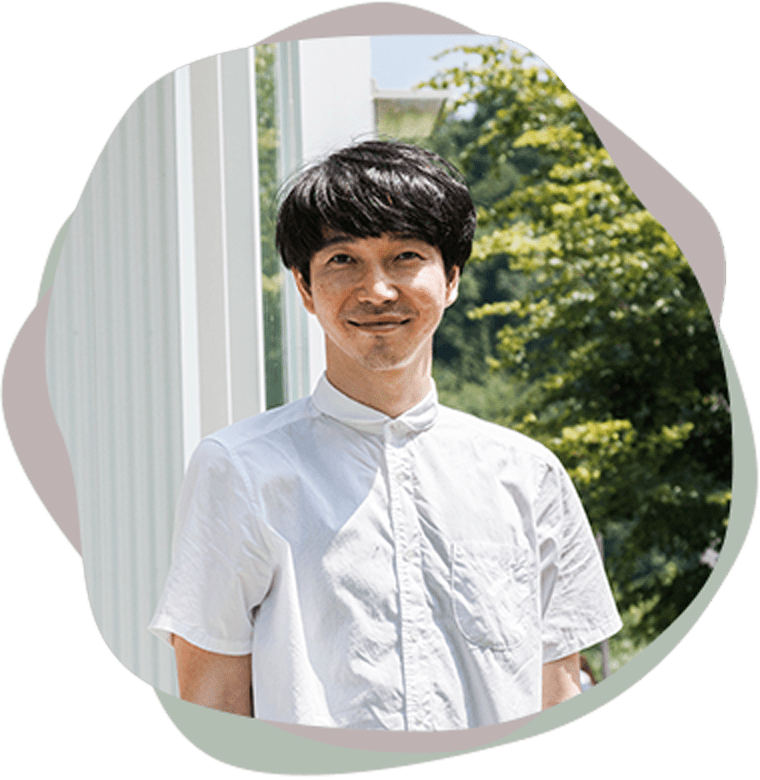
葛島隆之(くずしま・たかゆき)
1986年三重県生まれ。2010年名古屋工業大学大学院修了(若山滋研究室)。10-16年studio velocity勤務。17年葛島隆之建築設計事務所設立。18年より大同大学、名古屋造形大学にて非常勤講師。主な受賞歴に、神戸市役所市民ロビー改装設計プロポーザル入選(16年)、星野珈琲店設計コンペ1次審査通過(19年)、SUGIMOTO建築デザインコンペティション銀賞(20年)、くまもとアートポリスプロジェクト立田山憩いの森・お祭り広場公衆トイレ公開設計競技2020佳作(20年)。大阪駅前・うめきたシップホールにて10月16日より開催される「Under 35 Architects exhibition 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会2020」に出展予定。主な作品に、「Hut」(18年)、「A house」(20年)。http://kztkoffice.site/
Twitter https://twitter.com/t_kuzushima
Instagram https://www.instagram.com/t.kuzushima_associates/
丘の上のぽっかりと広い空間に、榎の林がのびのびと葉を茂らせていました。たわやかな幹と枝の高みからは、鳥の声が降っています。この樹々を繫いでツリーハウスをつくったらすてきだろうな……。ふとそんな夢を膨らませそうになりました。白い円形の散歩道が樹々のぐるりを囲んで、緑陰はクマのプーやコブタやクリストファー・ロビンが飛びだしてきそうな優しい雰囲気に包まれています。かわりに飛びだしてきたのは、この小さな林の傍らに建つ家に住む、小さな女の子でした。
丘を区切る幾つかの見えない線について、女の子はたぶんまだ知りません。林と家の間に引かれているのは、市区町村の境界線です。家を建てることができる東側の区画と、建てるべからずの西側の区画。建築家の葛島隆之さんは、行政区域の境界線にいくつかの補助線を引いて、家のための二等辺三角形と、林の庭のための五角形とに切り分けました。以前は立ち入れないほど混雑していた樹々を間引くと、三岐鉄道の黄色い電車が木立の間から見えるようになりました。

なだらかな丘の傾斜に寝そべるように、家は建っています。屋根までまるごと地面と平行の傾斜をもった平屋建てのその家の佇まいは、どこか、蓮の葉っぱに落ちた水滴のような自然さを湛えています。
葛島さんがふと、雨の話をしてくれました。「敷地」や「土地」や「区画」と呼ばれるずっと前、ただの丘の斜面に降り、染みこんで流れていった雨。その雨の身振りに教わるように、葛島さんはこの家の雨樋を砂利の下に埋めました。だからいまも雨は、屋根の斜面を滑り、砂利に落ちて染みこみ、地中を通って流れてゆきます。「雨目線からすると、あまり変わっていないかもしれません」と、葛島さんは朗らかに言いました。

丘に傾斜があるように、家のなかにもゆるやかな傾斜があります。二等辺三角形の内部を蛇行する廊下の勾配を上るともなく上っていくと、角を曲がるたびに大小の中庭が視界の左右に現れます。
林側と道路側にそれぞれ2つ。その中庭の出入り口の役割も果たす大きな窓からは、榎林の梢や空や、道向こうの墓地や家並みが見渡せます。大げさかもしれないけれど、西に東にさまざまな景色が登場するこの光射す廊下を歩きながら、私はちょっと登山者の気持ちでした。それはまた、横倒しになった大樹の道管を光に導かれて進む水のような気持ちでもありました。道管の先には気持ちのいいリビングダイニングがひらけて、女の子とお母さんが昼食の準備をしています。気持ちのいい長梅雨の晴れ間です。
扇垂木という手法を応用して天井に緻密に渡された梁が、廊下からリビング、さらに奥の子ども部屋や寝室までを、ひと続きの大きな流れに見せています。外へ外へ視線を誘われ、登山者や水分の気持ちにさせられる理由は、勾配だけでなく、どうやらこの扇状の梁にもありそうでした。


がぶりがぶりと丘の景色を見せてくれるいくつもの大きな窓に、訪問者の私は快い開放感を感じてばかりでしたが、葛島さんに「どう開くかを考えることは、どう閉じるかを考えることです」と言われてやっと、安全やプライバシーを守る家の機能について思いだしました。とても重要な機能です。
林や道路から中庭をしっかりと仕切れること、自生の樹々やシェードで外からの視線や日射しを避けられること。開閉のバランスは日常生活のたのしさ心地よさに直結しています。開放感と安心感は、同じひとつの自由の表裏です。

不可抗力の要因がリモートワークを大きく前進させ、家で過ごす時間が増えた多くの人にとって、住みかの開閉の技術やアイデアの必要は、ほとんど呼吸の必要に近い重要性を帯びてきている気がします。住む場所の自由度は高まっても、土地と人との相性によっては、暮らしの不自由が勝ってしまう可能性もあります。
百年単位の時間を丘の上で生きる榎でも、その一本を掘り起こして馴染みのない場所へ移植されれば他の樹々と助け合えなくなり、寿命はうんと短くなります。丘をめぐる風や鳥や虫、水の流れ、木の根が支える土、その生態系の確かな合理はあまりにも大きな時間のなかにあって、人間の目にはなかなか見えません。そういう大きな自然の尺度を信頼して家を設計することは、激しい災害を人間がやり過ごしていくためにも、もっともっと研究されていくべきなのかもしれません。

誰かが田舎で暮らそうと決めたとき、その土地とその人にとって自由度の高い、たのしい家をつくること。葛島さんは自分の仕事を、そんなふうに表現しました。そういう家が、ゆっくりゆっくり地面に根を張る樹のようにあちらこちらの土地に根づいたとき、それはたのしい地域のヒントにも、たのしい環境の希望にもなることができるかもしれない。榎林と家の間に立つ葛島さんを見ていると、私には建築家という人が、大きな大きな庭の庭師のようにも思われてくるのでした。
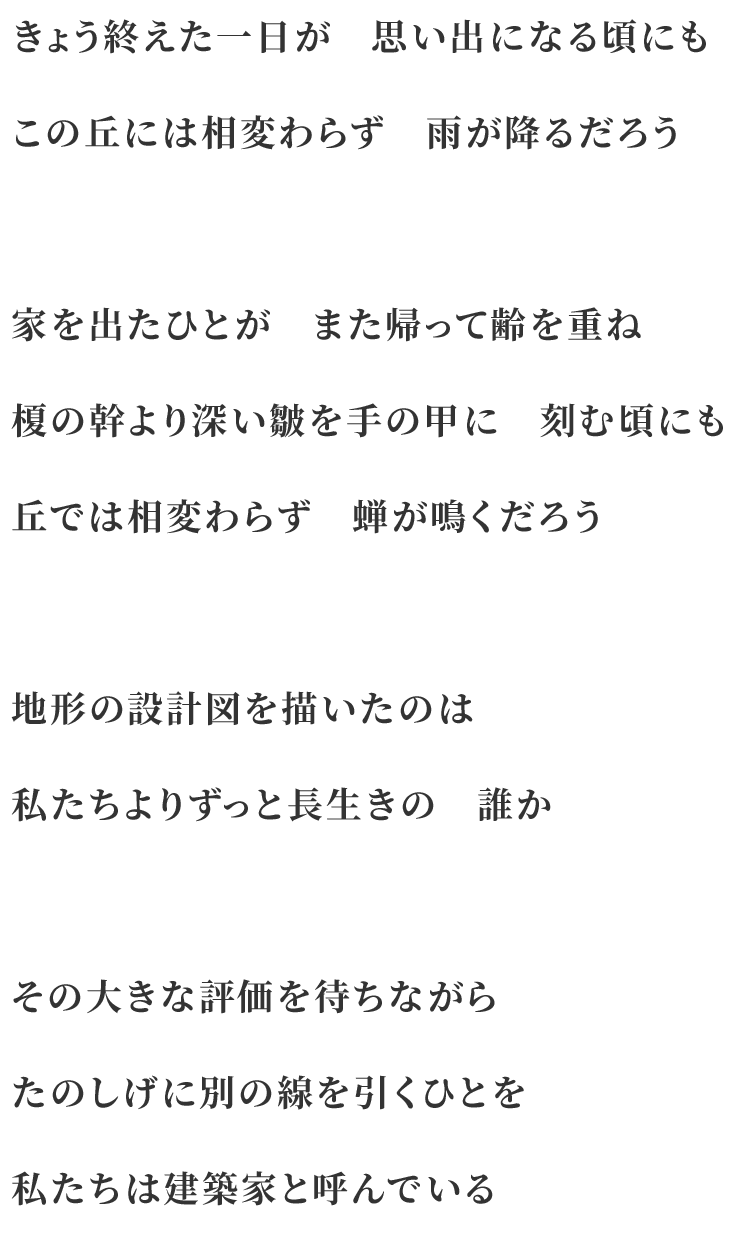
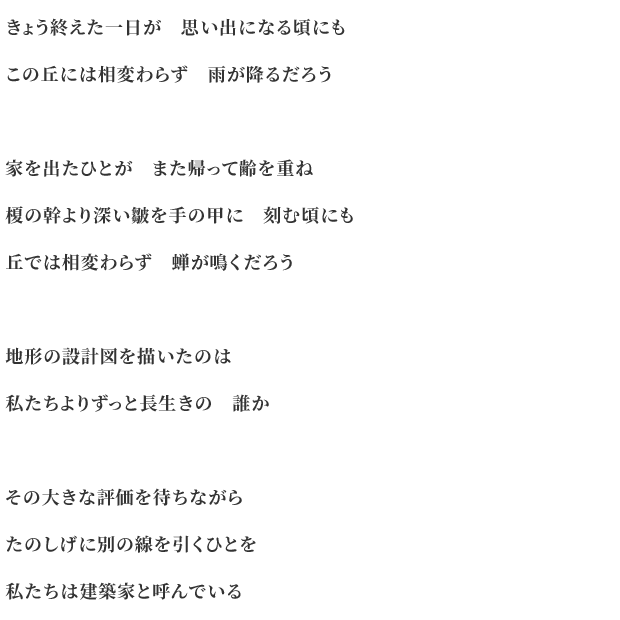


大崎清夏(おおさき・さやか)
1982年神奈川県生まれ。詩人。詩集「指差すことができない」が第19回中原中也賞受賞。近著に詩集「新しい住みか」(青土社)、絵本「うみの いいもの たからもの」(山口マオ・絵/福音館書店)など。ダンサーや音楽家、美術家やバーのママなど、他ジャンルのアーティストとの協働作品を多く手がける。19年、第50回ロッテルダム国際詩祭に招聘。https://osakisayaka.com/