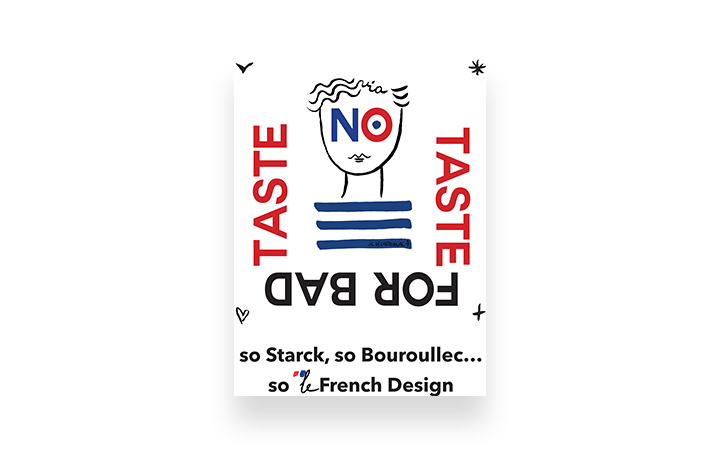NEWS | サイエンス / フード・食
2020.02.20 15:47

▲Photo by Jacek Dylag on Unsplash
京都大学経済学研究科の久野愛講師は、1870年代から1970年代の米国に焦点を当て、人々が「自然」だと思う食品の色が、いかに歴史的に構築されてきたのか明らかにした。
「目で食べる」という言葉があるように、私たちがある食べ物を「美味しそう」「新鮮そう」と感じる際、視覚は大きな役割を果たしている。たとえば「赤いトマト」や「黄色いバナナ」といったものは、いかにも美味しそうに感じるだろう。ただ、野菜や果物を含めて多くの食品は、その見た目、特に色は人工的に創り出されたものでもあるという。

▲図:バターの着色料の広告、1916年(「バターを売るには味と色が重要」という見出しをつけて色の重要性を強調)
そこでこの研究では、アメリカにおける産業誌や市場調査報告書、企業内の書簡、広告などを用いて、企業内・企業間で行われた議論を分析。
食品企業の生産・マーケティング戦略や政府の食品規制、「自然な」色の再現を可能とする技術的発展、消費者の文化的価値観(特に自然観)の変化に注目し、「自然」と「人工」という概念の境界が流動的であること、さらに味覚や視覚といった五感の歴史性や社会性について考察している。
なお、この研究は2019年にハーバード大学より書籍「Visualizing Taste: How Business Change the Look of What You Eat」として出版されている。久野氏は、「食べ物の色など、普段当たり前、自然だと思っていることが、どのように・誰によって作り出されてきたの
かを知ることは現代社会をより深く理解する一途になると考えています。」と語っている。![]()