REPORT | プロダクト / 展覧会
2019.09.02 13:59

▲点在する展示会場をつなぐ小川沿いの小道が「Social Seating」の展示場所。写真中央は中坊壮介さんがデザインしたベンチ。
フィンランド南西部の小さな村、フィスカースで「FISKARS VILLAGE ART & DESIGN BIENNALE」(以下、フィスカースビエンナーレ)が初開催されている。3つの展示で構成され、そのうちのひとつ「Social Seating」はデザイナーのジャスパー・モリソンがキュレーションしている。本展に参加する3人の日本人デザイナーに、日本ではあまり知られていないフィスカースビエンナーレについて、また自らの作品について尋ねた。

▲かつての銅器製造工場で開かれた「Factory Exhitbition」。手前はこの地で木工家具をつくるデザイナー兼家具職人のMinja Kolehmainenによるスツール。
閉鎖した工場跡をアーティスト、デザイナー、職人に開放
ビンナーレが開かれているのは、ヘルシンキから1時間ほど電車に乗り、タクシーやバスを乗り継いで到着する小さな村。フィスカースとは村の名前でもあるが、1649年にこの地で創業したフィンランドで最も古い企業名でもある。同社は刃物などの金属加工で知られ、オレンジ色の持ち手をしたハサミが有名だ。現在はイッタラやウェッジウッド、ロイヤルコペンハーゲンを傘下にもつ一大グループに成長している。
同社はこの地で80年代に閉鎖した工場をアーティストやデザイナー、職人らに住まいや工房として開放し、現在は入居希望者のウェイティングリストができるほど人気を集めているという。
今年5月19日に始まり、9月15日まで開催されているフィスカースビエンナーレは、コンテンポラリーアートを取り上げる「Beings with」、デザインにフォーカスした「Social Seating」、新旧のものづくりの製法や技法からデザインの成り立ちを考える「Factory Exhibition」という3つの展示から構成されている。

▲「クラフトマンシップの桃源郷にふさわしい、平和な雰囲気を表現したかった」と語る熊野亘さんのベンチ。地元企業のニカリと製作した。
自らのクリエイティビティを表現する場
「Social Seating」展のキュレーターは、ジャスパー・モリソン。彼が選んだ18人のデザイナーたちが今回のためにデザインしたがベンチが、村の中央を流れる川沿いに並んでいる。マルティノ・ガンパー、ハッリ・コスキネン、セシリエ・マンツらに加えて、日本からは熊野亘、中坊壮介、武内経至が参加した。
「フィンランド留学中から夏にフィスカースで開かれるアート展は見ていました。今年からヘルシンキデザインウィークの主催者Kari Korkman氏を迎え、アート&デザインビエンナーレと冠して、アート、デザイン、クラフトといった各分野の世界的なデザイナーやキュレーターを立てています。それにより、国際的な視野でフィスカースという場所を捉え直した展示になったと感じました」と語るのは、アアルト大学出身の熊野亘さん。
「フィスカースは、決して行きやすくもなければ、有名な美術館があるわけでもないけれど、金物をつくっていた時代から脈々と受け継がれる純粋なクラフトマンシップの桃源郷のような雰囲気があります。ビエンナーレの参加者はそれらを汲み取り、コマーシャルとは無縁の自らのクリエイティビティを素直に表現したくなる、そんな場だと思います」と続ける。
モリソンからのブリーフィングは、「アートやクラフトの展示会場をつなぐ川沿いの道に、ふたり掛け以上のベンチをデザインする」という、とてもシンプルなものだったと明かした。
「パブリックスペースのベンチをデザインするにあたって考えなくていけないことは、持ち去られないための固定の仕方、設置する場所、そこから見える景色への考慮です。でも、それらは大都市的な考え方であって、フィスカースで同じコンテキストが必要なのかと……。そこで逆に簡単に持ち運べて、フィスカースを自由に楽しむことのできるベンチをデザインすることにしました。リファレンスとなったのは、東京の地下鉄構内でポスターや広告を張り替える人が使う木製のステップ。片手で持ち上げられ、簡単にセットできる構造をベンチに応用しました。都会の景色をつくっている道具をフィスカースの景観を楽しむものにトランスフォームしたわけです」と熊野さん。

▲熊野さんがベンチのインスピレーションにしたのは、地下鉄構内で広告の張り替えに使われていた小さなステップ。
美術館とは違う、風景に溶け込むベンチ
もうひとりの参加デザイナー、中坊壮介さんは、「各所にベンチが設置されていく様子を見ていたのですが、それぞれ置かれるや否や、展示作品とは思わず、座る人々を多く見かけ、Social Seatingというコンセプトを実感しました」と語る。

▲「椅子の何倍にもなる垂直荷重を、いかに無理無駄のない構造で支えるか」を追求したという中坊壮介さんのベンチ「Grate」。スチールはKorpijärvi Johanssonというインテリア設計会社、木部はLuksiaという木工学校の学生が製作した。
オープニングではモリソンとデザイナーらがベンチをひとつずつ回り、自らのベンチについて説明するツアーを実施したそうだ。
「批評とは無縁の穏やかな雰囲気で、散歩しながら、ベンチに座りながら話をする、という感じのツアーでした。私の作品には、すでにラップトップで仕事をする男性が腰かけていたので感想を尋ね、そのまま彼を囲んで説明を続けるという、普段とは違う環境が興味深かったですね」と中坊さん。7月末には再びフィスカースを訪れ、それぞれのベンチの変化を見てきたという。「日焼けをしたり、錆びたり、木からアクが出たていたり、曲がりが生じていたり。これら通常の製品では受け入れられない変化が美しく、日々の風景にベンチが溶け込む姿を見ることができました。ジャスパーはそういったことも見据えていたのだと思います」。
ものづくりの文化をシェアする場
武内経至さんは、「作家が一人ひとり自分のベンチの前に立ち、商業的な価値など関係なく、ピュアにデザインを語り合う、幸せな時間を過ごしました。普段1,000人もいない小さな村に残るクラフトマンシップを守りたいという思いが、主催者からも伝わってきました。コマーシャル効果を狙って発足したのではないことは明らかで、純粋にものづくりの幸福感やその文化をシェアするという意味で、これ以上ないビエンナーレなのではないでしょうか」と振り返る。

▲「その場に昔からあったような自然な佇まいのベンチ」を目指した武内経至さんの「Kip」。イギリス英語で昼寝する、または昼寝する場という意味をもつ。武内さんはミラノ在住だが、ストックホルム・ファニチャーフェアで出会ったフレデリシアに製作を打診。商品化が決定しているという。
「ジャスパーから連絡をもらったのは今年1月。まずはフィスカースに足を運び、その場での“ソーシャル”を感じたいと思ったのですが、現地気温はマイナス30度で、真っ白。訪れても意味がないと、ネットで写真を見ながらイメージを膨らませました。自然に包まれたフィスカースという場と人をつなぐ、人と人をつなぐ、モノと人との関係を生む、という3つのソーシャル、3つの関係性が自分にとってのSocial Seatingに対するアプローチだと思い、その場にあっても不自然でない素材、できれば地元の木材を使おうと考えました。家族でピクニックをしたり、ひとりで昼寝をしたり、自由に使ってもらえるベンチ。背もたれをつけないことでモノとしての存在感を抑え、360度その場を体感できるベンチを想像して、自然とこの形に導かれました」と武内さん。
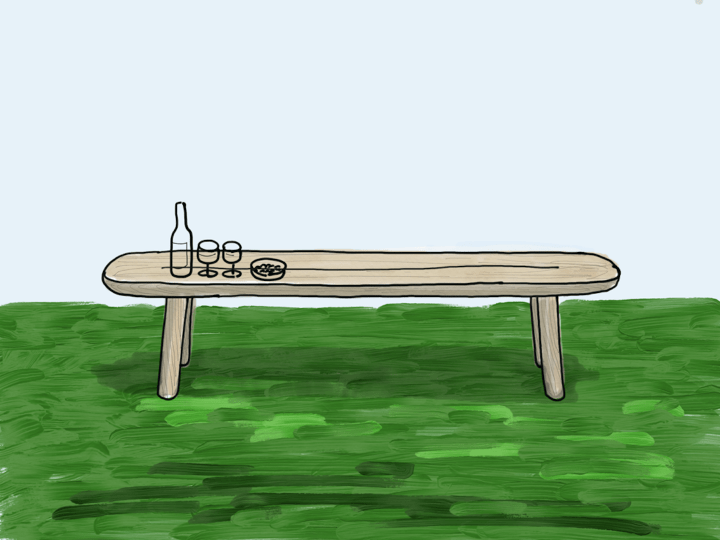
▲武内さんが最初のプレゼンで用いたスケッチ。
コンテンポラリーアートとクラフトにもフォーカス
残り2つの展示についても紹介したい。
イェンニ・ヌルメンニエミがキュレートする現代アートの展示「Beings with」は、共生がテーマ。アーティストたちの作品を通じて、人間の永遠のテーマとも言える、共存や相互依存という問いを投げかけた。

▲穀物貯蔵庫だった場所で行われた「Beings with」。右手奥に見えるのはニューヨークをベースにする笹本晃の作品。
キュレーターにアンニーナ・コイヴを迎えた「Factory Exhitbition」は、コンテンポラリーデザインと、その背景にあるものづくりのプロセスにフォーカスしたもの。スイスのローザンヌ芸術大学ECALで教える彼女は、ヴィトラのリサーチ部門でディレクターをしていた経験をもち、ロナン&エルワン・ブルレックの本なども執筆している。伝統的な製法と現代的な製法を比べながら、デザインへの考え方の違いを紐解いていった。

▲「Factory Exhitbition」より、手前はスイス人デザイナー、カルロ・クロパスのキッチンツールやカトラリー。木を削る、ステンレスを型抜きする、樹脂のインジェクションなど、素材による製法の違いを考察。右奥はTajimi Custom Tilesと韓国人デザイナーのイ・カンホのコラボレーション作品。ユニットを重ねることでベンチや建材になるループ状の構造は、焼成により強度を増す土の特徴を表現している。
ゆったりとした時間が流れるフィスカース村で、デザインとアートを心ゆくまで楽しむ時間はとても豊か。2年後のビエンナーレでは、誰のキュレーションでどんな展示が行われるのだろうか?![]()













