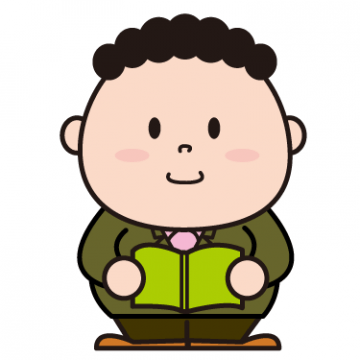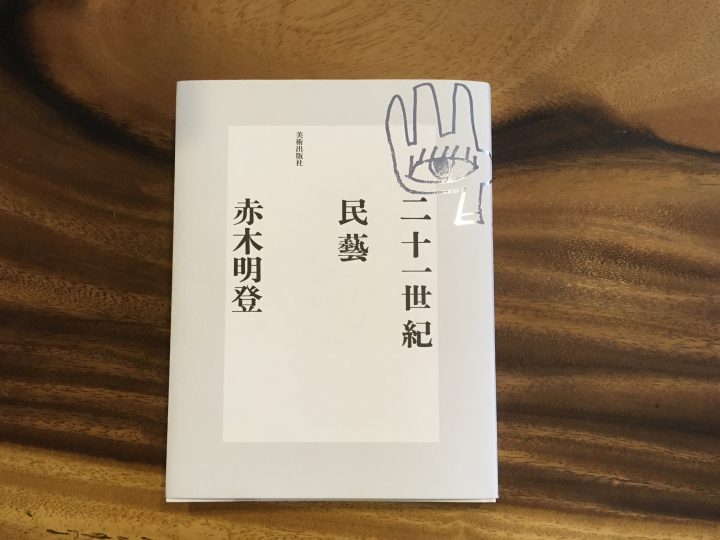その聖なる場所は、森の中にひっそりとあった。
複雑にからみあった熱帯植物の蔓や根が、壁のように視界を塞いでいる。
その中を細く伸びる石畳の道を進んで行くと、
生い茂る木々の葉の向こうに、明るい空間が見えてきた。
そこには何もなかった。
巨大な岩が屹立する空間に、ただ光が差し込んでいた。
でも、何もないが、気配は感じる。
何者かの気配がその場を濃密に満たしていた。
初めて沖縄の御嶽を訪れた時、その場にただ立っているだけで、心の底から畏怖の念が湧き上がってきたことを、いまもありありと思い出すことができる。
沖縄の土地には不思議な力がある。
この島の風土は、人間のスケールを超えた悠久の時の流れを生み出す力を秘めている。島は昔からさまざまな勢力に支配されてきたが、人々は島の風土に抱かれるようにして苦難を乗り越えてきた。人々にとって島は「宝物」なのだ。
真藤順丈さんの直木賞受賞作「宝島」(講談社)は、アメリカ占領下にある沖縄の戦後をまるごと描いた大作。歴史に翻弄される人々の人生と沖縄の風土を見事に描き切った傑作だ。
戦後まもない沖縄には、米軍の施設から物資を盗み出す「戦果アギヤー(戦果をあげる者)」と呼ばれる人々がいた。「戦果アギヤー」のリーダーであるオンちゃんは、盗んだ物資を貧しい人々に分け与え、弱冠20歳の若者でありながらコザの街の英雄だった。
ところが1952年の夏の夜、嘉手納基地を襲撃したオンちゃんは、米軍に発見されてしまい、逃走する過程で消息を絶ってしまう。捕まったわけではなく、基地の外に逃れることはできたらしいのだが、忽然と姿を消してしまうのだ。
ただし本書の主人公はオンちゃんではない。本書で描かれるのは、オンちゃんがいなくなった後の幼馴染たちの長い人生だ。
襲撃に加わったグスク、オンちゃんの弟のレイ、オンちゃんの恋人のヤマコ。この3人の、沖縄返還までの20年の人生が物語のメインとなる。
3人はそれぞれ、刑事、テロリスト、教師への道を歩むが、それぞれの人生に、戦後の沖縄で実際に起きた事件が絡んでいく。
米兵による凶悪な犯罪や、米軍と市民との理不尽なまでの地位的な格差といった現在も繰り返され、いまだ解消されていない問題はもちろんのこと、米軍施設からの毒ガス漏洩事件(1969年、米軍施設内でVXガスが漏洩した事件が明るみに出た)や、度重なる事件への怒りが頂点に達して起きたコザ暴動(1970年)など、数々の現実の事件を背景に物語は進んでいく。この小説を読む人はその苦難の歴史にきっと言葉を失うだろう。
ここで注意してほしいのは、この小説が、英雄オンちゃんがいなくなってしまった後の物語であることだ。この物語は「英雄不在」であるという点に大きな意味がある。
3人はオンちゃんを探し続けるが、なかなか見つけることができない。英雄が不在のまま、その後の人生を懸命に生きなければならなかった3人に、おそらく作者は、戦後の沖縄の人々の人生を重ねているのではないだろうか。英雄はいない。もう手を差し伸べてくれる人はいない。それはなんと困難な歩みだったことだろう。
だが、この小説を読み進むうちに、もうひとつの大切なことに気づくはずだ。
英雄不在の中、自らの人生を切り拓いてきた沖縄の人々こそが、「英雄」だったのではないかと。そして人々を英雄たらしめているものこそ、この島の風土なのだと。この島に守られて育った人々は、彼らにとって何ものにも代えがたい宝物を守るために戦ってきたのだ。
この物語で描かれた時代と同じ、戦後まもない沖縄を訪れて衝撃を受けたのが、岡本太郎である。彼は初めて訪れた沖縄で、島の民俗文化の中に深く分け入っていく。その旅の興奮は、「沖縄文化論—忘れられた日本」にまとめられている。
この本の中で、岡本太郎は「文化とは何だろう」と自問しながらこう述べている。文化とは、その土地を耕すことで生成され、やがて根を張ったもので、その耕される土壌こそが、民衆の生活であると。
日本の過去の文化の多くは、大陸の文化をそのまま取り入れるか、またはその巧みなアプリケーションに過ぎなかった。その土地だからこそ生まれたと言える文化がいったいどれだけあるだろうか。岡本太郎はそう問いかけ、島の風土が生み出した沖縄の文化に惜しみない共感を寄せている。
著者は東京出身だが、聞くところによれば、琉球語の辞書の用例を諳んじるくらい読み込んで、本書を執筆したという。激動の戦後を生き抜いていく3人の人生を物語る地の文に、時折「あきさみよう!」といった感嘆の声が合いの手で入るのが、読んでいてとても心地よい。この語り手の声が、物語に突き抜けた明るさを与えている。作中でいくつもの悲惨な事件が起きているのに、この語り手の声は、どこか人間の大きさを超えたところから響いてくるようだ。
この地の文の「語り手」は、沖縄の風土そのものではないだろうか。この島で生まれて死んでいったすべての人々の声を、沖縄という土地の「地霊」の声を、著者はおそらくイメージしているはずだ。
沖縄の歴史は苦難に満ちている。でもそこで生きる人々は強い。逞しく、明るく、ゆったりとしていて、ユーモアがある。それらはすべて島の風土によって育まれたものだ。
沖縄の地霊が語る小さな英雄たちの物語。島の風土から生み出されたようなこの物語を、ぜひ多くの人に体験してほしい。![]()