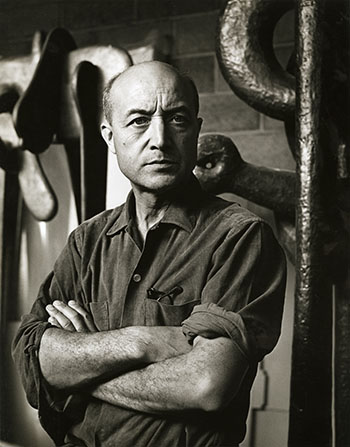INTERVIEW | 展覧会 / 建築
2018.12.26 16:22

現役の一作家にフォーカスした展覧会を、私たちはある種の“顕彰”と捉えがちだ。すばらしい作家がいて、その価値を高く認め、さらに広く知らしめるため、彼/彼女の展覧会が企画されたのだ、というふうに。しかしそれが展覧会のすべてではない。東京オペラシティ アートギャラリーで開催された「田根 剛|未来の記憶 Archaeology of the Future ─ Digging & Building」展の担当キュレーターの野村しのぶは、こう明言する。展覧会とは、観る人や作家、キュレーターが「どう生きるか」をともに考える場で、建築展は私たちが生活する建築と都市を手掛かりに、議論を活性化させるためのものであると。
彼女がこの展覧会を構想したのは2012年、東京オリンピックに向けた新国立競技場のデザイン・コンクールが行われた後だった。ファイナリストとなった、田根が設立メンバーのひとりである Dorell.Ghotmeh.Tane/Architects(DGT.)の「古墳スタジアム」案を目にして、彼女はそこに強いメッセージを読み取ったという。
「あのコンクールに古墳をモチーフとして提案したことに反骨精神を感じました。古墳とは、縄文や弥生という人々がより小さな単位で暮らしていた時代に対して、強大な権力が生まれた中央集権的な時代の象徴です。オリンピックに関連するものごとが政治的にも経済的にも権力側の論理で進んでいく状況に対して強烈なものをぶつけてきたと思いました」
今回の展覧会で展示された古墳スタジアムの模型は実寸の1/100のサイズで、内部に人が入れるほどの大きさがあり、竣工した場合のスタジアムを想像できた。東京に林立しつつある高層ビルの人工性との対比が印象的だった。

▲「古墳スタジアム」は、この地域の歴史的経緯を、森のような建築によって未来に受け継ごうとした。
「こんなスタジアムができたらよかったのにね、という感想を何度も聞きました。とはいえ私自身はそうは思えずにいます。古墳というモチーフは重い意味を持つにもかかわらず、現在の状況でそのことを意識させずに完成するとしたら恐ろしい。古墳スタジアムの楽観的な受け取られ方については複雑な気持ちです」
野村の思いは、2014年に同館が開催した「ザハ・ハディド」展から一貫していた。新国立競技場の建設は国家的なプロジェクトであり、東京都心の一等地に、莫大な額の税金を使って数十年にわたり使用される巨大施設がつくられる。それが後世までの大きな財産になるのか、または負担になるのか。国民はそれについて知る権利とともに、考える責任がある。コンクールに参加した設計者の思想や活動を知ることは、人々がこうした意識をもつきっかけになる。
「新国立競技場について問題だったのは、誰も何も決めていないところだと、田根さんが話していました。私もそれに同感です。そして、それは今の日本で起きている色々な問題に通底していることだと思います」

野村が展覧会を決心したもうひとつの理由に、DGT.が設計して2016年に完成を迎えようとしていた「エストニア国立博物館」があった。2005~06年開催のコンペにおいてDGT.は、募集要項で示された敷地に隣接する、旧ソ連占領時代の軍用滑走路に博物館を建てる案を提示した。国民にとって負の遺産でもある滑走路を、自国を象徴させる施設に活用することには、エストニア国内で否定的な声も大きかった。しかもコンペの時点で田根は20代半ばで、コンペ参加のために結成されたDGT.は無名の若手建築ユニットに過ぎなかった。この建物について、野村はこう見る。
「コンペの募集条件に合っていないにも関わらず、場所の文脈を踏まえたあの作品を提出したことは若い彼らならではの大胆な挑戦だったと思います。そして、何よりこの案を受け入れたエストニアの人々に感心させられます。新国立競技場の奇妙な顛末をはじめ、日本の状況を考えると、国の負の遺産に光を当てるような案が日本で実現できるでしょうか。これがつくれる国民から、私たちが学べることはたくさんあると思いました」

▲「田根 剛|未来の記憶 Archaeology of the Future―Digging & Building」
展示風景
東京オペラシティ アートギャラリー
2018
photo: Keizo Kioku
実は今回の展覧会の準備途中で、野村が古墳から読み取った意味を、田根が意識していなかったと聞くことになった。田根の念頭にあったのは、新国立競技場を100年単位で受け継がれる森にすることや、森のつくりかたを隣接する明治神宮内苑の森に倣うことだ。そして、オリンピックの起源である古代ギリシアの土地を掘り込んだスタジアムの形式を参照しつつ、日本の歴史上最大の建造物である古墳と関連づけた。古墳が多くの人々の手で建造されたことをはじめ、色々な意味を持つものとして扱いつつも、それを現在のオリンピックに象徴される日本の政治や社会へのアンチテーゼとしたわけではなかった。
「田根さんは無垢な人で、それは彼の建築家としての大きな魅力です。ナイーヴという語が肯定的に使われる日本においては特に、無垢さは強さになります。さまざまな困難な状況をさらりと突破することもできるのかもしれません。とはいえ、通過するだけでは問題への意識が置き去りになってしまいます。
私は展覧会とは、自分たちがどういう社会をつくりたいか、どう生きるかを議論したり思考したりする場でありたいと考えています。そのような意味では、田根さんの建築は形としても物語としてもアイコニックで私たちの感覚に直接的に訴える魅力がある一方で、私たち自身の問題を考える余地を与えてくれているか、とも考えます。それはこの展覧会を制作する方向性についても同様でした」
こう話すように、野村は田根の建築や思考を複眼的に考察しながら、展覧会に取り組んでいた。

「田根剛|未来の記憶」展の冒頭には、天井高6mの大空間を使った、「『記憶』という概念そのものをリサーチする実験空間」があった。壁や床には無数の画像が掲示され、それらが12のキーワードに分類されて、さらに細かいキーワードが添えてある。田根が展覧会に際して記したテキストには、「私はいつも考古学者のように遠い時間を遡り、場所の記憶を掘り起こすことからはじめます」とあった。この展示手法について、野村は話す。
「ほんの少し前までは画像ひとつ手に入れるだけでも文献を探し、そこに著された参考文献をさらに辿り、と、今とは比べものにならないほど手間と時間がかかりました。その過程は、情報そのものはもとより、それを残してくれた先達への敬意を自然に抱かせました。しかし現在はそれを意識せずに、情報の海の中で無数のイメージにアクセスできる。過去の事柄を調べる作業を、考古学に倣って発掘と表現していますが、私は採集というほうが言葉としては近いと考えています。文脈や情報の扱い方はとても現代的だと思います」

▲「田根 剛|未来の記憶 Archaeology of the Future―Digging & Building」
展示風景
東京オペラシティ アートギャラリー
2018
photo: Keizo Kioku
「考古学」という言葉は、この展覧会のタイトルに「Archaeology of the Future」とあるように、田根のアプローチを表現する重要なアレゴリーである。個々のプロジェクトに際して、過去に遡って丹念にリサーチを行うことが、新しく建築を発想する原動力になるということだろう。そこでのアプローチは、直感的で衝動的な面を持ち合わせる。無垢という言葉には、そんな意味も含まれているようだ。
「田根さんの無垢さは建築家としての武器であり、閉塞した状況を突破する力になりえるでしょう。しかし建築家は無垢と成熟を兼ね備える必要があります。私はそれを、自分の求めるものに正直であることと同時に、他者の立場にも立ってものごとを考え、両立するように進めることだと思います。またそれは建築家だけに求めることではなく、私たち自身に当てはめて考えてみたいことでもあります」と野村は話す。

「田根剛|未来の記憶」展は、田根の創造性を伝えるという意味で実に見応えがあり、来場者からも好評を得たに違いない。あるプロジェクトの背景に、時間的にも空間的にも多岐にわたる情報やイメージが存在していることと、それを読み解いてひとつの形にする建築家の奇跡的な能力に、誰もが圧倒されたことだろう。
「経験したこともない、想像すらしたこともない」建築を、「場所の記憶」を手がかりとして現実に創造しつつある、田根の姿勢は眩しい。だからこそ、その魅力をあらゆる人々が自身と社会に関係づけて考えるきっかけにしたいと企画されたのが、この展覧会だった。さまざまな「問い」の種が、会場の中にひそんでいたのだ。今後の田根の活躍が、このような企図の延長線上においても実り多いことを期待したい。![]()
「田根 剛|未来の記憶 Archaeology of the Future ─ Digging & Building」
- 会期
-
2018年10月19日(金)〜12月24日(月)
*現在は終了 - 会場
- 東京オペラシティ アートギャラリー
- 詳細
- https://www.operacity.jp/ag/exh214/