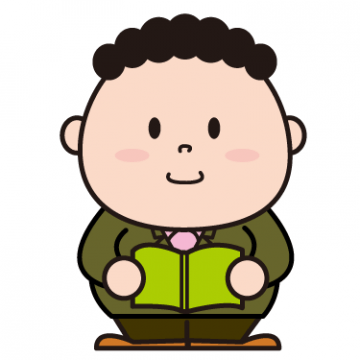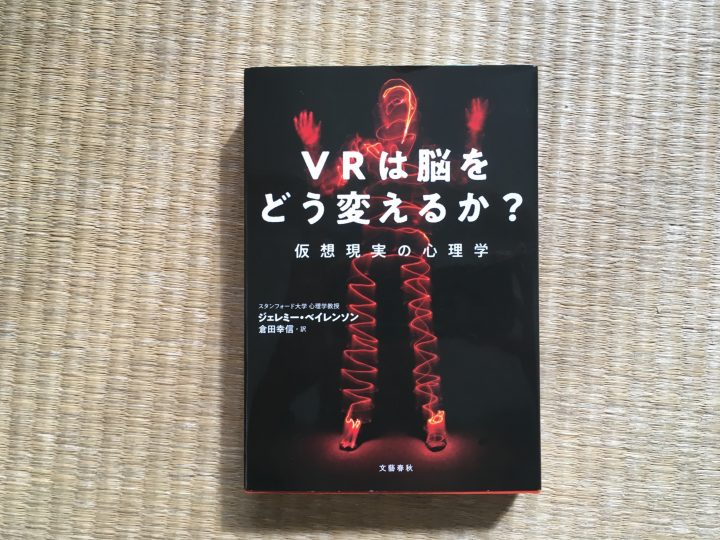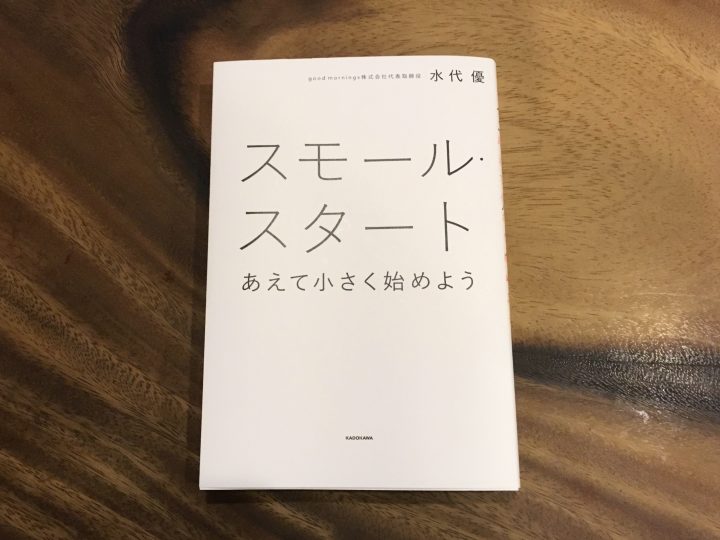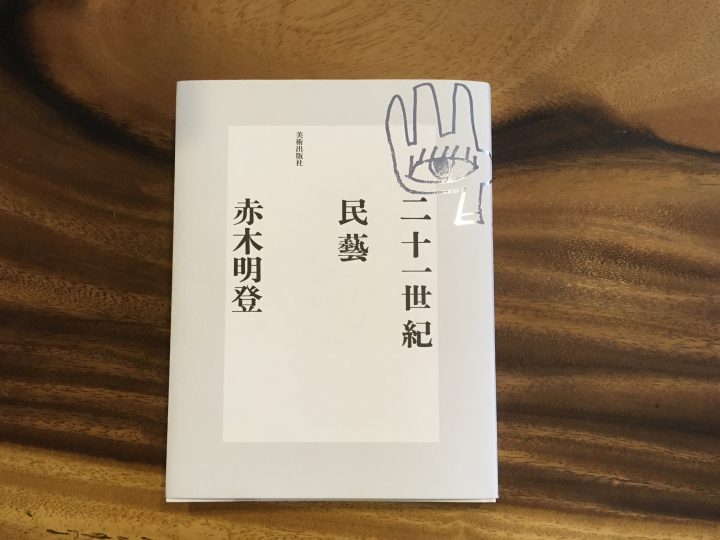「事実は小説よりも奇なり」という使い古された言葉があるけれど、現実には小説をしのぐようなドラマティクな出来事にはそうそうお目にかかれない。だが、これはどうだろうか。
ケンブリッジ大学の若き神経科学者エイドリアン・オーウェンは、同じ研究者だったモーリーンと恋におちる。ほどなくしてふたりはロンドンのアパートで一緒に暮らし始めた。だが最初のほうこそロマンスの興奮であふれていた同居生活も、やがて退屈な日常へと取って代わり、口論が絶えなくなった。
あれほど愛し合ったにもかかわらず、ふたりは憎み合ったまま別れてしまう。
モーリーンと別れてから4年後のある日、同僚から彼女が事故に遭ったことを知らされる。自転車で木に突っ込んだ彼女は脳の動脈瘤が破裂し、くも膜下出血を起こしていたのだ。彼女はすぐに植物状態と診断された。
見たところまったく応答のない人の脳にも、ひょっとしたらなんらかのかたちで意識が存在しているのではないか?モーリーンの事故は、そんな疑問の種をエイドリアンの中に蒔いた。その後、エイドリアンは研究者として頭角を現す。「植物状態」と診断された患者に意識があるかどうかを診断する方法を編み出したのだ。彼の研究は世界的な注目を集めていく。そして彼は自らが考え出した手法を使って、植物状態にあるかつての恋人と向き合うのだった……。
これは「生存する意識 植物状態の患者と対話する」エイドリアン・オーウェン 柴田裕之訳(みすず書房)に出てくる実話だ。モーリーンとのエピソードだけでもまるでドラマのようだが、この本の中にはさらに驚くような話が詰まっている。ぼくはためらうことなくそれらを「奇跡」と呼びたい。本書は人類が初めて経験した奇跡についての物語なのだ。
著者が探求してきたのは、「グレイ・ゾーン」と呼ばれる曖昧な領域だ。
植物状態や昏睡状態がこのグレイ・ゾーンにあたる。呼びかけても目を開けず、なんの認識もないように見える人もいれば、呼びかけに応じて時折、指を動かしたり、目で物を追ったりする人もいる。著者はこうしたグレイ・ゾーンにある人と初めて「ファースト・コンタクト」することに成功した科学者である。
著者は90年代からグレイ・ゾーンにある人の診断を続けてきた。
著者が編み出した手法は画期的だ。グレイ・ゾーンにいる人に呼びかけ、2つの事をお願いする。ひとつは「テニスをしているところを想像してください」。もうひとつは「自宅の中を歩くところを想像してください」だ。このふたつではそれぞれ脳の反応する部分が違う。テニスをするところをイメージすると、運動前野が活性化し、家の中を歩き回るのを想像すると海馬傍回と呼ばれる皮質領域が活性化するのだ。これを、人体をスキャンする技術で観察するのである。
具体的にはこんなふうに患者に問いかける。
「いま痛みがありますか?イエスならテニスをしているところを、ノーなら自宅の中を歩き回っているところを思い浮かべてください」
この手法を使って初めて患者とのコンタクトに成功した瞬間は本当に感動的だ。著者によれば、植物状態にある人の15〜20%は、たとえどんなかたちの外部刺激にまったく応答しなくとも、完全に意識があるという。
これは大変な発見だ。それと同時に恐ろしいことでもある。
本人に意識があるにもかかわらず、医師や家族が傍で生命維持装置を外す相談をしていたら?著者はコンタクトに成功した患者にさまざまな質問を投げかけている。その中には「死にたいですか?」などというどきりとするような質問も含まれる(その回答は多くの人にとって予想外のものだろう。ぜひ本書で確かめてほしい)。
相模原の知的障がい者の施設に押し入り19名のも命を奪った犯人は、呼びかけに反応がなかったというだけで被害者を刺していった。本書を読めば、犯人の行為がいかに無知と偏見に基づいた愚かな行為かということがよくわかる。
「自己決定権」や「生産性」などという言葉も軽はずみに使えなくなるはずだ。
本書を読んで痛感したのは、私たちはまだ何も知らないということだ。脳の不思議について。意識の謎について。生と死の境界線について。人類はまだ、ほんのわずかのことしか解き明かすことができていない。
手塚治虫の名作「ブラック・ジャック」にこんな話がある。
かつてブラック・ジャックの命を救った医師・本間丈太郎からある日、カルシウムの鞘に包まれた手術用のメスが送られてくる。それは臨終の床にあった本間が過去の手術ミスを告白するきっかけになるのだが、最期に本間はブラック・ジャックにこんな言葉をかけるのだ。
「どんな医学だって、生命のふしぎにはかなわん」「人間が生きものの生き死にを自由にしようなんて、おこがましいと思わんかね」
意識とはなにか。生きるとはどうことか。その神秘にぜひ触れて欲しい。
一年の終わりに、この奇跡の物語をあなたに贈りたい。![]()