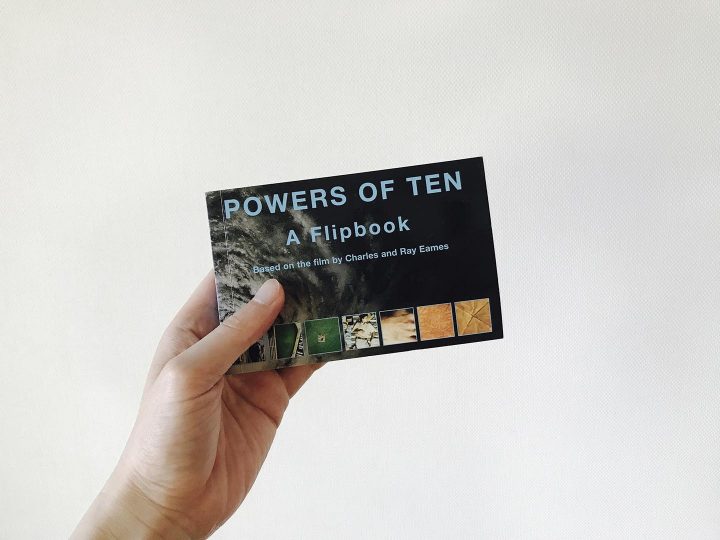年末年始は帰省して、息子と凧揚げをしたり読書をしたり、のんびりと過ごした。正月にはたくさんご馳走が並ぶが、なかでも雑煮には目がない。正月にしか食べられないと思うから、ついつい食べ過ぎてしまって、正月が終わる頃には毎年顔が少し丸くなっている。雑煮は出汁の澄んだ味と野菜の甘みに、焦げた餅の香ばしさが混ざり合ってしみじみ美味しいと思うのだが、母親に味付けはどうかと聞かれても、ちょうどいい、ちょうどいいと子どものように繰り返すだけで、その美味しさをうまく言葉にできない。
そもそも「美味しい」は一言で表現できないのかもしれない。美味しさを形容するには、二言以上必要である。「甘い」とか「辛い」とか一言で言える表現は、味を表現する際には褒め言葉ではない。「甘過ぎず、辛すぎず」とか、「淡白だが、コクがある」とか、美味しいものは両極の味や食感が絶妙に混ざり合っている。異なった個性を持った素材や調味料が掛け合わされ、均衡が生み出された状態が「美味しい」ので、「うまい」とか「ちょうどいい」とか、調和の妙は一言で表現できても、味そのものは簡単には形容できないのだ。一言で表現できるということは、意識化されるほどひとつの個性が際立っていて、バランスが崩れているということなのだろう。美味しいものの前ではみんな無口になるしかない。
大学でデザインの講評をしていると、初めに持ち寄られるデザインは引っかかりばかりで、その違和感は一言で表現できてしまうものが多い。何度も講評と修正を重ねていくと、ばらばらだった要素がからまり合い、やがてほどけない塊になる。そうなると「いいね」という漠然とした感想しか出てこない。良いと感じているのに、その良さを一言で形容できない状態が理想的なのだ。「ちょうどいい」をつくるのはなかなか高度である。今年も母親の雑煮をすすりながら、感じ入っている。