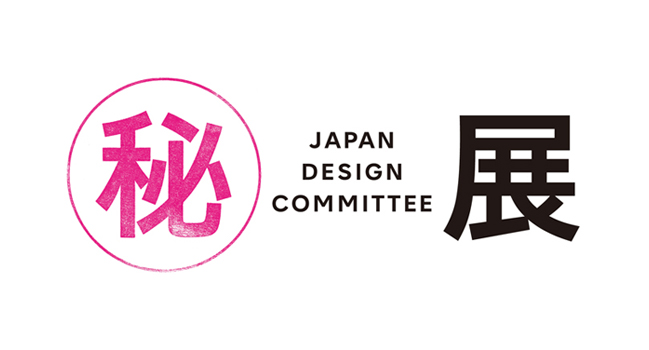INTERVIEW | 建築
2017.05.16 19:15

東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTで、アスリートの身体と心に迫る「アスリート展」が開催されている。
展覧会ディレクターを務めるのは、為末 大(元陸上競技選手)、緒方壽人(デザインエンジニア)、菅 俊一(研究者/映像作家)の3名。約30組の作家が展示に参加し、身体や心理、それらを鍛えるためのテクノロジーといった視点からアスリートとは何かを紐解いている。体験型の展示を通して、鑑賞者がアスリートの感覚を自らのそれに置き換えることのできる内容だ。
本展の会場構成を手がけたのは、建築家の工藤桃子と高橋真人。メイン会場を体育館に見立て、アルミのフレームと寒冷紗のスクリーンを用い、“開放と集中”という視線の変化を活かした構成だ。工藤は「これだけ規模の大きい会場デザインは初めて」と語るが、インテリアデザインで培った構成力と素材に対するノウハウを存分に発揮し、建築と共鳴するような会場デザインを実現している。その意図や直近のプロジェクトについて、工藤に聞いた。
身体の限界値を体感する
工藤さんはどの段階からアスリート展の企画に関わったのですか。
企画のスタート時からです。21_21 DESIGN SIGHTの方から「アスリートについてどう思う?」という問いをもらったのが最初。そのときはまさか会場構成を担当するとは思いませんでした。力強く筋肉質なアスリートのイメージを、女性の目線からソフトで美しいものにという意図があったのではないかと思います。昨春くらいから企画チームの一員として「アスリートとは何だろう」と考えていきました。

▲ Takram「アスリートダイナミズム」。 © 21_21 DESIGN SIGHT
「驚異の部屋」と題したギャラリー1では、ポリゴンの人体が壁4面を走ったり、飛んだりしています。アスリートの動きを原寸で感じることができ、その速さや高さに圧倒されます。
アスリートの根源を探ることは、人間の身体の限界を追求することにつながります。映像は1分の1のサイズにこだわって、スポーツ工学研究所などの研究機関からデータを提供してもらい、モーショングラフィックに落とし込んで制作しています。
中央に設置したフレームは長さ6m、高さ3m。現在、人間が自力で飛べる長さと高さの限界値です。ポリゴンの人形はアーティストの菊地絢女さんによる造形。立体展示があることで、自分の身体と比較でき、驚きが増すのではないかと思います。

▲「驚異の部屋」。アニメーションは高橋啓治郎、人形造形は菊地絢女。
身体と心が繊細につながる空間
メインのギャラリー2に入ると、奥行きや高さを含めて展示空間の広さを活かした見通しの良さに目を見張ります。
「空間全体を使ってほしい」というディレクター陣の要望がありました。これまでの展覧会は什器にプロダクトを展示するなど、視点を下げるかたちで見せることが多かった。今回は体験型の作品が多いので、身体で空間全体を感じられるような構成が求められました。
体育館という場では、同時に行われているいろいろな競技をすべて見渡すことができます。ギャラリー2に入ったときも、いちばん奥にある展示までを見通せるようにしたいと考えました。そのため、天井から下ろしたスクリーンをすべて斜め20度くらいに振っています。

▲ ギャラリー2に入ると、会場奥までを見通すことができる。Photo by Hideki Makiguchi
作品配置の意図を教えてもらえますか。
会場構成はあくまで背景なので、わかりやすさを心がけました。まず全体をレイヤー構造にして、手前のレイヤーに体験型の作品を集めました。アスリートにとって「タイミング、グレーディング、スペーシング」という要素が大切なんです。来場者が自身のそれらを測定し、アスリートとの差や難しさを知ることで、彼らの身体能力を実感してもらいたいと考えました。
次のレイヤーでは、アスリートの内面や心理を扱っています。トレーニングさえすれば身体能力が高まるかと言うと、実は心理的に引き戻されるなど、そうではないバランスがあるそうです。為末さんも「身体と心のバランスの良さがトップアスリートにつながる」と仰っていました。そこで今回は、その2つを明確に分けずに、ゆるやかにつなげたいと考えました。
天井からの半透明のスクリーンが各展示をゆるやかに区切りつつ、つなげています。この素材を選んだ理由を教えてください。
アスリートは強くマッチョなイメージがありますが、常に揺れ動いている彼らの心理みたいなものを表現したいと考えました。「身体」と「心」のレイヤーの境目として、半透明の寒冷紗を使っています。建築で用いる寒冷紗は塗装の目地を補修するための下地材ですが、ちょうどよい網目の大きさなので、重なるとふわっと霧がかかったように見える。アスリートの心理を表現するのにぴったりだと思いました。

▲ 寒冷紗のスクリーンを斜め20度に振ることで、鑑賞者の見る角度によって透明度が変化する。4.8mの天井高いっぱいに使われている。Photo by Hideki Makiguchi
作品のパーティションや什器にはアルミが使われています。
アルミはアスリートのシャープで精緻なイメージから。また、重い印象にならないように心がけました。オフィス向けユニットシステムの既製品を使って組んでいます。日頃インテリアや建築で用いる素材とは異なり、軽やかで、しかも会期が終われば解体するものなのでアプローチも異なり、個人的にとても面白いチャレンジでした。

▲ 展示什器は既成のユニットシステムのパーツ。天板の存在感が出すぎないようにグレーで塗装した。Photo by Hideki Makiguchi
素材の特徴を素直にとらえたい
ところで、工藤さんが建築に取り組むうえで心がけていることはありますか。
建築をやりたいと思ったきっかけは民俗学なんです。今 和次郎と柳田國男から入ったので、今でも、国内外限らず地方の村などに行ったときには、その土地ならではの建て方や素材の使い方をよく見ています。
私が設計を始めた頃は、本物の木らしく見えるシートなど、フェイクの素材が世の中にいっぱい出てきた時期。日本の建築法規が少し解放されたからだと思いますが、私はそれらがあまり好きになれなかった。木目が複雑な曲線を描いたり、同じ木目が反復されるのはおかしいのではないか。そうではなく、「木はこういうもの」と特徴を素直にとらえて、素直に空間に置きたいんです。スチールでしかつくれない薄さをわざわざ木目で覆う必要はないですよね。そう考えていくと、密度や重さにつながっていくのかもしれません。
ひとつの物件に対してひとつの新しい素材をつくるそうですね。
インテリアを設計するときも建築を意識しながらつくりますし、リサーチ的な意味もあって常に素材のスタディを重ねています。ある物件のために石の研ぎ出し材をつくりましたが、通常は大理石を入れるところを、空間に柔らかさや有機的なイメージを与えるため、川石を入れて研いでもらいました。ほかにもいろいろと試したい素材ネタはたくさんあります。

▲「House O」のために開発した川石の研ぎ出し材を用いたキッチン。Photo by Hideki Makiguchi
建築の「重さ」を引き受ける
最初の建築物件が4月に着工を迎えたそうですね。
青森の個人邸なんですが、「観音様が守っている」と伝えられる小さな村にあります。地名に動物の名前がたくさんついていて、観音様の湧き水が村全体の生活用水にもなっている。そんな不思議な空気感のある土地に、海の見える家をつくります。土地の素材を使うことを心がけているので、産地の木材をたっぷり使って、5年後、10年後に色が変わったらようやく完成と言えるような。木材に合わせて屋根などの材料も選んでいるため、竣工時には未完成と言えますね。

▲ 青森の個人邸のコラージュ。敷地が1haもあるため、家のかたちを長く引き伸ばして森まで入り込んでいくようなイメージ。© MOMOKO KUDO ARCHITECTS
根室でも宿泊施設のプロジェクトが始まったそうですね。こちらも興味深い土地です。
春国岱(しゅんくにたい)と言って、600haの湿地・原生林に1500〜3000年かけてできた海岸、草原、湿原、森林、干潟といった多様な環境が共存する場所です。空も川も見たことのない色をしているんです。落葉樹と針葉樹のバランスがよく、たくさんの動物や魚が暮らしている豊かな場所。そばにはアイヌの集落があって、なぜここを村にしたかが自ずと感じられます。

▲ リサーチを重ねている根室。Photo by Momoko Kudo
この土地では厳しい気候が大切で、それによって人と自然が共存しています。外部環境から守られた建築ではなく、モンゴルのゲルのように自然のなかに人が入っていくような建物にしよう、という構想までは決まっています。ゲルは羊毛を圧縮してつくられるので、根室でも素材づくりからできたら面白いだろうなと考えています。今後1年ほどかけてリサーチし、来年から計画が順次進んでいく予定です。
アスリート展の会場構成にしても、最近のプロジェクトにしても、独特の「素材感」が印象的です。軽やかさだけではない、建築の「重厚さ」を受け入れようとする姿勢というのでしょうか。
これまでは建築を「ない」ものにしようと、ガラスを使うなどして存在を軽やかにしてきたことが多かったように思います。一方、私たち世代の建築家は、「でも、ガラスも物質だよね」と認めるところから始まっているのではないかと。建築がもともと土地に縛られた重い存在であることを引き受けたうえで、次のアプローチを見つけたい。ある意味、素直な世代と言えるのかもしれないと思います。(終)

▲ Photo by Simone Becchetti
工藤桃子/東京生まれ、スイス育ち。2006年多摩美術大学環境デザイン学科卒。07年から11年まで松田平田設計勤務。13年に工学院大学大学院藤森研究室修士課程修了後、15年までDAIKEI MILLSデザインユニットとして活動。15年にMOMOKO KUDO ARCHITECTSを設立。maison DES PRESやCIBONEといったショップデザインのほか、オフィスや個人邸のインテリアデザインも手がけている。http://momokokudo.com
21_21 DESIGN SIGHT企画展「アスリート展」
会期 2017年2月17日(金)〜6月4日(日)
10:00〜19:00
火曜休館
会場 21_21 DESIGN SIGHT