
『x-DESIGN』の著者による連載第2弾の今回は、筧 康明准教授と水野大二郎専任講師、エクス・デザインの最若手ふたりによる対談です。インタラクションを主軸にした研究を続ける筧と、ファッションが専門の水野、興味への原体験は異なるが、デザインへの考え方は近い。この本からどのような未来を考えるのか。
小さいテレビとバーバパパ
水野大二郎(以下、水野)
本の中で筧さんは「TECHTILE」という研究について書かれていました。これは原体験が関わっているんでしょうか?
筧 康明(以下、筧)
僕、実は自分がデジタルコンプレックスだったんじゃないかってことに最近気づいたんですよ。僕たちの子どもの頃って、大きく二分できると思うんです。それは、ファミコンを買ってもらった人と、買ってもらえなかった人。僕は買ってもらえなかった人だったんです。僕の父は高校の伝統産業科で、染織を教えていたんです。家電や機械は古いものをずっと使い続けて、最新のものは買わない。家をリフォームしようと言って、父が木を持ってきて、自分で床を張り替え始めたこともありました。そういう昔ながらであり、DIY精神溢れる家だったんです。だからファミコンはおろか、テレビもすごく小さいし、当然コンピュータは家になかった。絵を描いたり、モノを組み立てたり、遊びのルールを自作したり、アナログな要素を駆使して遊んでいました。だから、大学に入ってからもコンピュータはすごく苦手で、避けに避けまくった挙句、二十歳くらいまで触ったことがなかった。でも、いざ触ってみると、その瞬間からコンピュータが持っている即時性や計算可能性にすっかり魅了されてしまったんですね。

ただ、画面の中の世界だけで全て良いとも思えなかった。小さいテレビのおかげで、僕は今でも実家に帰ると、自分の部屋にはほとんど入らずに家族と一緒に居間にいる。テレビの大きさで家族の位置や距離が決まってくる。そういった、物理的な関係性の生まれ方とか、物理的な要素によって生まれる価値が面白いんです。研究を始めるときに、そんな物理世界のほうをコンピュータを使って引き立てることはできないかと思ったんですね。別に便利にしなくてもいいんだけど、デジタルを取り入れることで、身の回りの世界の中にいつもとは違う価値を見つけ出せる状態にする。そういったところが僕の原点ですね。

▲「TECHTILE toolkit (筧康明、南澤孝太、仲谷正史、三原聡一郎)2012」マイクと触感アクチュエータをモノや身体にとりつけることにより、感触のラピッドプロトタイピング(採集・加工・編集・伝送)を簡易に実現するツール。多くの人に使ってもらうべく開発・普及活動を行っている。2012年日本グッドデザイン賞受賞。
水野
僕は、ファミコンは買ってもらったのですが、ファミコンがくる前、3つのものに大きな影響を受けているんです。1つはレゴ、もう1つは油粘土、そしてバーバパパ。最初箱に書かれている手順通りにつくって、分解して、組み立てられるレゴにはまりました。その次に、なんでもつくれる油粘土にはまった。もうありえない形のものがなんでもつくれる、すごいなって思ったんです。そして、バーバパパが来ました。どうやらレゴも油粘土もバーバパパと同じだ、ということに気づいたんです。ぶよぶよしていて何にでもなれる。どうやら僕はバーバパパみたいなものになりたいらしい(笑)。
筧さんのお話で気づいたのは、エクス・デザインと似たことは他大学でも実践されていても原点が違う、ということでしょうか。
筧
そうですね。僕はインタラクションを設計する上で、さまざまな要素を積極的に取り入れたいと思っている。もちろん、その中にコンピュータも含まれるけれど、コンピュータは研究の目的ではなくあくまで要素の1つに過ぎないんですよね。人と人の距離や、そのとき着ている服のような要素と同列にコンピュータがある。そういった意味では、いわゆるHCI(ヒューマンコンピュータインタラクション)の分野の人たちとは違うかもしれませんね。

▲「at [case edo-tokyo](minim++/y.kakehi)2004」筧が開発したインタラクティブな空間演出システム「i-trace」を用いた、観客参加型の作品。筧が修士課程学生時代にminim++とコラボレートして制作。航空写真の床の上を歩き回ると、軌跡の上に、方角を示す十二支の動物の足跡とその場所の古地図が現れる。
「意匠」で終わらないデザイン
筧
水野さんにとってのデザインとは何なんでしょう?
水野
この本を書くにあたって、いろいろ考えたんですけれど、今回使ったデザインという言葉は「意匠設計」に近いかと思います。「デザイン=意匠」だけではなく、「デザイン=設計」も含めて、姿形だけじゃなくて、仕組みを含めて考えていました。
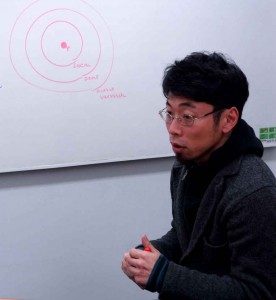
筧
僕もデザインという言葉はかなり広い意味でとっています。僕が興味を持っているのは、インタラクション、ものとものの関係性であって、形は付随するけれど、「意匠」という言葉には全く収まらない。もちろん、最終的に形にはなるし、その形が関係性を変化させることは面白いんだけど、狭い意味での「意匠」で終わってほしくないとは思いますね。
その点、水野さんにとってのファッションデザインは僕とは逆で、形あるものが先にきますよね。
水野
ファッションデザイナーの多くは、確かにすごく綺麗な人のための服をつくることはできる。だけど広義のファッションとは個人の話だけにとどまらず、服を着ている人たちが出会って町の空間をつくっていくことも視野に入れられるはずです。最初はただ製品の意匠のレイヤーを扱っていたはずが、より社会的なレイヤーからフィードバックを得たりすることも可能ですよね。筧さんの場合であれば、社会的なインタラクションを生み出すために、何らかの形あるものが必要になったりする。自分の専門領域だけを見ていると見えないけれど、実は、固有の製品のあり方から社会のあり方まで、全部つながっていると思うんですよね。
筧
今21_21 DESIGN SIGHTでplaplaxとして展示している作品の中には、コンピュータを使っていない作品もある。センサーがなくても、コンピュータがなくても、インタラクションの設計はできるし、僕らの中では今までの文脈とつながっているんです。ただ、僕らがマンマシンインタラクションを経由した経験は少なからずアナログなものをつくるときにも影響していて、動かないものだけをつくってきた人とは違う視点で作っている。

▲「苔画(木村 孝基、筧 康明)2012」。水分によって形を変えるスナゴケの湿潤・乾燥状態をコントロールすることで、その葉の開き具合の差でデジタルパターンを表出させるプロトタイプ。
水野
僕は、博士課程でファッションを学んでいた期間に、インクルーシブ デザインと呼ばれる、国籍、性差、障害など人々の差異をそのままにデザインするという設計思想や、サービスデザイン、デザインリサーチといった、もともとファッションデザインにはなかった他のデザイン領域の手法、思想に広がり、一般市民の創造力を問題意識として捉えるようになりました。今ではデジタルファブリケーションの利活用を通したデザインの可能性についても考えています。

そうやっていろんなことを経験した今、デザインの真ん中に来るのは顔の見えるユーザであり、そのユーザと協働できるメタレベルのデザイナーがいるんじゃないかと思うようになりました。メタデザイナーは無形のインタラクションや、形あるものだけでなく、すべてを設計するために環境を整備していく人なんじゃないかと僕は考えているんです。従来のデザイナーみたいに「グラフィックデザインができます」とかだけではなくて、物事をより広く見られる立場の人が今後は強く求められるようになると思います。つまり、ある程度一般的なスキルがあって、状況をよく観察し、ユーザの考えを把握できて、彼らと一緒に協働できる手法を持っていて、それらを使ってデザインするための環境も同時にデザインしていける人。
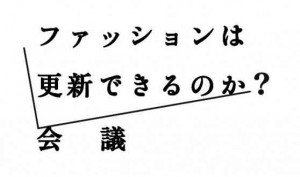

▲上:水野がモデレータとして参加した、ファッションの未来を考える「ファッションは更新できるのか?会議」。NPO 法人ドリフターズ・インターナショナルとNPO 団体 Arts and Lawが主催。
▲下:蘆田裕史とともに水野が創刊したファッションの批評誌。両者による自費出版。どちらのプロジェクトも、メタデザイナーのあり方を考える試みである。
筧
そういう意味では、SFCはメタデザイナーが育つ環境としていいのかもしれませんね。
水野
向いていると思います。SFCの環境ならば情報環境で今何が起きているかを知りつつ、今の世界にはどんな社会的な課題があるかを学び、デザインやテクノロジーの技術と掛け合わせてどのような未来を描くか、あるいはどのような問題を解決していくかを模索できると思うんです。ただ、頭で勉強しただけのメタデザイナーではおそらく表面的になりがちで、実体験を伴う成果物とか、制作を提案、実装できない。だから、実践することが大切です。姿形のあるものと、提言としての制作は入れ子になっているので、どちらかがないとうまく機能しない。学ぶ場と、実践する場、エクス・デザインはその両方になれると思っています。
*さらに詳しい内容については、x-DESIGNのこれまでの研究活動と所属する10名の教員それぞれの思想的背景をまとめた書籍『x‐DESIGN―未来をプロトタイピングするために』(慶應義塾出版会)をご覧ください。
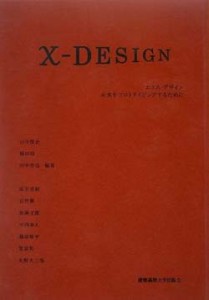
*第3回に続きます。












