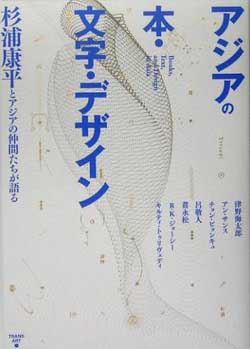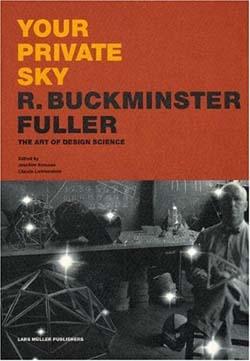『魂の保護を求める子どもたち』
トーマス・J・ヴァイス 著/高橋明男 訳(水声社 2,940円)
評者 韓亜由美(建築家・ステュディオ ハン デザイン)
「人生で出会う困難に対し、デザインができること」
日本もいよいよ少子高齢化社会を迎え、括弧付きの「ユニバーサルデザイン」の議論を脱してデザイン・フォー・オールの思想の定着が求められている。対象となる社会的弱者というのはもちろん老人だけではない。もう片翼の多数を構成する乳幼児から思春期までの子供たちを取り巻く状況はどうだろうか。この10年を振り返れば、妊娠・出産についての生命倫理問題から子供への虐待、家族関係の崩壊、不登校、荒れる学校、凶悪な少年犯罪の増加、子供の性の商品化、と挙げれば切りがないほど、暗澹たる気持ちになる現実がある。
子供たちは生来の無垢な弱者であるばかりでなく、20世紀の科学技術産業主導の進歩史の結末、歪みを一身に受け止めているかのようだ。戦争のただ中のイラクの子供たちならずとも、その存在の危機に直面していると言っても過言でない。
この本の著者は、シュタイナー教育の理論の実践者で、スコットランドの田舎で障害を持つ子供や成人のための(健常者をも含む)村落共同体—後のキャンプ・ヒル運動—を創立したメンバーのひとりであり、1939年から没するまで30年以上にわたって中心的役割を担った。
彼は本書の中で、子供たちの障害は、単に治療の対象としての独立した「病」としてではなく、周囲の環境との関わりにおける人間の総体的な発達上の障害として見るべきだとしている。つまり、正常な発達と見なされていても多くの潜在的な異常や欠陥の間に比較的、調和的な均衡が保たれているということでしかなく、子供の発達は環境のなかでそのような異常や欠陥に常にさらされている、ということらしい。そして障害と共に生きなければならない子供たちをその事実以上に苦しめているのは、実は「健常者」と自認する人々がつくり上げているところの誤解と無理解に満ちた環境かもしれないのだ。
本の主軸である発達障害の章では、「朝と夕べ(大頭の子どもと小頭の子ども)」「左と右」「麻痺のある子ども」「落ち着きのない子ども」「自閉症」「盲目の子ども」「難聴の子ども」「失語症の子ども」「情緒障害と不適応の子ども」「ダウン症の子ども」と異なる障害の経緯をつまびらかにし、それぞれに対する人間の本来の人格に寄り添った理解を促している。
私はこの本を読み進むなかで、障害児の治療教育についてというよりも、人間が成長してゆく過程で誰しもが出会うさまざまな困難、障害についての謎の多くが解き明かされてゆくような、まさに目からウロコが落ちる思いがあった。著者はまた、こう表現している。「小児期の発達障害をひとまとめにすると、そこには人間存在そのものを映し出す広範で魅力的で、美しい展望が浮かび上がる。それら人間像は誇張されたものではあるかもしれない。しかしだからこそ、それによって開示されることがらもとても多いのだ」と。そして諸科学の1つとしての教育ではなく、芸術である教育は成長する人間としての子供を養い、導くとしている。
例えば、数ある障害の中でも最も難しいとされる自閉症は、日本では平成6年に初めて法律的に障害者と認められた。一方で、かのビル・ゲイツはじめ自閉症を自認しながらも社会的に活躍する地位の高い人々は数多い。社会による小児期の発達障害に対する受け入れ環境の物理的、文化的側面による外的影響の大きさは計り知れない。また、心理的環境が持ち得る積極的な可能性をも示唆している。そんなとき、一体デザインに何ができるだろう。それとも子供を取り巻く環境自体をリデザインするべきなのだろうか。そして、本当に魂の保護を求めているのは子供ばかりではないはずだ。
今年5月4日、こども環境学会が設立された。設立大会の国際シンポジウムのテーマは「こどもと環境:都市化の中のこどもたち」であった。(AXIS 110号 2004年7・8月より)
「書評・創造への繋がり」の今までの掲載分はこちら。