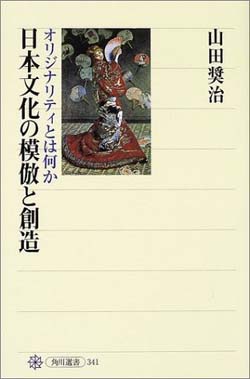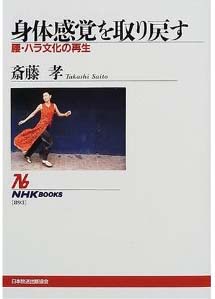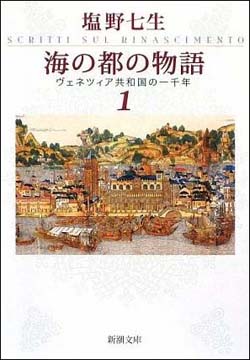『荷風好日』
川本三郎 著(岩波現代文庫 1,050円)
評者 和田精二(湘南工科大学教授)
「デザイナーは影を追い求めてはいけないのか?」
そういえば、出版界も映画界も江戸ブームである。本誌の前号に日産・クリエイティブボックス・NECデザインによる「江戸ナビ」の提案モデルが掲載されていた。助手席側に江戸時代の地図、ドライバー側に現在の東京の地図が現れる。近代の町並みの向こうに江戸を見ようというのだろう。表層的な東京でなく、江戸と東京を重ねることで東京を楽しむクルマによる散歩である。心のはずむ提案を考えるのはデザイナーの一般的な意識構造であろう。
さて、永井荷風の散歩の世界を基軸に、荷風の心の軌跡を綴ったのが川本三郎の『荷風好日』。「この本を読み耽るようになったら、変だ、おかしい、危ないんじゃないか」と松岡正剛説くところの荷風の『断腸亭日乗』の愛読者にしてくれた本である。生涯の大半を東京で過ごした荷風は、明治も深まってから知的遊民の特権を生かして散歩を楽しみ、現在も読み継がれている東京散歩随筆の嚆矢『日和下駄』を残した。川本は「大仰にいえばこの本によって文化としての散歩が確立した」と断定する。
散歩によって見えてくる風景は、人に見られることで初めて風景としての意味を持つ。国木田独歩が武蔵野の雑木林というこれまで誰も語らなかった風景を発見したように、荷風は下町の路地や横丁に詩情を見つけた。フランスから帰った荷風は、古い建物を次々に取り壊していく東京の近代化を非文化的なものと捉えた。東京から古き良き風景が消え、江戸の残り香がなくなっていく。せめて文章の中だけでも、あるべき東京の姿、良き風景を書きとめておきたい。『日和下駄』はそこから生まれた過去に向かう散策記である。本当に実在するのではなく、荷風の心の中にある町を求める。
ところが、皮肉なことに荷風はモダン都市と化した東京にひとりであることの豊かな孤独を味わえる絶好の隠れ場所を発見する。明治以来の日本の性急な文明開化を嫌った荷風は、華やかな表通りの賑わいに背を向け、横丁へ、路地へと入っていく。維新以来の文明開化の波をかぶっていない町に心ひかれていく。しかし、路地で生活している人間にそんな見方は余計なことであった。やがて、古き良き過去などどこにもないことを知った荷風は、見捨てられたもの、失われたものを、場末の遊び場の中に見ようとする。正確に言えば、過去に戻ろうとしたのではなく、幻影の過去をつくろうとした。こうして玉の井を舞台にした『濹東綺譚』が生まれた。
荷風の散歩が影を求める行為とするなら、前述の「江戸ナビ」は光を求める行為。デザイナーは夢を売る職能だから影を求めない。光を追いかけるデザイナーが影を追う文学に心酔してはいけないのであろう。デザイナーは本を読まないとぼやいていた出版人の声、書物を禁じられ、映像情報のみの生活を強いられる市民生活を描いたフランソワ・トリュフォーの映画「華氏451」の画面、「私は一段高い、安全な場所に立って、その痛ましさを眺めているのだった」と語った吉行淳之介の言葉を重ね合わせている。デザイナーが、影を意識の営みとして感じ始めたとき、デザインも変貌していくのだろうか。(AXIS 109号 2004年3・4月より)
「書評・創造への繋がり」の今までの掲載分はこちら。