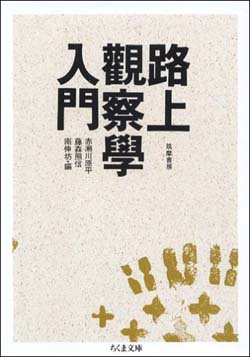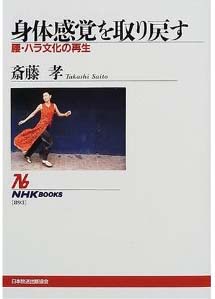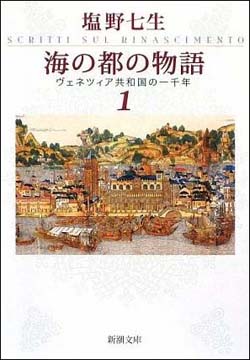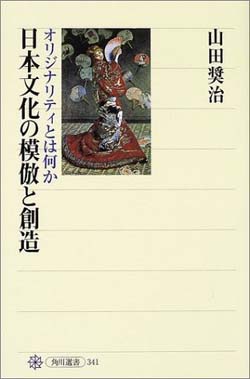
『日本文化の模倣と創造 オリジナリティとは何か』
山田奬治 著(角川選書・1,600円)
評者 和田精二(湘南工科大学教授)
「独創主義の弊害、『模倣』のすすめ」
世界中のコンピュータ・ユーザーが、知財権を盾にとったマイクロソフトの強引なビジネスに泣かされてきた。それだけに、ソフトウェア開発の優れた方法とされるリナックスのオープンソース方式には溜飲が下がる思いがした。ソースコードをあえてオープンにして、開発者コミュニティで共有し、大勢のプログラマーが改良に参加できる運営方法に曙光を感じたものだ。
さて、今回紹介するこの本の著者は、そこで展開されている方法論が、日本の連歌のルールと近似していると指摘、その分析結果から、リナックスのオープンソース方式を「独創」主義から「再創」主義への発想転換のよい例だと強調する。ここで、独創とはオリジナリティを指し、再創はすでにあるものを寄せ集め、コピーし、新たに何かを付け加えて創造することを指す。すなわち、「模倣」である。 最近、模倣の効用が説かれるようになった。
日本には古来「見立て」という模倣の方法論があったのに、それを捨てたことは日本の損失であったと松岡正剛氏は著書『日本流』(朝日新聞社刊)で書いた。養老孟司氏は、デザインはこれまで見て蓄積した記憶の組み合せから生じる脳の活動の結果であるから、真のオリジナリティはないと喝破した。アーノルド・トインビーも社会を動かすための模倣の仕組みをミメーシス(現実描写)と名づけ重要視した。そのあたりまでの模倣の概念は私にも理解ができる。ところが、この本はそうした理解の範囲を簡単に超えてくれた。何とも過激だが、論証に説得性があるので困惑してしまうのだ。
第1部では、人間の成長過程を例に、模倣の能力は人間の認識行動の基盤と断定し、第2部では、模倣を禁ずる制度である著作権制度に疑問を呈し、第3部では、日本の古典詩歌やさまざまな芸道のなかに、再創主義の実例を見ていくという筋立てとなっている。私流に要約すると以下のようになる。私たちは独創的であることは善いことで、模倣は悪いことと思いこんでいるが、そうした概念はそれほど古いものではない。オックスフォード英語大辞典第2版によると英語のoriginalityの初出は1742年、creativityは1875年。それまでは、言葉自体がないから、つくり出したものの中にoriginalityやcreativityが求められることはなかった。
近代までの芸術は、今で言う工芸に近く、ルネサンスの作品を芸術というのは近代的な価値観の後付けに過ぎない。日本も例外ではない。日本でも見立てという模倣は、浮世絵に限らず、和歌、庭園、建築、歌舞伎から芸道、料理にいたるまで、日本文化のあらゆる部分にあって文化の継続に役立っていた。日本の文化は模倣によって伝承されてきたのである。明治以降、欧米からの独創主義に影響されてきた日本にわずかに残る模倣による文化伝承の1つが、伊勢神宮の20年に1度の式年遷宮である。
大量の御神宝をそっくりデッドコピーすることで工芸品の製作技術が伝承されてきた。日本人の知恵に驚き入る。ところが近代国家の成立とともに、次第に創作物も経済的な利益確保の対象となり、国家存続のため独創は戦略的な成果物と化していく。米国の憲法が特許の権利を謳っているように。著者は最後に強調する。私たちが守るべきは人類の文化であって、一部の権利者の利益ではない。このままでは、私たちの文化が窒息してしまうかもしれない、と。
現代世界が競争原理で成り立っている以上、著者の言うことは知識としては理解できるが、私の行動を変えることは不可能である。しかしグローバリゼーションという美名のもとで日本の金を大国に搾り取られてきた現実を考えれば、われわれは近代社会の競争原理という呪縛の中に生きていることを思い知らされる。守るべきものは何なのか。ことほど左様にこの世の中は複雑で多層的であることを認識させてくれる本である。それにしても、こういった「独創」的な論をどんとぶち上げられる著者の見識と努力に敬意を表したい。(AXIS 104号 2003年6・7月より)
「書評・創造への繋がり」の今までの掲載分はこちら。