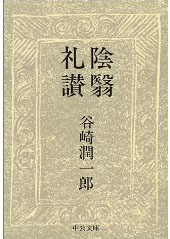
『陰翳礼讃 』
谷崎潤一郎 著(中公文庫 500円)
評者 深澤直人(デザイナー)
「なくしてしまった美の領域」
「今ごろ『陰翳礼讃』ですか?」と、芸術、文化、建築、デザインに詳しい諸氏におとがめを受けそうなくらいこの本は、日本人の美学を伝える本として、まるで教科書のようにたくさんの人に読まれているようである。私は情報に疎いので、自分がある感覚の領域に達したときに、やっとその本に巡り会ったりする。デザインもアートの本も知識を得るために読むより、著者と経験を共有しながら読むほうが楽しい。『陰翳礼讃』は日本はもとより世界で、日本人の独特な美的感覚を解く本として有名である。
1カ月ほど前に新潟県の十日町にあるジェ−ムズ・タレルの「光の館」に行ったときにも、そこにこの本が置いてあった。それから数日後、東京AADスタジオの卒業制作展の審査会で、今度、森アートミュージアムの館長に就任するデビッド・エリオット氏からもこの本の話が出た。そのときの展覧会のテーマは「ル−メン・シティー」だった。期せずして、共に光を題材にしたアートに触れたとき、この本に巡り会った。
近年、明るさは夜に昼をつくり出すような機能であり、暗闇は光の届かない部分として一括されてしまっている。明るいか暗い、その双方にあまり奥行きや幅を感じることができなくなった。『陰翳礼讃』は谷崎潤一郎の日常の経験をもとに、現代の「暗い」と称されている領域の中の微細な陰影に感じ入る美の感覚を捉えて解説している。現代の誰もが日常で想い浮かべる「光」という概念のなかにはすでに存在しないであろう感性のことを嘆き、陰のなかの「光」の微細な変化を美として生活にはめ込んでいた時代を懐かしむがごとく、この本を書いている。生活に明るさを求めるがゆえに失った、暗さのなかの抑揚。昔から受け継がれて今に形を残すものの本質的な美しさをわれわれは実は知らないのかもしれない。かつて陰の部分に包まれて完結した美を放っていたものと、現代のそれらのものは単に形が同じであっても、もう別のものなのかもしれない。
谷崎曰く、塗り物の吸い物椀の例で、その蓋を取って口に持っていくまでの間、暗い奥深い底のほうに、容器の色とほとんど違わない液体が音もなく澱んでいるのを眺めた瞬間の気持ち、を書いている。陰のなかの一連の動作から、匂い、椀の中の液体の重みや揺れ、湯気、温度といった複合の美が、暗くて視覚できない中身を、他のセンサーの複合によって感受する瞬間的な美の価値を解いている。それを、「一種の神秘であり、禅味である」と言っている。
確かに、現代に生きるわれわれは暗闇のなかの深さを知らない。暗さは「暗い」だけで奥がない。目が暗さに慣れるまでの時間を体験できない。明るさのなかの視覚情報は備わった身体の他のセンサーの感度を鈍らせてしまっている。
「われわれ東洋人は何でもない所に陰翳を生ぜしめて、美を創造するのである。(中略)われわれの思索のしかたはとかくそう云う風であって、美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える。夜光の珠も暗中に置けば光彩を放つが、白日の下に曝せば宝石の魅力を失う如く、陰翳の作用を離れて美はないと思う」。(本文より)
明るさを得たことによって失った美の領域。谷崎がこれを出版したのが昭和8年(1933年)だから、陰翳の美の領域を失いかけていたその時代からすでに70年程経っていることになる。建物、部屋、建具、庭、着物、肌、飾り、食べ物、紙、あらゆるものが陰翳のなかで放つ美を書き記したこの本は、われわれがもう体験することのできない欠落した領域を示している。闇や隈のなかでは感触や匂いや音、それらと組み合わさる時間の観念がより際立ってくるのである。われわれが京都を訪れて日本古来の美に浸るときも、その美はきっともう昔のそれとは異なっているのかもしれない。
光の館で友人が言った言葉を思い出す。「確かに、黒い、奥深い色をした羊羹が黒塗りの漆器の上にのって出てきたら、外国人は無気味に思うかもしれないね」。
闇のなかの深さ。浸透する光をこの本によって得た。(AXIS101号/2003年1・2月より)
「書評・創造への繋がり」の今までの掲載分はこちら。













