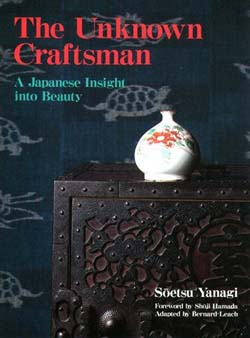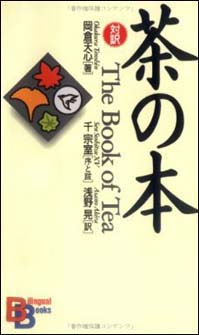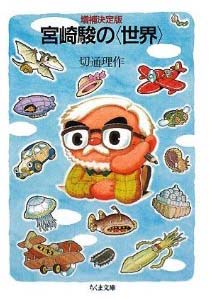
『宮崎駿の<世界>』
切通理作 著(ちくま文庫 1,155円)
評者 竹原あき子(デザイナー、和光大学教授)
「現代の若者の感受性の行方、飛翔感を読み取る」
10数年前、学生のレポートで「『雪の綿星』のラストシーンのような」という表現に出会ってとまどった。それ以来、彼らの文化現象を理解するために少女マンガ、アニメ、ゲーム、ヒップホップ、ストリートダンスなどに付き合ってきた。その経験から50年くらい昔の学生だったらニーチェ、カントなどを引用しただろうシーンに、現代の学生は「エヴァンゲリオン」の庵野秀明、や「風の谷のナウシカ」の宮崎 駿の言葉や登場人物の台詞をしばしば何の屈託もなく引用することに気がついた。今彼らを魅惑の世界に導く師は、文字世界に君臨する哲学者より、身近で現実と幻想が入り混じる世界を視覚的に描くマンガとアニメ作家のほうが多い。
本書『宮崎 駿の<世界>』はまさにその宮崎 駿の一挙手一投足に心酔し師とあおぐ青年、切通理作の宮崎アニメ紹介の労作だ。切通が「作品を体験し直す、という快感」にこだわり、まだ宮崎が無名だった時代からの全作品を綿密に、あたかも脚本をトレースするように描写し、動画の主要な場面と登場人物を解説している点では、アニメファンをも満足させる書だ。何度でも繰り返し、静止画像で観賞し直すことができるビデオの発達が、このようなスタイルの解説書を書かせた点でも、映像となったものすべての批評が新しい地平を切り開きつつあることを発見させる。
「紅の豚」と「魔女の宅急便」は良くできたアニメだったが、筆者は気恥ずかしくて我慢できない場面が多かった。その理由はストーリーはともかく戦後直後の衣食住のすべてに飢餓状態であった子供があこがれた風景や食物、ジェスチャーや物の価値観そして歌などが、これでもかと展開されていたからだ。ヨーロッパ文明へのコンプレックスの裏返しではないかと、我が少女時代の思い出と重ねながら席から腰を浮かせた。それを宮崎と同世代だけの特殊な反応といってしまえばそれまでだが、1970年代に米国とヨーロッパの影響から抜け出たデザイナーから見れば、なんと遅ればせの作風か、と目を疑った。もちろん「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」でその気配は薄くなった。だが失ってしまった日本の昔懐かしい風景や自然が美しすぎるのも物足りない。
その点に敏感な世代ではない著者、切通は宮崎は無国籍のアニメから日本を舞台にしたアニメに転換したと単純に分析する。だがそれは宮崎とパートナーである高畑 勲が痛いほど感じていた戦後直後の依存症からの脱却であったに違いない。とはいえ初期のアニメのほとんどを日本が舞台だったと思い込んでいた若いファンも多くいたことを知れば、アニメ、いや映像に国籍を意識させる必要がないことを、本書で論じる必要があっただろう。
第4章が面白い。ことに「身体の開放」「落下の持続」「落下の決意と飛翔」の項で、宮崎アニメにとって、飛翔のカタルシスを手に入れるためには、いったん落ちなければならない、その飛翔を効果的に演出するために宮崎は縦の構図をとる、と分析しているところだ。さらに落ちる、その瞬間にふわりと浮上するのも特徴だ、と。
最終章「フレームを越えた表現」でも宮崎の自然観を見事に引き出している。建築家フンデルト・ヴァッサーと荒川修作の自然を見る目に共感しながら「人間が自然に手を入れた以上、それにとことん手を加えなければいけない……」と語った宮崎は新しい自然の構築に関心を示しだした、という点だ。単なるエコメッセージを届けるアニメではない、と。
本書はアニメファンになりそこねた世代に、なぜ若者が宮崎に魅了されるか、つまり現代の若者の感受性の行方、飛翔感、善悪二極の希薄さ、懐かしさ、ひたむきさ、愛、などなどを著者、切通を鏡にして読み取らせる書物でもある。デザイナーの理想をどこまで製品に反映させてきたかの検証材料にもなる。残念ながら、2,000万人近い観客を動員する製品を生産するカリスマ的人間像に迫りたいと奮闘しつつも、思いの過剰さが著者自身の言葉で宮崎という人物に迫ることをためらわせている。その点でアニメファン以外の読者に不満を残す。いやそれは次作で、と答えるだろうがそのときは手塚、ディズニーなどの人物像との対決も期待したい。(AXIS 95号/2002年1・2月より)
「書評・創造への繋がり」の今までの掲載分はこちら。