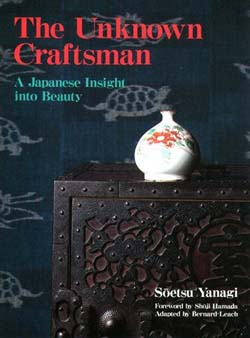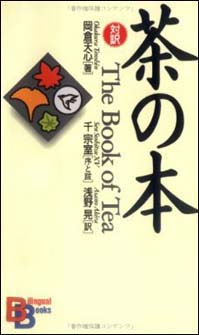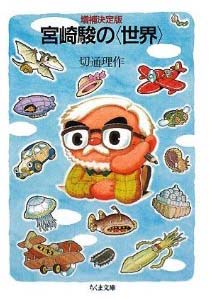『小説ソウル』
荒木経惟 著(スイッチパブリッシング・3,400円)
評者 竹原あき子(デザイナー・和光大学教授)
「生きることを正面から見つめよ」
10年間かけて数千点撮りためた写真からおよそ300点。釜山行きらしいフェリーの甲板から見上げたぬけるほど黒い青空にはじまり、スープにされるまでを金属パイプの檻の中で待つ犬で終わるソウルの写真集。「小説」と命名した荒木らしい息遣いがこの最初と最後の2点に凝縮され る。写真を読めと読者に迫る。
3つの読み方がある。すでに荒木のファンなら中上健次との共作『物語ソウル』(パルコ出版局・1984年)を横に置いて初めからページをめく る。荒木をエロスのカメラマンと認識する読者なら、第1回太陽賞(1964年)に輝いた写真集『さっちん』(新潮社・1994年)を読んでから。荒木を何者かも知らず偶然手に取ってしまった読者なら、パラパラアニメのように、3センチほどの分厚い束を握って最後のページから親指で最初の頁に向かって紙をしごきあげる。何回も何回も。そして時たま1枚を凝視しよう。ソウルの町と人がザワザワと動き、読者の過去と重なる微細な部分に心が揺れる瞬間を待とう。
フランスの社会学者・記号学者のロラン・バルトは画家トゥオンブリの絵画について、彼のカンバスは、つねに、ある偶然の力、「幸運」を含んでいる、と書いていたが、荒木の写真にも同じ現象がある。荒木の作品のひとつひとつが細かな計算の結果であるかどうかは大した問題ではない。大事なのは矢継ぎ早に投げ出すようにフィルムに映し撮った彼の写真の偶然の効果なのだ。その効果とは、荒木の物語には読者が入り込む隙間があることだ。だからといって彼がシャッターを切る瞬間に自分が何をしているのかわかっていても、それが呼び起こす結果について認識しているわけではない。だが荒木の紡ぎ出した写真の隙間という効果に読者は束の間の偶然の力、「幸運」を手にする。
アスファルトが禿げてできた雨上がりの水たまりに、無心に自分を映す3人の子供の写真。水鏡の向こうに何があるのかと探り、靴をはいたまま水を蹴り上げる快感に酔い、映った自分の顔に驚く子供。そのページに立ち止まった読者の過去がソウルの路上と重なり、至福の瞬間が過ぎる。
青い林檎、黄色のメロンを入れた野菜篭、真っ赤なシャツを着た母親らしき人物の視線の向こうでゴザに仰向けになって眠る青い服を着た幼児の安心しきった表情。ソウルの市場の何気ない風景なのに、どこか過ぎ去ってしまった自分の夏の幸せを噛みしめる。荒木の偶然の力、を読者はここに体験する。
アスファルトの凹みもない10年後の雨上がり。黄色い雨カッパを着た子供は母親の後ろをうつむき加減に追いかけ、母の視線は前方にしかない。都市の近代化はそこに生きる人の物腰も、表情も、視線さえも変えた。『小説ソウル』は都市の変わりようが人を変えた物語でもある。ヨーロッパの流行雑誌を切り抜き、張り込み、企画を練ることを生業としてきたデザイナーに、もうそこから抜けて、生きることを正面から見つめよ、と警告する小説でもある。(AXIS 93号/2001年9・10月より)