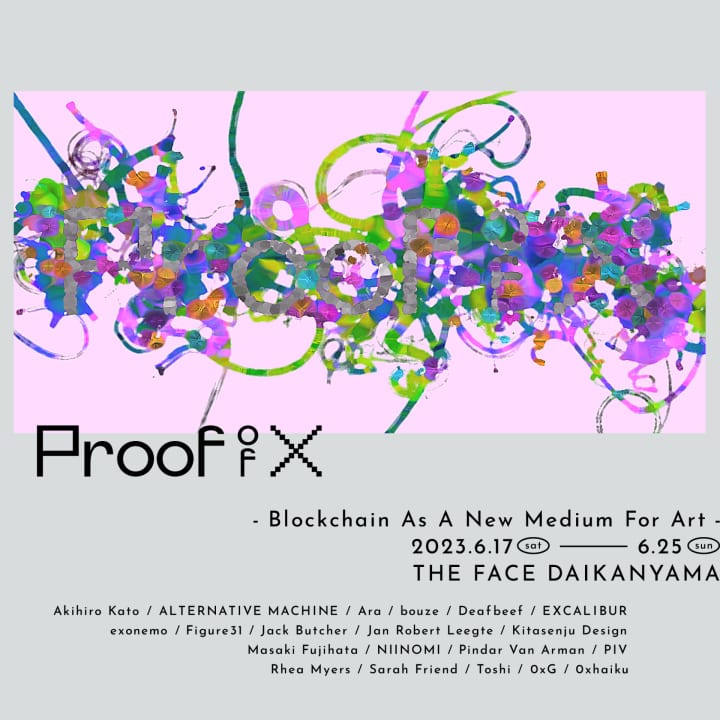MEMBERSHIP | アート / グラフィック
2025.04.15 11:36
写真とグラフィックデザイン。どちらも2次元のイメージを扱う表現であり、画面を構成するさまざまな要素をコントロールしながら、見る者の認知や記憶に訴えかけるコミュニケーション手法だと言えるだろう。2025年2月27日(木)から東京都写真美術館(TOP)で開催されている「鷹野隆大 カスババ ―この日常を生きのびるために―」のグラフィックデザインをデザイナーの北川一成が担当した。展示作家である写真家の鷹野隆大とのコラボレーションによって生まれた2種類のグラフィックデザインには、どのような制作プロセスがあったのか。両者の対話から写真とグラフィックデザインの関係や、写真家とグラフィックデザイナーのコラボレーションの可能性を探る。

左から鷹野隆大(たかの・りゅうだい)/写真家・アーティスト。セクシュアリティをテーマとした作品と並行し、〈毎日写真〉や〈カスババ〉といった日常のスナップショットを手がけ、国内外で活躍している。北川一成(きたがわ・いっせい)/デザイナー・アーティスト。主宰するGRAPH(グラフ)であらゆる領域のビジュアルデザインのほか、ビジネスやコミュニケーションのあり方までを設計するブランディングを多数手がけている。
リズムを狂わせる独特の雰囲気
――まずは、おふたりの出会いについてお聞かせください。
鷹野:昨年国立西洋美術館で開かれたグループ展に参加した際に、私の所属するギャラリーのオーナーに北川さんをご紹介いただきました。その時に、北川さんが私の展示作品を次々に解釈してくださったのですが、それが非常に的確で、瞬時に言語化する能力がちょっと怖いくらいでした(笑)。
北川:鷹野さんの作品を拝見して、科学的だなと感じました。作品に宿る身体性もさることながら、「人間とは何か?」ということを解剖学者さながらの解剖しているようなアプローチに興味を持ちました。まるで時計に興味を持った子どもが好奇心からそれを分解するように、自分が感動したことや興味を持ったことをバラバラにしたり、組み直したりしていくような。本当に優れた芸術や発明レベルの科学、0から1を生み出すイノベーションといった、唯一無二のものは高度な計画性や先見性がないと生まれないと思うのですが、鷹野さんはそうした代えがたい表現をされるアーティストだと思ったんです。
鷹野:いまもよく覚えているのは、「変態やな」という北川さんの言葉でした。