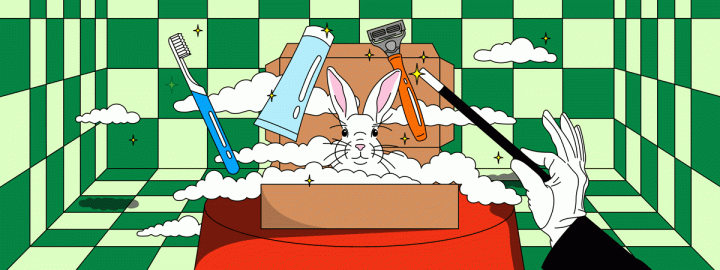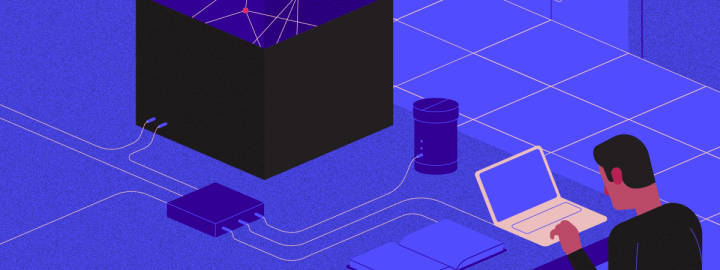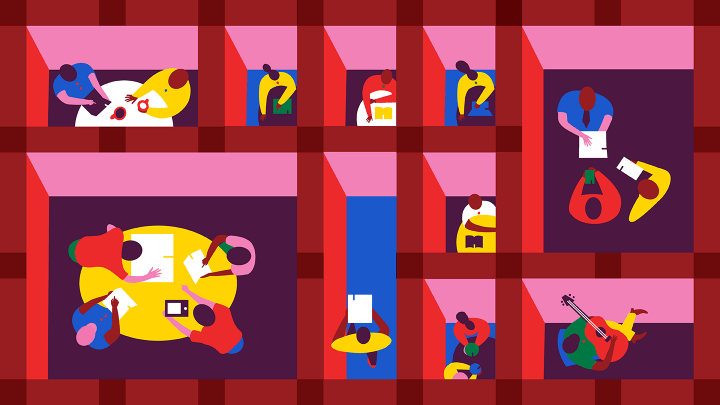
論理に偏った思考が、オープンオフィスを失敗に終わらせた
仕事をする席を自由に選べる「オープンオフィス」(フリーアドレスオフィス)の概念は、ユートピア的なビジョンから生まれました。ところが、現実のオープンオフィスでは、しばしば魚が泳ぐ水槽やシアターコーナーなどが設けられ、かえって気が散りがちです。また、デスクのレイアウトによっては、人の入れ替わりで作業効率が下がり、ストレスが増すだけの結果に終わりました。
それでもfrogを含めた多くの設計者たちが、オープンオフィスをつくり続けています。なぜならば、実現しづらくはあっても、オープンオフィスには、経済的なメリットや共同作業がしやすくなる可能性が依然としてあるからです。
2019年6月にノルウェーの電力会社Equinor(エクイノール)で、オープンオフィス型イノベーションラボの開設記念イベントが行われました。これは、frogが実践してきた空間づくりの試みにとって誇らしい出来事でした。多くの失敗例のある分野でいかに成功するかを、何カ月も真剣に考え続けた努力が形になった瞬間だったからです。
frogのデザイン担当チームが直面したのは、キューブファーム(パーティションで仕切られた小部屋が並ぶ従来型のオフィスフロア)における悩みの種と何ら変わらないスペースの制約でした。約200m2弱の限られた空間に、三つの研究開発チームの業務スペースを収める必要があったのです。
最大の不安は、スペースの制約によってデザインチームの思考が制約されるのではないかという点でした。オープンオフィスの概念の原型である1950年代のBürolandschaft(オフィス風景)と呼ばれた運動は、オフィス空間の杓子定規な仕切りと階層を排し、個人にフォーカスした有機的なレイアウトや備品を取り入れようとするものでした。しかし、1970年代には経済性を重視した結果、味気ないキューブファームへと退化してしまいました。これと同じようなことが起きるのではないかと恐れたのです。
カナダの小説家ダグラス・クープランドが「子牛を太らせるための家畜小屋」と呼んだキューブファームは、個室のないレイアウトという物理的な形態は同じですが、当初のオープンオフィスの概念にあった人の感情や意欲に訴える特性は一切取り入れられていませんでした。
順応性のあるワークスペースを求める声がようやく高まってきたのは、デジタル時代が訪れ、週40時間のデスクワークに代わるさまざまな働き方が広まり始めてからのことです。そこで私たちは、もう一度Bürolandschaft「オフィス風景」の精神を再解釈することはできないかと考えました。
それは考えが甘いんじゃないか? デザイナーが現実からかけ離れた思想に心酔するという、よくある例に過ぎないのでは?——そう思う人もいるでしょう。しかし、私たちはそうは思いません。実際にオフィスで働く人たちに話を聞くなかで、有機的で融通性の高いオフィス環境は今の時代にこそふさわしいことがわかりました。
私たちはエクイノール社内の技術研究のさまざまな側面を検証した結果、空間デザインに従業員を合わせるのではなく、空間の方が従業員とその仕事に適応する多層的なオフィス環境をつくろうという構想にたどり着きました。
広範な分野の専門知識を活用したこの種の多層的なデザインは、デジタル世界と物理世界の融合が進むなかでますます一般的になりつつあります。エクイノールのイノベーションラボでは、建築、ビジュアル/インタラクションデザイン、テクノロジー、業務プロセス、ユーザー調査の知識を結集し、真の意味で組織化された環境をつくり上げました。
取り組んだのは、さまざまなデザイン手法を用いて未来を構築する、一種のスペキュラティブデザイン(「こうもあり得るのではないか」というビジョンに対し、人々が理解しやすい高い精度でデザイン化する事で、問題を提起しながらアイディアの種を生み出すデザイン手法)です。
それぞれの企業には、従業員に対して思いやりのある未来もあれば、そうでないものもあります。私たちはまず徹底したデザインリサーチを行い、個人のニーズを集め、ワークフローを明らかにしました。それを元に技術的な要件を決定した上で、そうしたニーズに今後何年にもわたって応える空間を多層的なアプローチによって構築しました。
ユーザー中心のデザインは、物理的空間そのものではなく意識から始まります。デザインリサーチの主な目標のひとつは、エクイノールにとって「イノベーション」という言葉が何を意味するのかを明らかにすることでした。彼らにとってのそれは、難しい問題を解決するためにグローバルで分野横断的なチームを迅速に編成することだったのです。つまり、誰もが自分の分野のツールや手法を使って、各々の専門知識で直接的にプロジェクトに貢献できることを意味するのです。
別の言い方をすれば、職場とは個々の参加者に順応しながら、その場でイノベーションが生み出される舞台だということです。そのような職場には、近くの人と交流する空間、チーム作業をする空間、一人で集中する空間、実験ができる空間、イベントを行う空間が必要です。これらの空間の適切な配分をみつけることが、今回のデザインの核心でした。
各活動の構成比率は組織によって異なるため、それぞれ独自の空間配分が求められます。これを適切なバランスで配分すれば、使う人は自分が仕事をしたい環境を選ぶことができます。床面積が狭く、イノベーションラボの動的な性質を考えれば、上記のすべての空間を必要に応じて提供できるデザインにすることが必要でした。
順応性の高い環境は技術だけでは構築できないため、インテリア空間のレイアウトや雰囲気をどのようにデザインするかを発想し直す必要がありました。各構成要素を体系的にデザインし、チームのワークフローを破綻させたりすることなく、大規模な投資をかけずに空間を構成し直せるようにしました。
今回のエクイノールの事例では、各チームはわずか数分で空間の構成を変えることができます。オフィス家具はモジュラー式でキャスターが付いており、スムーズに移動できます。テクノロジー機器(スクリーン、カメラ、電源など)は、さまざまな空間で使用できるように戦略的に配置しました。数少ない静的な空間は、主に各自で集中して仕事をするためのスペースで、部屋の周辺部に沿って配置しています。
さらに、複数のチームがひとつの室内で仕事をする環境では、音環境の制御がカギになります。空間の機能性と各チームが集中できる環境を維持するには、騒音を相殺できる機能が必要不可欠です。私たちは資材やオフィス家具の選定に加えて、サウンドマスキング技術を採用することでこの問題を解決しました。
改修や新築のためのコストは、どんな組織にとっても莫大な投資です。私たちはデザイナーとして、組織にとって有効に機能し、組織と共に生き、変化していく環境を構築する責務があります。
かつてオフィス家具メーカー、ハーマン・ミラー社のロバート・プロプストがデザインした最初のパーティション式オフィスシステム「アクション・オフィス」と、その改良版「アクション・オフィスII」は、カスタマイズ性に重点が置かれていました。パーティションの配置、個人用スペースのパーソナライズ化が可能で、レイアウト変更もしやすく、1960年代の適応可能型オフィスのすべての要件を満たすシステムでした。
しかし、これまで各企業が犯した間違いは、この種のシステムの形態だけを採用し、その精神を取り入れなかったことです。空間の有効活用というただひとつの指標を最大化するために、トップダウンで全社一律に導入したまでで、企業の業務——あるいは「行動」——に従って、それを支える空間の使い方を決めるという形をとらなかったのでした。
今こそ私たちの行動基準を転換し、私たちがつくる場所で生活し仕事をする人々へと再び目を向ける好機です。![]()
この記事は、frogが運営するデザインジャーナル「DesignMind」に掲載されたコンテンツを、電通CDCエクスペリエンスデザイン部・岡田憲明氏の監修でお届けします。