
首都大学東京 インダストリアルアート学域の授業「プロダクトデザイン特論D」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。
鈴木康広の“ものごと”への姿勢・視線の向け方
今回は「ファスナーの船」や「空気の人」「まばたきの葉」などの作品で知られるアーティスト、鈴木康広さんへのインタビュー。鈴木さんのユニークな作品やアイデアはどのように生まれてくるのか、“ものごと”への姿勢、視線の向け方などについて聞きました。
素材がもっと良い方法を教えてくれる
——大学では家具コースを専攻していたとのことですが、高校時代から美大を志していたのでしょうか。
高校までは普通科で、自分のまわりに専門的なデザインという言葉を発するような人はほとんどいませんでした。消去法で理系の生物クラスという、いちばんつぶしが利かないところに追い込まれていって……。ただ、生物に興味を持ったということは、今の自分にとってとても生きています。生物学は非常に曖昧な学問だと思っていて、ユクスキュルという有名な生物学者の「生物から見た世界」という本にも書いてあるんですが、生物学自体が人間主体で、生物の気持ちというか、生物側にはなれないと。そういう大きな難問を抱えながら、人間は科学として生物を扱ってきた、客観的な視点でいくら物事がわかっても、生き物側にはなれない。絶対に到達できない他者の視点というか、限界をもった自分自身の視点そのものの成り立ちがすごく気になっていました。子どものころからの数学と国語への苦手意識から、最終的には「美大しかない」と思って受験しました。
——子どものころはどのように過ごされていたのでしょうか。
うちは親がスーパーマーケットをやっていて、屋根付きのダンボール置き場みたいなところを基地のようにしていました。ダンボールのほかにも発泡スチロールやセロハンテープ、包装紙など、そこにあるものは何でも使っていいと言われていたので、それらで遊び道具をつくっていました。
特に印象に残っているのは野球のグローブです。ダンボールを揉んで柔らかくして、ちゃんと型紙をつくって……。すごく興奮しました。売っている物も持っていたのですが、自分でダンボールとか他の素材で再現するのが楽しかったんです。それは自分にとって、デザインという視点やものづくりの入口だったと思っています。
例えば、粘土でいろんなものをつくるというのが、ひとつの造形的な訓練としてありますが、訓練すればするほど、素材の扱いに慣れてくると思います。手と粘土が協力しあうようになってくるんです。はじめは粘土は他人のようなもので、しっかりと相手の性質を認めると手と粘土が協力しあうようになってくるんです。だんだんと粘土が「鈴木君に協力するよ」みたいに言ってくれる。なので、こちらも「ありがとう」とか言って。素材を扱っていると、もっと良い方法を素材自体がこっそりと教えてくれるんです。それがとにかく楽しくて。

パラパラマンガにいちばんときめいた
——大学に進学してからは現在のようなアーティストの活動を想定していたのですか。
大学時代はコンセプトを立ててものをつくるというよりは、職人になりたかったんです。家具職人とか靴職人とか。木工にはまったり、裁縫に興味を持ったり、簡易的な卓上織り機をつくって織物をしてたりしていました。でも3カ月から半年くらい経つと飽きちゃうんです。自分の中でブームが去ってしまうことに気づきました。木工は2年くらい取り組んだんですけどね。
——意外と飽き性なんですね。
素材が次々協力してくれて盛り上がるんですけど、次にやりたいことが見えてきてしまって。職人というのは、ものとゆっくりきちんと付き合うものですよね。もしかすると職人は「自分にはこれしかない」みたいな思い入れが強いのかもしれない。僕の場合はなかなかそうはならなくて。特に大学生になって、初めて見るものに、あれも面白いこれも面白いと次々ときめいてどんどん興味持った時期でした。
最終的にいちばん性に合っていたのはパラパラマンガです。パラパラマンガは下に書いたものが透けて見えるので、そこから1コマずらして描くことはそんなに難しいことじゃない。でもちょっとずらさなきゃいけないから飽きないし、下のコマを見ていると自ずと次を思いつける。ちょうどいいんです。思いつきや書き損じが、面白い方向に転がっていくこともある。意図を超えたところに成果が生まれるパラパラマンガにいちばんときめきましたね。

余白をあえてデザインする
——パラパラマンガのほかに現在の活動につながるような習慣はありますか。
たいしたことではないんだけど、スケッチやメモをとります。ノートに描いた簡易な絵や言葉を見返して、さらに思いついたことをその周辺に描く、ということをやっています。確かなアイデアや考えというより、なんか自分が「おっ!」と思った、というところに意味があるかなと思っているんです。
——ノートは肌身離さず持ち歩いているんですか。
そうですね。カバンにノートを何冊か入れていて、「おっ!」と思ったら、取り出して、空いてるページを探して描くんですが、描き始めるまでに数十秒間かかるんですよね。それで、その時間が実は必要なんじゃないかと、人から指摘を受けたことがあります。「おっ!」と思ってから、「どう描こうかな」と、その間に考えているそうなんです。カメラならすぐ撮ったほうがいいけど、ノートの場合は写真で撮ろうと思ってない部分、つまり、それを見て触発された“何か別のもの”について、「どう描こうかな」「次見たときにもっと面白くしたいな」という気持ちが働く。見たそのままじゃなくて、その次を予感するモードに入ってる。編集しているとも言えますね。そのためにはちょっと時間が必要で、ペンのキャップを外して、ページを探して、という時間は結構大事なんです。
今はノートパソコンでもなんでもすぐに立ち上がるように設計されています。それがひと昔前のデスクトップなんてボタン押して立ち上がるまでの間にコーヒーを一杯入れられる。その時間がすごく良かったと聞いたことがあります。音楽を一曲聴いてしまう時代もあったとか。心の準備というかウォーミングアップの“間”があったのかもしれません。そういう時間を省いてしまうのは、クリエイターにはすごくリスキーなのかなと思ったりします。一見すると無駄な時間というか、余白をあえてデザインするって、難しい問題ですよね。
つまり、仕方なかったみたいなものを意図的に入れる、これがデザインの課題なんじゃないかと思っています。わざわざ面倒にするとか、わざわざ使いにくくして、不便にして、さらに工夫するとか、そういうことは意外とできないものです。その後戻りできないものに対してデザインがどうやって最適なものを人間にきちんとフィードバックできるか。クリエイターとして作品というひとつの成果物を示すことで、「こういう無駄なことが実は役に立っているんじゃないか」と言えたらいいなと思っているんです。(取材・文・写真/首都大学東京 インダストリアルアート学域 渡邉康太/秋山夏穂/・安達耀一郎/太田 誠/鶴田大翔/厳亦斌/李林嬡/方瀅瀅)![]()
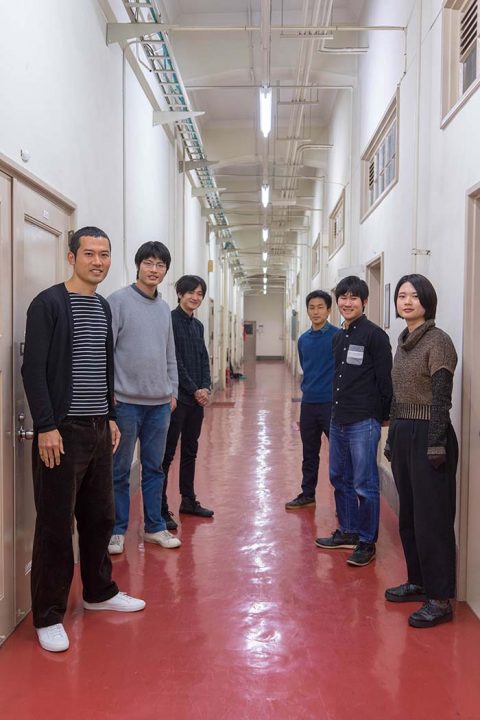
鈴木康広/1979年静岡県浜松市生まれ。東京造形大学デザイン学科卒。日常のふとした発見を通じ、誰もが知っているものを新鮮な感覚でとらえ直す作品を制作。代表作に「ファスナーの船」「まばたきの葉」「空気の人」など。2014年に水戸芸術館、17年に箱根彫刻の森美術館で個展を開催。16年「第1回ロンドン・デザイン・ビエンナーレ」に日本代表として参加。15年毎日デザイン賞受賞。現在、東京大学先端科学技術研究センター中邑研究室客員研究員、武蔵野美術大学空間演出デザイン学科准教授。
http://www.mabataki.com












